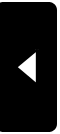2012年07月24日
スポーツ関係以外でも…
先日「奄美地域労働福祉協議会」の定期総会後に行われる
講習会の講師としてよばれました。

テーマは「熱中症」
この季節、定番ですね。
とはいえ、スポーツ関係以外の対象者への講義は未経験だったので、
さて、どう話を持っていったらいいのでしょう・・・
いろいろ調べていくうちに、
労働者に対して、熱中症を警告するポスターと出会い・・・
非常に端的にまとめてあったので、
このポスターに書いてある内容を、さらに詳しく説明することにしました。
意外とシビアなタイトルですよ。
『警告!死を招く熱中症』
スポーツの世界ではご法度に近い「死」という表現・・・
いやはや、でもこれくらいあれば、目を引きますね。
30分の講義でしたが、意外と多くの方が聞いてかえって下さり、
緊張の30分・・・笑いもあり、有難かったです・・・
皆さんの温かさに救われました。感謝。
でも。
昔は
「水は飲むな」
・・・の世界で育った私たち。
なんで、いつから、こんなに「熱中症」「水分補給」、うるさくなったの?
素朴な質問を受けました。
私なりの解釈でしかお答えできませんでしたが…
「家電の充実」「科学の進歩」「教育システムの変貌」
時代は確実に「変化」していて、
『便利な世の中』の恩恵を受けることと引き換えに、
様々な弊害や考え方の違いももたらすものだと思います(思うことにしました)。
昔から「日射病」という言葉はありました。
しかしながら、屋内にいる人たちにも似たような症状が出ていたことがわかったのでしょう。
似たような症状の総称が「熱中症」で、症状の違いで分類がされています。
便利な世の中は、確実に子供達のみならず、大人の体力低下も反映します。
クーラーなしでは夏を乗り切れない人も、たくさんいることでしょう。
とかく、夏は体力が消耗されるので、暑さに負けない体力が必要となります。
暑さに弱い人も「熱中症」の予備軍ともいえると思います。耐性には個人差があります。
果たして、暑さから「身を守る」という事は本当はどういう事なのでしょうか・・・?
昔の考え方も、あながち間違えではないことも沢山あると思います。
もしかしたら、また時代は巡って・・・
『水はやっぱり飲まない方がいいらしい』
なんて日も来るかも(来ないか・・・)。
アラフォーに確実に近づきつつある私も・・・
時代の波に取り残されないよう、変化していきたいものです。。。
講習会の講師としてよばれました。

テーマは「熱中症」
この季節、定番ですね。
とはいえ、スポーツ関係以外の対象者への講義は未経験だったので、
さて、どう話を持っていったらいいのでしょう・・・
いろいろ調べていくうちに、
労働者に対して、熱中症を警告するポスターと出会い・・・
非常に端的にまとめてあったので、
このポスターに書いてある内容を、さらに詳しく説明することにしました。
意外とシビアなタイトルですよ。
『警告!死を招く熱中症』
スポーツの世界ではご法度に近い「死」という表現・・・
いやはや、でもこれくらいあれば、目を引きますね。
30分の講義でしたが、意外と多くの方が聞いてかえって下さり、
緊張の30分・・・笑いもあり、有難かったです・・・
皆さんの温かさに救われました。感謝。
でも。
昔は
「水は飲むな」
・・・の世界で育った私たち。
なんで、いつから、こんなに「熱中症」「水分補給」、うるさくなったの?
素朴な質問を受けました。
私なりの解釈でしかお答えできませんでしたが…
「家電の充実」「科学の進歩」「教育システムの変貌」
時代は確実に「変化」していて、
『便利な世の中』の恩恵を受けることと引き換えに、
様々な弊害や考え方の違いももたらすものだと思います(思うことにしました)。
昔から「日射病」という言葉はありました。
しかしながら、屋内にいる人たちにも似たような症状が出ていたことがわかったのでしょう。
似たような症状の総称が「熱中症」で、症状の違いで分類がされています。
便利な世の中は、確実に子供達のみならず、大人の体力低下も反映します。
クーラーなしでは夏を乗り切れない人も、たくさんいることでしょう。
とかく、夏は体力が消耗されるので、暑さに負けない体力が必要となります。
暑さに弱い人も「熱中症」の予備軍ともいえると思います。耐性には個人差があります。
果たして、暑さから「身を守る」という事は本当はどういう事なのでしょうか・・・?
昔の考え方も、あながち間違えではないことも沢山あると思います。
もしかしたら、また時代は巡って・・・
『水はやっぱり飲まない方がいいらしい』
なんて日も来るかも(来ないか・・・)。
アラフォーに確実に近づきつつある私も・・・
時代の波に取り残されないよう、変化していきたいものです。。。
2012年06月30日
子供達の可能性
今日は、娘がお世話に
なっている「大島Jr新体操クラブ」の方で…
こんな私の活動に興味を持って下さるお母様からの希望で、
貴重なお時間を頂いてストレッチや姿勢について、解剖学や運動学の方面から「解説」させて頂きました。
まず、思ったのは…
私も2人の娘の親ですが、
お母さんの、我が子を思う気持ちの強さを(日々、活動の中で常に感じつつも…)
「我が子の為に、何か自分が出来ることはないのだろうか?」という親心を
今日アドバイスしながら、そのエネルギーを一心に感じました。
私は、最初のこの仕事の対象は
「社会人のスポーツ選手」でした。
専門的なスポーツ能力を買われて、就職した、ある意味スポーツ選手ならば「成功」した人達です。
その後は県の代表チームになるようなの高校生のチーム、それからそんな選手が集まるような短大のチームでした。
日の丸予備隊の選手達も。
表舞台には出ていませんが、能力のある選手、素晴らしい選手にも出会える機会がありました。
小さい頃から続けてきた競技を、
高校、さらには大学まで続ける選択をする選手は、
競技人口のほんの一握り、
これもまた、ある意味競技者として「成功」した選手といえるのではないかと思います。
そして、現在、小学生、中学生と…
「未来」の可能性の詰まった選手をみる機会が増えた時、
心から思います。
「能力の開花は、このずっと先に待っているかもしれない。今出来なくても、才能がないわけじゃない。今の経験は、たとえ、形を変えたとしても、必ず糧となる。」
コツコツ続けてきた事が、高校・大学で花開く選手も沢山みてきています。
また、何らかのきっかけで競技を変えてその才能を発揮した選手も、います。
技術はそこそこでも、出会いやきっかけで新しい能力を発揮する選手も、沢山みてきています。
わかりやすく「成功」という表現をしましたが、もちろん、それ以外は「失敗」かというと、決してそうではありません。
どんな形でその競技を終えたとしても、
「やって良かった」
何より嬉しい瞬間です。
また、その裏では、必ず家族のサポートがあり、信頼があり、選手達は皆、親の有難さを感じ、いろんな苦悩を抱えながらも、今までを振り返り、感謝の気持ちを語ってくれました。
私は、トレーナーという仕事を通じて、
選手のこれまでの人生に触れる機会を経験してきました。
これは私にとって、トレーナーのみならず「母親」として、考えさせられるきっかけとなるわけです。
いつも、"対選手"にしか指導する場がほとんどの私にとって、
本当にお母さんを前に緊張し(笑)、私の拙いアドバイスを真剣に聞いて下さる姿勢に、逆にこちらが沢山の事を考えされた時間でした。
実際の指導内容に関しましては、思いつきとその場の感じでゴメンなさい(>_<)
また何か、同じ母親として、ご相談に乗れる事があればなぁと、思いました。
私もまた、我が子を思い、我が子の為を思って選択した環境と、出会いに感謝し
ながら、成長を見守っていきたいとおもいます。
なっている「大島Jr新体操クラブ」の方で…
こんな私の活動に興味を持って下さるお母様からの希望で、
貴重なお時間を頂いてストレッチや姿勢について、解剖学や運動学の方面から「解説」させて頂きました。
まず、思ったのは…
私も2人の娘の親ですが、
お母さんの、我が子を思う気持ちの強さを(日々、活動の中で常に感じつつも…)
「我が子の為に、何か自分が出来ることはないのだろうか?」という親心を
今日アドバイスしながら、そのエネルギーを一心に感じました。
私は、最初のこの仕事の対象は
「社会人のスポーツ選手」でした。
専門的なスポーツ能力を買われて、就職した、ある意味スポーツ選手ならば「成功」した人達です。
その後は県の代表チームになるようなの高校生のチーム、それからそんな選手が集まるような短大のチームでした。
日の丸予備隊の選手達も。
表舞台には出ていませんが、能力のある選手、素晴らしい選手にも出会える機会がありました。
小さい頃から続けてきた競技を、
高校、さらには大学まで続ける選択をする選手は、
競技人口のほんの一握り、
これもまた、ある意味競技者として「成功」した選手といえるのではないかと思います。
そして、現在、小学生、中学生と…
「未来」の可能性の詰まった選手をみる機会が増えた時、
心から思います。
「能力の開花は、このずっと先に待っているかもしれない。今出来なくても、才能がないわけじゃない。今の経験は、たとえ、形を変えたとしても、必ず糧となる。」
コツコツ続けてきた事が、高校・大学で花開く選手も沢山みてきています。
また、何らかのきっかけで競技を変えてその才能を発揮した選手も、います。
技術はそこそこでも、出会いやきっかけで新しい能力を発揮する選手も、沢山みてきています。
わかりやすく「成功」という表現をしましたが、もちろん、それ以外は「失敗」かというと、決してそうではありません。
どんな形でその競技を終えたとしても、
「やって良かった」
何より嬉しい瞬間です。
また、その裏では、必ず家族のサポートがあり、信頼があり、選手達は皆、親の有難さを感じ、いろんな苦悩を抱えながらも、今までを振り返り、感謝の気持ちを語ってくれました。
私は、トレーナーという仕事を通じて、
選手のこれまでの人生に触れる機会を経験してきました。
これは私にとって、トレーナーのみならず「母親」として、考えさせられるきっかけとなるわけです。
いつも、"対選手"にしか指導する場がほとんどの私にとって、
本当にお母さんを前に緊張し(笑)、私の拙いアドバイスを真剣に聞いて下さる姿勢に、逆にこちらが沢山の事を考えされた時間でした。
実際の指導内容に関しましては、思いつきとその場の感じでゴメンなさい(>_<)
また何か、同じ母親として、ご相談に乗れる事があればなぁと、思いました。
私もまた、我が子を思い、我が子の為を思って選択した環境と、出会いに感謝し
ながら、成長を見守っていきたいとおもいます。
2012年06月17日
スポ少交歓大会
今日の奄美地区は何処もスポ少の郡体予選だったのでしょうか…
うちの娘のチームの応援に、朝から太陽が丘へ
。

ま、正確にいうと、
娘のモッパーの応援に(笑)
今日は縁あって、龍郷町の方で閉会式後に「講習会」を依頼されていたので
夕方りゅうゆう館へ。
女子バレーの決勝をやっていました。

本当に暑い中、子供達頑張ってますね!
暑い体育館で、お疲れの中引き続き
拙い私の話なんて聞いてもらうのは恐縮でしたが…(ーー;)
クーリングダウンを兼ねて、また保護者や指導者もいらっしゃるという事で、
「親子で出来るアフターケア」
というテーマで、
「アフターケアの5本柱」として
ストレッチング
アイシング
マッサージ
食事
睡眠
うちストレッチングとマッサージは
親子さんにも一緒にして頂きました。
この内容でどうかな〜と思いつつ…
結構皆さん真剣に、楽しく取り組んで下さり、
私もとても楽しく終える事ができました(^^)
(龍郷町の参加して下さった皆様、有難うございました!)
私は、高校生や大学生を主に対象として仕事する事が多いのですが、
その時期でも、まだまだ伸び代十分!な子は全員だと、思うんです。
まだ、こんな事が出来るんだよ、まだまだ、あなた達は伸びる力があるんだよ…
私はいつも、来てくれた選手にはそう声を掛けてエールを送ります。
いや、それは事実であり、本心です!
それを思うと、
少年団の子達は、またまだたっくさんの可能性を持っています!
でも、成長期の真っ只中で、
体格も、理解度も個人差が大きい時期。
世のお父さん、お母さん、
今、目の前の子供達の能力を、「全て」だと思わないで下さいね!
子供達自身が"望めば"粘り強く頑張っていたら、
きっと、然るべき時期が来ると思うんです。
思うようにプレー出来る子も、
思うように出来ない子も、
根気強く、応援してあげて下さい!
そのチャンスをつかむ日の為に、
「健康」は自分で守ろうね…(^^)
モッパー少女も、
自信を持って仕事を全うした、ようで(^_^;)しっかりと褒めてやりました。
「バレーが楽しい」「スポーツが楽しい」と思わせてくれる環境を、子供達の為に作って下さる指導者の方々に、感謝です。
うちの娘のチームの応援に、朝から太陽が丘へ
。

ま、正確にいうと、
娘のモッパーの応援に(笑)
今日は縁あって、龍郷町の方で閉会式後に「講習会」を依頼されていたので
夕方りゅうゆう館へ。
女子バレーの決勝をやっていました。

本当に暑い中、子供達頑張ってますね!
暑い体育館で、お疲れの中引き続き
拙い私の話なんて聞いてもらうのは恐縮でしたが…(ーー;)
クーリングダウンを兼ねて、また保護者や指導者もいらっしゃるという事で、
「親子で出来るアフターケア」
というテーマで、
「アフターケアの5本柱」として
ストレッチング
アイシング
マッサージ
食事
睡眠
うちストレッチングとマッサージは
親子さんにも一緒にして頂きました。
この内容でどうかな〜と思いつつ…
結構皆さん真剣に、楽しく取り組んで下さり、
私もとても楽しく終える事ができました(^^)
(龍郷町の参加して下さった皆様、有難うございました!)
私は、高校生や大学生を主に対象として仕事する事が多いのですが、
その時期でも、まだまだ伸び代十分!な子は全員だと、思うんです。
まだ、こんな事が出来るんだよ、まだまだ、あなた達は伸びる力があるんだよ…
私はいつも、来てくれた選手にはそう声を掛けてエールを送ります。
いや、それは事実であり、本心です!
それを思うと、
少年団の子達は、またまだたっくさんの可能性を持っています!
でも、成長期の真っ只中で、
体格も、理解度も個人差が大きい時期。
世のお父さん、お母さん、
今、目の前の子供達の能力を、「全て」だと思わないで下さいね!
子供達自身が"望めば"粘り強く頑張っていたら、
きっと、然るべき時期が来ると思うんです。
思うようにプレー出来る子も、
思うように出来ない子も、
根気強く、応援してあげて下さい!
そのチャンスをつかむ日の為に、
「健康」は自分で守ろうね…(^^)
モッパー少女も、
自信を持って仕事を全うした、ようで(^_^;)しっかりと褒めてやりました。
「バレーが楽しい」「スポーツが楽しい」と思わせてくれる環境を、子供達の為に作って下さる指導者の方々に、感謝です。
2012年06月05日
救急法救急員の資格更新
日曜日、日本赤十字社鹿児島支部へ行ってきました。

三年ごとに4日日程で更新してきた救急法救急員の資格も、今年度は、な、な、なんと一日で更新出来るなんて(涙)!
離島住まいには、ありがたーい(^^)
トレーナーの資格更新にも、必ず「心肺蘇生法」「AED」の資格は必要です。
昨年度、改訂版が出て内容も変わっていました。
AEDで解析、ショック後も、AEDの指示に従って心肺蘇生を二分間続けます。
結構、これがきつい…汗だくです。
プロでも確実な心肺蘇生は3分間が限界だそうです。
今年もお世話になりました~

人が倒れています!

大出血等、なし!
AEDの使い方も、すっかり忘れていました(ーー;)危うく、私が感電するところだった。
その他、三角巾を使った包帯法や回復体位の取り方、搬送法などおさらいしました。
無事、終了。
そのまま、港へむかい、鹿児島を後にしました。

さようなら、桜島~
どか灰が凄かった(ーー;)うっすら舞っているのも灰です。

台風接近で心配されましたが、全く揺れず、快適な旅。
いつも、ありがとう。

三年ごとに4日日程で更新してきた救急法救急員の資格も、今年度は、な、な、なんと一日で更新出来るなんて(涙)!
離島住まいには、ありがたーい(^^)
トレーナーの資格更新にも、必ず「心肺蘇生法」「AED」の資格は必要です。
昨年度、改訂版が出て内容も変わっていました。
AEDで解析、ショック後も、AEDの指示に従って心肺蘇生を二分間続けます。
結構、これがきつい…汗だくです。
プロでも確実な心肺蘇生は3分間が限界だそうです。
今年もお世話になりました~

人が倒れています!

大出血等、なし!
AEDの使い方も、すっかり忘れていました(ーー;)危うく、私が感電するところだった。
その他、三角巾を使った包帯法や回復体位の取り方、搬送法などおさらいしました。
無事、終了。
そのまま、港へむかい、鹿児島を後にしました。

さようなら、桜島~
どか灰が凄かった(ーー;)うっすら舞っているのも灰です。

台風接近で心配されましたが、全く揺れず、快適な旅。
いつも、ありがとう。
2012年05月29日
「歌」と「スポーツ」の共通点
3週に渡ってボイストレーナーの先生にご指導いただいた最終日でした。
「腹式呼吸が知りたい」というところから、始まったレッスンでしたが、
今まで自分が「使っている」と思い込んでいた『腹筋』は半分くらいなもんだった、
という事実を身を以て知り、
実際、発声をする=パフォーマンス とつなげることのむずかしさ、
でも、この「基礎体力」があるからこそ、
さらに自分の能力の可能性に幅を持たせることができるし、
パフォーマンスに「余力」が生まれる。
そして、
「今よりもうまくなりたい」という強い思いが、新たな”道”をつくり、
的確なアドバイスをもらえる人と出会える”運”を呼び込み、
素直な心でアドバイスを実践できる人間性をもち、たゆまぬ努力が出来る人が
確実に実を結ぶ。
今までのご指導の経験から、貴重なお話を聞かせていただきました。
感謝の気持ちでいっぱいです。
しかも、先生から逆に「ヨガ」を勧めていただき、
「ヨガ(スポーツ)と歌って繋がっているんだな~って思うから」と聞いたときには、
ちょっと驚きましたが、
私も、さっそく始めてみました(笑)。概ね、最後(無空のポーズ)には、疲れて爆睡・・・
ヨガの「集中力」は、歌とも、スポーツとも良く似た感覚・・・
心理用語でいえば「フローな状態」でしょうか・・・
あの感覚はトレーニングによって身につける事ができるかもしれない。
どこまで現場で取り入れられるか、と思案中(←ウソ)
・・・あまり細かいことは考えていませんので、
近いうちに体育館かどこかでCDを流して集団ヨガを試していることでしょう(笑)。
とにかく予想以上に、「歌うこと」は「スポーツ」と繋がりを持ち、
私のトレーナー活動において、視野が広がったことには間違いありません。
今度は、この「歌」の感覚を
「スポーツ」の感覚として伝える言葉に変え、動きに変え、
選手自身も知らない、限りない能力を引き出すツールにしたいと思います。
先生との出会いに感謝です。
「腹式呼吸が知りたい」というところから、始まったレッスンでしたが、
今まで自分が「使っている」と思い込んでいた『腹筋』は半分くらいなもんだった、
という事実を身を以て知り、
実際、発声をする=パフォーマンス とつなげることのむずかしさ、
でも、この「基礎体力」があるからこそ、
さらに自分の能力の可能性に幅を持たせることができるし、
パフォーマンスに「余力」が生まれる。
そして、
「今よりもうまくなりたい」という強い思いが、新たな”道”をつくり、
的確なアドバイスをもらえる人と出会える”運”を呼び込み、
素直な心でアドバイスを実践できる人間性をもち、たゆまぬ努力が出来る人が
確実に実を結ぶ。
今までのご指導の経験から、貴重なお話を聞かせていただきました。
感謝の気持ちでいっぱいです。
しかも、先生から逆に「ヨガ」を勧めていただき、
「ヨガ(スポーツ)と歌って繋がっているんだな~って思うから」と聞いたときには、
ちょっと驚きましたが、
私も、さっそく始めてみました(笑)。概ね、最後(無空のポーズ)には、疲れて爆睡・・・
ヨガの「集中力」は、歌とも、スポーツとも良く似た感覚・・・
心理用語でいえば「フローな状態」でしょうか・・・
あの感覚はトレーニングによって身につける事ができるかもしれない。
どこまで現場で取り入れられるか、と思案中(←ウソ)
・・・あまり細かいことは考えていませんので、
近いうちに体育館かどこかでCDを流して集団ヨガを試していることでしょう(笑)。
とにかく予想以上に、「歌うこと」は「スポーツ」と繋がりを持ち、
私のトレーナー活動において、視野が広がったことには間違いありません。
今度は、この「歌」の感覚を
「スポーツ」の感覚として伝える言葉に変え、動きに変え、
選手自身も知らない、限りない能力を引き出すツールにしたいと思います。
先生との出会いに感謝です。
2012年05月23日
勝負の世界
第二回目、ボイストレーニングを受けさせて頂きました(^_^;)
自分なりに、先週ご指導頂いた「腹式呼吸」を一週間毎日試してきました。
通常は、歌を本格的に歌うなかで、
さらにステップアップしたい方が、問題を解決すべくこういう所を訪れるのだとおもいますが、
私は全くのド素人…
声の変化はわかりませんが、
身体の変化は感じました。
ストレッチするより、腹部を呼吸と共にしっかり使うほうが、筋肉が緩む…
ムダな力が抜けて、
上半身の軽さと、下半身の安定感を感じました。
当然、ベーシックな身体作り、土台作りの一つの方法でしかないので、
ここからどうパフォーマンスに繋げるか、技術的な練習をする必要があるのは、
歌もスポーツも全く同じ。
トレーニングした筋肉を、身体を、
自分でコントロールして、使いこなさなければ意味がないのです。
今日も沢山のヒントやアドバイスを頂きました(^^)
その中でも、
「自分の身体を振り絞って、最大限に声を出し切る事で、初めて自分の(今の)限界を知る。
限界を知るからこそ、本番で計画的(ペース配分)に歌を歌え、ステージを成功させる事が出来る」
歌のステージって、マラソンみたいですね、と(^_^)
練習で、中途半端にしか取り組んでなかったら、
自分が果たして何処までのテンションで試合を戦えばいいのかわからないはず。
だから、自分が見えなくなったり、焦ったり、「普段通り」「練習通り」なんて
出来るわけがない…
ピーキング、という言葉があります。
文字通り、試合にベストコンディションで臨む為に、時間をかけて計画していく方法です。
意外とスポーツの現場よりも、音楽の世界の方がシビアに追求されている気がしました。
直接敵と、目に見える形で
戦うモノではないからでしょうか…。
誤魔化しが一切効かない、厳しさを感じました。
話を聞けば聞くほど、
限りなくスポーツの世界、そして勝負の世界と深く繋がり、
身の引き締まる思いです。
自分なりに、先週ご指導頂いた「腹式呼吸」を一週間毎日試してきました。
通常は、歌を本格的に歌うなかで、
さらにステップアップしたい方が、問題を解決すべくこういう所を訪れるのだとおもいますが、
私は全くのド素人…
声の変化はわかりませんが、
身体の変化は感じました。
ストレッチするより、腹部を呼吸と共にしっかり使うほうが、筋肉が緩む…
ムダな力が抜けて、
上半身の軽さと、下半身の安定感を感じました。
当然、ベーシックな身体作り、土台作りの一つの方法でしかないので、
ここからどうパフォーマンスに繋げるか、技術的な練習をする必要があるのは、
歌もスポーツも全く同じ。
トレーニングした筋肉を、身体を、
自分でコントロールして、使いこなさなければ意味がないのです。
今日も沢山のヒントやアドバイスを頂きました(^^)
その中でも、
「自分の身体を振り絞って、最大限に声を出し切る事で、初めて自分の(今の)限界を知る。
限界を知るからこそ、本番で計画的(ペース配分)に歌を歌え、ステージを成功させる事が出来る」
歌のステージって、マラソンみたいですね、と(^_^)
練習で、中途半端にしか取り組んでなかったら、
自分が果たして何処までのテンションで試合を戦えばいいのかわからないはず。
だから、自分が見えなくなったり、焦ったり、「普段通り」「練習通り」なんて
出来るわけがない…
ピーキング、という言葉があります。
文字通り、試合にベストコンディションで臨む為に、時間をかけて計画していく方法です。
意外とスポーツの現場よりも、音楽の世界の方がシビアに追求されている気がしました。
直接敵と、目に見える形で
戦うモノではないからでしょうか…。
誤魔化しが一切効かない、厳しさを感じました。
話を聞けば聞くほど、
限りなくスポーツの世界、そして勝負の世界と深く繋がり、
身の引き締まる思いです。
2012年05月16日
歌えるトレーナー?
いい巡り合いがありました~。
トレーニング指導の中で、度々活用する「腹式呼吸」を
プロのボイストレーナーの方に直接ご指導を受けました!
以前から、気になりつつも・・・
ようやく勇気を出して、ご連絡を取らせていただいたところ
畑違いのこんな私を快く引き受けてくださりました。
とはいえ、「歌うのではなく、腹式呼吸だけ」なんて
無謀な要求をするものですから、困られたことでしょう。。
私も、どこまで自分の仕事とつながりがあるのか
全くわからない状態でしたが、
”絶対、ヒントはあるはず” という完全な「思い込み」(笑)。
(こういう「思い込み」は、大切。)
実際、ドキドキしながらご指導いただいたのですが・・・
まあ!目が覚めるような新境地!!
自分の思っていた”腹式呼吸”なんて、予想どおり、甘い甘い。
お話を聞いていて、たくさんスポーツと深く繋がる部分があり、
本当に興味深い時間でした。
身体の筋肉をめいいっぱい使う、
「身体が楽器」という声楽の世界。
”身体の中から出すエネルギーに声をのせて、遠くに飛ばす”
だから、自分の身体の中にしっかりと安定したものを持っていなければならない。
本当に心に残るお言葉でした。
自分の身体の中に、しっかりと安定したものがあるからこそ、
ジャンプが出来たり、足が前に出たり、ボールを遠くに飛ばせたり、
相手を押したり、手具にエネルギーを伝えられたり、
無駄な力を抜いたりすることができる。
”歌”と”スポーツ”、方向性は全く違うようですが、感覚はかなり近いのです。
また、
私が指導者ということで、
先生の指導上での経験やアドバイスも丁寧にしてくださいました。
さて、肝心な実技は?というと・・・
身体の筋肉を意識して動かすのは、私の得意分野なので~
たぶん、お褒めの言葉を頂きました~わーい。
その代り、かなりの集中力と頭と身体を使って、ぐったりです。
若干、筋肉痛も(苦)。
3回の特別レッスン。せっかくなので、
パフォーマンスとして「発声」につなげるところまで
頑張ってみようと思っています!
声がデカくなった方が、指導の時にもきっと役立つはず。
島でも、こんな素晴らしい指導者がいらっしゃる。
きっと、ここ(奄美)に来なければ、私は一生知らない世界だったかもしれません。
きちんと学んで、今度は私の出来る分野に置き換えて、
島の子供達へ還していきたいです。
トレーニング指導の中で、度々活用する「腹式呼吸」を
プロのボイストレーナーの方に直接ご指導を受けました!
以前から、気になりつつも・・・
ようやく勇気を出して、ご連絡を取らせていただいたところ
畑違いのこんな私を快く引き受けてくださりました。
とはいえ、「歌うのではなく、腹式呼吸だけ」なんて
無謀な要求をするものですから、困られたことでしょう。。
私も、どこまで自分の仕事とつながりがあるのか
全くわからない状態でしたが、
”絶対、ヒントはあるはず” という完全な「思い込み」(笑)。
(こういう「思い込み」は、大切。)
実際、ドキドキしながらご指導いただいたのですが・・・
まあ!目が覚めるような新境地!!
自分の思っていた”腹式呼吸”なんて、予想どおり、甘い甘い。
お話を聞いていて、たくさんスポーツと深く繋がる部分があり、
本当に興味深い時間でした。
身体の筋肉をめいいっぱい使う、
「身体が楽器」という声楽の世界。
”身体の中から出すエネルギーに声をのせて、遠くに飛ばす”
だから、自分の身体の中にしっかりと安定したものを持っていなければならない。
本当に心に残るお言葉でした。
自分の身体の中に、しっかりと安定したものがあるからこそ、
ジャンプが出来たり、足が前に出たり、ボールを遠くに飛ばせたり、
相手を押したり、手具にエネルギーを伝えられたり、
無駄な力を抜いたりすることができる。
”歌”と”スポーツ”、方向性は全く違うようですが、感覚はかなり近いのです。
また、
私が指導者ということで、
先生の指導上での経験やアドバイスも丁寧にしてくださいました。
さて、肝心な実技は?というと・・・
身体の筋肉を意識して動かすのは、私の得意分野なので~
たぶん、お褒めの言葉を頂きました~わーい。
その代り、かなりの集中力と頭と身体を使って、ぐったりです。
若干、筋肉痛も(苦)。
3回の特別レッスン。せっかくなので、
パフォーマンスとして「発声」につなげるところまで
頑張ってみようと思っています!
声がデカくなった方が、指導の時にもきっと役立つはず。
島でも、こんな素晴らしい指導者がいらっしゃる。
きっと、ここ(奄美)に来なければ、私は一生知らない世界だったかもしれません。
きちんと学んで、今度は私の出来る分野に置き換えて、
島の子供達へ還していきたいです。
2012年05月14日
熱と水分補給
前回の「熱中症について」の続編です。
参考文献は NSCAジャーナル2012 vol19 #4
「ジュニアおよび大学テニス選手のための暑熱と水分補給に関する考察」より
<健康の観点から>
・暑熱環境はパフォーマンスの低下だけでなく、
運動関連の筋痙攣、すなわち労作性熱痙攣とも関係があります。
・熱痙攣の病因は以下の3つの要因
「運動誘発性の筋疲労」「体内水分の損失」「発汗によるナトリウムの多大な損失」
その予防について・・・
・脱水症状や全身の塩分バランスの崩れを伴う熱中症(熱痙攣・熱疲労)を
予防するためには、
飲食物に塩をかけたり、加工食品を食べたりして、食事にナトリウムを追加すればよい。
・・・と書かれています。
結構汗かきな人は、結構な量の塩分が汗とともに失われるようです。
続けて、こう書かれてあります。
・競技会やトレーニングの少なくとも1時間前にスポーツドリンク(約1ℓ)とともに
小さじ半分(1g)の食卓塩を摂れば、水分・糖質・塩分を簡単に付加することができる。
・特に熱痙攣や脱水症状を起こしやすい選手には、水分補給計画の一環として
エクササイズ中にナトリウムを含む液体・・・
スポーツドリンク(約1ℓ)に塩小さじ1/4(0.5g)を加えるなど・・・を摂取させるとよい。
具体的な塩分と水分補給の方法の一つが挙げられています。
島では、やはり”暑い”だけに、水分や塩分補給について関心が高い、と感じます。
現場に常時おいてあるものランキング
「塩」 「梅干し」 「黒糖」
さらに、文献にこう書かれてあります。
「たっぷりの水とともに摂取すること。」
意外と、「塩なめておけば大丈夫」的な考えで・・・
水分が十分に摂れていないってことはありませんか?
確実な熱中症の予防は、「身体の中にこもった熱を冷ますこと」。
(これは、発熱時の水分補給でも、同様だと思います。)
続けて・・・
・大切なことは、塩分摂取増加のための方法は、競技会(試合)の前にすべて試して、
どの方法が選手にとって最も苦痛でないかを確かめること。
いくら正しい情報、良い方法でも、日ごろやっていないことを試合で取り入れることは
適切なコンディショニングとは言えません。
また、こんなことも書かれています。
・テニス選手の発汗率は0.5~2.6ℓ/H(1時間当たり0.5~2.6ℓ)。ところがテニス中に摂取される
水分量は1.0~1.6ℓ/H、と報告されている。この点を考慮すると、選手の発汗率が高い場合、
その選手が脱水状態に陥る理由は明白である。
・しかし、選手が最大限の努力をもって水分補給をしようとしても、足りない可能性がある。
なぜなら、胃の水分が吸収される速度は、最大約1.2ℓ/Hだからである。
よって、これを上回る割合で水分を摂取することは、胃に不快感をもたらしかねない。
がぶ飲みすると、お腹に溜る・・・のは納得ですね~。
要するに、「のどが渇いて、飲んでいる量」というのは、
実際には必要量に対して「足りていない」可能性も高いのです。
・たとえば、発汗率2.5ℓ/Hの選手が胃の不快感なしに、無理なく水分摂取を行うとすると、
約50%しか補給できない。つまり、試合中に最低80%の水分を補給するという目的は、
達成不可能と考えられる。
では、どうやってまかなうのか?という事になりますが・・・
・そこで、「試合前」 「試合中」 「試合間」 「試合後」に行われる水分補給を監視することが
重要になる。
実際、選手の発汗量を調べる方法は、
・尿の色
・練習前後の体重の計測
などがあります。
そこまで厳密に考えずとも、やはりこういう情報と知識を知っておくかどうかで、
熱中症の発生率を抑えることもできるのではないかと考えます。
長くなりますが、まだまだ続きがあります・・・
また次回UPします。
「選手に与える飲料」や「暑熱馴化」に関する情報です。
参考文献は NSCAジャーナル2012 vol19 #4
「ジュニアおよび大学テニス選手のための暑熱と水分補給に関する考察」より
<健康の観点から>
・暑熱環境はパフォーマンスの低下だけでなく、
運動関連の筋痙攣、すなわち労作性熱痙攣とも関係があります。
・熱痙攣の病因は以下の3つの要因
「運動誘発性の筋疲労」「体内水分の損失」「発汗によるナトリウムの多大な損失」
その予防について・・・
・脱水症状や全身の塩分バランスの崩れを伴う熱中症(熱痙攣・熱疲労)を
予防するためには、
飲食物に塩をかけたり、加工食品を食べたりして、食事にナトリウムを追加すればよい。
・・・と書かれています。
結構汗かきな人は、結構な量の塩分が汗とともに失われるようです。
続けて、こう書かれてあります。
・競技会やトレーニングの少なくとも1時間前にスポーツドリンク(約1ℓ)とともに
小さじ半分(1g)の食卓塩を摂れば、水分・糖質・塩分を簡単に付加することができる。
・特に熱痙攣や脱水症状を起こしやすい選手には、水分補給計画の一環として
エクササイズ中にナトリウムを含む液体・・・
スポーツドリンク(約1ℓ)に塩小さじ1/4(0.5g)を加えるなど・・・を摂取させるとよい。
具体的な塩分と水分補給の方法の一つが挙げられています。
島では、やはり”暑い”だけに、水分や塩分補給について関心が高い、と感じます。
現場に常時おいてあるものランキング
「塩」 「梅干し」 「黒糖」
さらに、文献にこう書かれてあります。
「たっぷりの水とともに摂取すること。」
意外と、「塩なめておけば大丈夫」的な考えで・・・
水分が十分に摂れていないってことはありませんか?
確実な熱中症の予防は、「身体の中にこもった熱を冷ますこと」。
(これは、発熱時の水分補給でも、同様だと思います。)
続けて・・・
・大切なことは、塩分摂取増加のための方法は、競技会(試合)の前にすべて試して、
どの方法が選手にとって最も苦痛でないかを確かめること。
いくら正しい情報、良い方法でも、日ごろやっていないことを試合で取り入れることは
適切なコンディショニングとは言えません。
また、こんなことも書かれています。
・テニス選手の発汗率は0.5~2.6ℓ/H(1時間当たり0.5~2.6ℓ)。ところがテニス中に摂取される
水分量は1.0~1.6ℓ/H、と報告されている。この点を考慮すると、選手の発汗率が高い場合、
その選手が脱水状態に陥る理由は明白である。
・しかし、選手が最大限の努力をもって水分補給をしようとしても、足りない可能性がある。
なぜなら、胃の水分が吸収される速度は、最大約1.2ℓ/Hだからである。
よって、これを上回る割合で水分を摂取することは、胃に不快感をもたらしかねない。
がぶ飲みすると、お腹に溜る・・・のは納得ですね~。
要するに、「のどが渇いて、飲んでいる量」というのは、
実際には必要量に対して「足りていない」可能性も高いのです。
・たとえば、発汗率2.5ℓ/Hの選手が胃の不快感なしに、無理なく水分摂取を行うとすると、
約50%しか補給できない。つまり、試合中に最低80%の水分を補給するという目的は、
達成不可能と考えられる。
では、どうやってまかなうのか?という事になりますが・・・
・そこで、「試合前」 「試合中」 「試合間」 「試合後」に行われる水分補給を監視することが
重要になる。
実際、選手の発汗量を調べる方法は、
・尿の色
・練習前後の体重の計測
などがあります。
そこまで厳密に考えずとも、やはりこういう情報と知識を知っておくかどうかで、
熱中症の発生率を抑えることもできるのではないかと考えます。
長くなりますが、まだまだ続きがあります・・・
また次回UPします。
「選手に与える飲料」や「暑熱馴化」に関する情報です。
2012年05月05日
優勝!
昨日のリベンジは、果たせたようです。

結果を聞いて、正直、ホッとしました(^_^;)
選手が今まで練習を頑張った結果ではありますが、
試合に際して…
保護者の方々や関係者の皆さんから
見えない所で多大なご協力頂いてます。
保護者の中には、内地での試合へは行けない方もいらっしゃると思うので、
いいゲーム、いい結果を目の前で届けられて良かったな~。

結果を聞いて、正直、ホッとしました(^_^;)
選手が今まで練習を頑張った結果ではありますが、
試合に際して…
保護者の方々や関係者の皆さんから
見えない所で多大なご協力頂いてます。
保護者の中には、内地での試合へは行けない方もいらっしゃると思うので、
いいゲーム、いい結果を目の前で届けられて良かったな~。
2012年05月02日
熱中症について
今月のNSCAジャーナル。

最新の情報を翻訳してあります。
その中より
「ジュニアおよび大学テニス選手のための暑熱と水分補給に関する考察」(Evan C.Johnson,Lawrence E.Armstrong)
<熱中症の原因>
・暑熱環境により、体表ににおいて血液から熱を放散させる能力が低下する。
・運動すると栄養素が代謝される時、放出されるエネルギーのほとんどが体熱となる。
したがって、運動強度が高いほど、多くの熱が産生されることになる。
つまり・・・
身体を動かす、ということはエネルギーが必要。
エネルギーが作られる時には必ず”熱”が発生するわけです。
熱は運動する筋から血液へ。
血液を通じて熱は体表(皮膚)へ。
”涼しい”と感じる環境では、体表において血液が冷やされ、
また筋へ戻っていくので
熱が身体の中へ「こもらない」で済むのですが・・・
高温で、さらに”多湿”の環境では、体表面(皮下)において血液から
熱を放散させる能力が低下する。
これによって引き起こされる問題・・・
つまり「熱中症」はこうした体温調節の機能がうまくいかず、
熱が体内に貯蔵されてしまう。
いわゆる「深部体温」の上昇が選手のパフォーマンスと安全にとって
重要な問題である。
と、難しい言葉で書かれています。
この体温調節の一つに
「発汗」という機能が働きます。
深部体温が低下するまで、発汗は続きます。
余談ですが・・・
運動していなくても、赤ちゃんや子供はよく「汗」をかいています。
高齢者や乳幼児は
成人に比べてこの体温調節機能が不十分なところあるので、
やはり「深部体温」が上がっている可能性がある、ということも
注意しておいてください。
・テニスは高い運動負荷と、高温多湿の環境を伴う競技である。
アスリートの深部体温が十分に低下するまで、発汗は継続する。
この状況において、脱水状態に陥ることは、重大な問題である。
・脱水を起こして、体重が基準値からわずか2%低下しただけで、
持久系エクササイズにおいてはパフォーマンスが低下し、
また競技特異的スキルも低下する。
また、
・トレーニングや試合の状況によっては、脱水症状の程度が高くても
「しのげる」ことがある。しかし、要求が厳しい課題においては、
パフォーマンスのごくわずかな低下さえも、課題の失敗をもたらしかねない。
水分補給がうまくいかないままでの運動活動は、
集中力の低下も招く、ということですね。
水分補給についても、続きは後日UPします。

最新の情報を翻訳してあります。
その中より
「ジュニアおよび大学テニス選手のための暑熱と水分補給に関する考察」(Evan C.Johnson,Lawrence E.Armstrong)
<熱中症の原因>
・暑熱環境により、体表ににおいて血液から熱を放散させる能力が低下する。
・運動すると栄養素が代謝される時、放出されるエネルギーのほとんどが体熱となる。
したがって、運動強度が高いほど、多くの熱が産生されることになる。
つまり・・・
身体を動かす、ということはエネルギーが必要。
エネルギーが作られる時には必ず”熱”が発生するわけです。
熱は運動する筋から血液へ。
血液を通じて熱は体表(皮膚)へ。
”涼しい”と感じる環境では、体表において血液が冷やされ、
また筋へ戻っていくので
熱が身体の中へ「こもらない」で済むのですが・・・
高温で、さらに”多湿”の環境では、体表面(皮下)において血液から
熱を放散させる能力が低下する。
これによって引き起こされる問題・・・
つまり「熱中症」はこうした体温調節の機能がうまくいかず、
熱が体内に貯蔵されてしまう。
いわゆる「深部体温」の上昇が選手のパフォーマンスと安全にとって
重要な問題である。
と、難しい言葉で書かれています。
この体温調節の一つに
「発汗」という機能が働きます。
深部体温が低下するまで、発汗は続きます。
余談ですが・・・
運動していなくても、赤ちゃんや子供はよく「汗」をかいています。
高齢者や乳幼児は
成人に比べてこの体温調節機能が不十分なところあるので、
やはり「深部体温」が上がっている可能性がある、ということも
注意しておいてください。
・テニスは高い運動負荷と、高温多湿の環境を伴う競技である。
アスリートの深部体温が十分に低下するまで、発汗は継続する。
この状況において、脱水状態に陥ることは、重大な問題である。
・脱水を起こして、体重が基準値からわずか2%低下しただけで、
持久系エクササイズにおいてはパフォーマンスが低下し、
また競技特異的スキルも低下する。
また、
・トレーニングや試合の状況によっては、脱水症状の程度が高くても
「しのげる」ことがある。しかし、要求が厳しい課題においては、
パフォーマンスのごくわずかな低下さえも、課題の失敗をもたらしかねない。
水分補給がうまくいかないままでの運動活動は、
集中力の低下も招く、ということですね。
水分補給についても、続きは後日UPします。
2012年04月27日
ペップトーク
「ペップトーク」という言葉をご存じでしょうか?
元気・やる気・勇気を引き出す短いメッセージの事、だそうです。
この言葉を広めてらっしゃるのは「岩崎由純」さんという
アスレティックトレーナーの方です。
10年前、岩崎さんのホームページへ、選手のケガについて相談したのがきっかけで、
直接お会いしたくて、訪ねていったことがあります。
現在も活動拠点でいらっしゃるNECの女子バレー部。
セッターの竹下さんやセンタープレーヤーの杉山さんも当時所属されていて、
選手と一緒にトレーニングに参加させていただいたり、
テーピングを教えていただいたりしました。
その5年後、NECへ再び行くきっかけがあり、
たまたまいらっしゃった岩崎さんと再会。
ほんの少しお時間をいただき、お話を聞くことができました。
緊張して、ほとんど覚えていないのですが・・・
記憶に残る一言があります。
「あなたなら、きっと夢が叶いますよ。」
この言葉のおかげで、どれだけ励まされたか・・・
最近、岩崎さんの本を買いました。
”子どものココロを育てるコミュニケーション術”
(株)東邦出版

「ペップトーク」についても解説してあります。
トレーナーは、どうしても会話する相手のココロがマイナスな状況で
対応することが多い仕事です。
私心なく、話を聞く(傾聴)をもっとも心がけていますが、
仕事を始めた当初は、クライアントのマイナスのココロをすべて吸収してしまい、
励ますどころか、自分がマイナスに・・・(涙)。
私は違った方向からコミュニケーションスキルは学んできましたが、
この本はとてもわかり易く解説してあります。
自らの言動を振り返ったり、
改めて「ペップトーク」の大切さを再確認。
「岩崎さんのような人間であり、トレーナーになりたい。」
いくつになっても、夢は追っていきたいものです。
元気・やる気・勇気を引き出す短いメッセージの事、だそうです。
この言葉を広めてらっしゃるのは「岩崎由純」さんという
アスレティックトレーナーの方です。
10年前、岩崎さんのホームページへ、選手のケガについて相談したのがきっかけで、
直接お会いしたくて、訪ねていったことがあります。
現在も活動拠点でいらっしゃるNECの女子バレー部。
セッターの竹下さんやセンタープレーヤーの杉山さんも当時所属されていて、
選手と一緒にトレーニングに参加させていただいたり、
テーピングを教えていただいたりしました。
その5年後、NECへ再び行くきっかけがあり、
たまたまいらっしゃった岩崎さんと再会。
ほんの少しお時間をいただき、お話を聞くことができました。
緊張して、ほとんど覚えていないのですが・・・
記憶に残る一言があります。
「あなたなら、きっと夢が叶いますよ。」
この言葉のおかげで、どれだけ励まされたか・・・
最近、岩崎さんの本を買いました。
”子どものココロを育てるコミュニケーション術”
(株)東邦出版

「ペップトーク」についても解説してあります。
トレーナーは、どうしても会話する相手のココロがマイナスな状況で
対応することが多い仕事です。
私心なく、話を聞く(傾聴)をもっとも心がけていますが、
仕事を始めた当初は、クライアントのマイナスのココロをすべて吸収してしまい、
励ますどころか、自分がマイナスに・・・(涙)。
私は違った方向からコミュニケーションスキルは学んできましたが、
この本はとてもわかり易く解説してあります。
自らの言動を振り返ったり、
改めて「ペップトーク」の大切さを再確認。
「岩崎さんのような人間であり、トレーナーになりたい。」
いくつになっても、夢は追っていきたいものです。
2012年04月24日
ふくらはぎのストレッチング
ストレッチボードって、ご存知ですか?
見たことある人も、多いかもしれません。

使い方は簡単。乗るだけでふくらはぎやアキレス腱のストレッチングが出来る優れもの(^^)

一年以上、寝かせてました…が、
うちの長女には、簡単で丁度いいな、と思って、復活。
小学生のクセに、ふくらはぎも意外と硬くて、びっくり。
私に似て身体が硬いので、可哀想。
振り返ると、本当にケガの多い、小学生だった私。
昔は、今ほど、ストレッチやら水分補給やら…しなかったし情報もなかった。
ただ、やっぱり
痛いのは、
辛かった記憶。
幸か不幸か分からないけど、母親がこんな仕事しているが為に…
実験台。

小学生に限らず、今日来てくれた選手達のふくらはぎも、かなり硬くなっていました。
負担がかかりやすい割には、ツラない限り、意外と忘れられている部位ですね。
足の裏まで重たくなります。
ストレッチボードがなくても、
階段の端につま先で立って、かかとを、段差利用して下ろしていくと、出来ます
。
ポイントは、膝を伸ばして、と、膝を軽く曲げてと、2パターンやると、
同じふくらはぎでも、違う筋肉をケア出来ます。
障害予防に、試してみて下さいね!
見たことある人も、多いかもしれません。

使い方は簡単。乗るだけでふくらはぎやアキレス腱のストレッチングが出来る優れもの(^^)

一年以上、寝かせてました…が、
うちの長女には、簡単で丁度いいな、と思って、復活。
小学生のクセに、ふくらはぎも意外と硬くて、びっくり。
私に似て身体が硬いので、可哀想。
振り返ると、本当にケガの多い、小学生だった私。
昔は、今ほど、ストレッチやら水分補給やら…しなかったし情報もなかった。
ただ、やっぱり
痛いのは、
辛かった記憶。
幸か不幸か分からないけど、母親がこんな仕事しているが為に…
実験台。

小学生に限らず、今日来てくれた選手達のふくらはぎも、かなり硬くなっていました。
負担がかかりやすい割には、ツラない限り、意外と忘れられている部位ですね。
足の裏まで重たくなります。
ストレッチボードがなくても、
階段の端につま先で立って、かかとを、段差利用して下ろしていくと、出来ます
。
ポイントは、膝を伸ばして、と、膝を軽く曲げてと、2パターンやると、
同じふくらはぎでも、違う筋肉をケア出来ます。
障害予防に、試してみて下さいね!
2012年04月21日
テーピング
トレーナーの代名詞、といえば「テーピング」
現場では、最近テーピング固定をする機会がめっきり減りました。
特に、ホワイトテープ。

突き指とか、そんな時くらいしか使わない。
テープの種類も増えて、用途に応じて使い方も様々ですが、
やはり固定とコストを考えると、
ホワイトテープは王道です。
トレーナーの試験には、必ずホワイトテープの固定法は出ます。ATの第一人者、鹿倉二郎先生のテーピングは、何度かご指導頂きましたが、神業です。
この前、「足関節のテーピングの1人巻き」をみて、出来るのかな〜と
私も、巻いてみました(^_^;)

意外と、人に巻くより簡単。
ポイントは、いかに足首を90度で固定したまま巻けるか、という点。
我ながら、きれいに巻けたと…
ちょっと、安心(^^)
現場では、最近テーピング固定をする機会がめっきり減りました。
特に、ホワイトテープ。

突き指とか、そんな時くらいしか使わない。
テープの種類も増えて、用途に応じて使い方も様々ですが、
やはり固定とコストを考えると、
ホワイトテープは王道です。
トレーナーの試験には、必ずホワイトテープの固定法は出ます。ATの第一人者、鹿倉二郎先生のテーピングは、何度かご指導頂きましたが、神業です。
この前、「足関節のテーピングの1人巻き」をみて、出来るのかな〜と
私も、巻いてみました(^_^;)

意外と、人に巻くより簡単。
ポイントは、いかに足首を90度で固定したまま巻けるか、という点。
我ながら、きれいに巻けたと…
ちょっと、安心(^^)
2012年04月15日
コーディネーショントレーニング教室
ASAコミュニティクラブの企画、コーディネーショントレーニング教室に次女が参加しました。


体育の授業参観している気分です(^^)
とても楽しそうに、やっていました。
コーディネーション(調整力)機能のピークは小学校です。
次々に変わった動きを提供して下さってましたが、
さらに「もっと!」
子供達のエネルギーは凄い!収集がつかない事も(^_^;)
習い事のように、何か「教えられて」一生懸命やるのも大事かもしれないけど、
これはまた、ちょっと違った…
子供達の自然な姿が見れた気がしました。
普段、引っ込み思案だと思っていた次女の、ちょっと型破りな姿に…驚きと、喜び。
人数が意外に少なくてもったいない…
次回も、楽しみです(^^)


体育の授業参観している気分です(^^)
とても楽しそうに、やっていました。
コーディネーション(調整力)機能のピークは小学校です。
次々に変わった動きを提供して下さってましたが、
さらに「もっと!」
子供達のエネルギーは凄い!収集がつかない事も(^_^;)
習い事のように、何か「教えられて」一生懸命やるのも大事かもしれないけど、
これはまた、ちょっと違った…
子供達の自然な姿が見れた気がしました。
普段、引っ込み思案だと思っていた次女の、ちょっと型破りな姿に…驚きと、喜び。
人数が意外に少なくてもったいない…
次回も、楽しみです(^^)
2012年04月08日
子供のスポーツ
今回は「子供のスポーツ」について少し書きたいと思います。
うちの娘達が最初に始めた習い事は
バレーボール…ではなく
「新体操」です。
現在も、次女は続けています。
リズム感や、手具と自身の細かいコントロール、バランス能力、柔軟性など、あらゆるスポーツの基礎を持つスポーツの一つだと思います。
こういった神経系能力の習得は子供、特にゴールデンエイジといわれる6~10歳にピークを迎えると言われています。
体育バカはそんな余計な知識を知ってただけに、
わが子に試している・・・というのもありますが…
何より、楽しくレッスンに取り組んでいるの事が、
子供にとっては一番の良い刺激。
今年度最初のレッスンはバレエレッスンやスキップ、ステップなどの基礎を中心に指導して下さっています。
全くの素人ですが、
どこの筋肉を使うのか、仕事柄気になるところ。
見真似で一緒にやってみるのですが、
難しい…
大人は完全に日頃使わない筋肉を使わざるを得ないので(涙)
思うようにはなかなか…身体が(ーー;)
本当に全身運動です。
子供は、凄い。
出来ない事も、ちょっとイメージ掴むと自分で少しづつでも「修正」が、できる。
要するに、少々ほおっておいても、子供は興味と環境さえあれば自ら学んでいく。
これが、この時期の子供の能力のすごさです。
トレーナーの目で子供をみると、そう思うのですが、
親の目で子供をみると、やっぱり細かいところまで言いたく
なっちゃいます(笑)。
今のトレーナー活動はバレーボール競技を中心に見ていますが、
トレーニング指導で一番心がけることは
「競技以外で使う筋肉をしっかりと活性化すること」
どうしても1つの競技ばかりやっていると、
技術が高くなればなるほど、
その競技で必要とされる筋肉が限定されがちになるので、
結局「局所的に疲労」し、「徐々に痛み」につながります。
そういった視点からは、
子供の「早期の競技スポーツ化」、基本的に私は反対です。
ま、理屈は理屈として~
こんなこと言ってばかりでは、なんもできなくなっちゃうので~
子供の「可能性」と「運」を信じて、
親としてできることを頑張りたい。
またトレーナーとして選手を預かる以上は、
親心を持って、頑張らなきゃ、ですね。
うちの娘達が最初に始めた習い事は
バレーボール…ではなく
「新体操」です。
現在も、次女は続けています。
リズム感や、手具と自身の細かいコントロール、バランス能力、柔軟性など、あらゆるスポーツの基礎を持つスポーツの一つだと思います。
こういった神経系能力の習得は子供、特にゴールデンエイジといわれる6~10歳にピークを迎えると言われています。
体育バカはそんな余計な知識を知ってただけに、
わが子に試している・・・というのもありますが…
何より、楽しくレッスンに取り組んでいるの事が、
子供にとっては一番の良い刺激。
今年度最初のレッスンはバレエレッスンやスキップ、ステップなどの基礎を中心に指導して下さっています。
全くの素人ですが、
どこの筋肉を使うのか、仕事柄気になるところ。
見真似で一緒にやってみるのですが、
難しい…
大人は完全に日頃使わない筋肉を使わざるを得ないので(涙)
思うようにはなかなか…身体が(ーー;)
本当に全身運動です。
子供は、凄い。
出来ない事も、ちょっとイメージ掴むと自分で少しづつでも「修正」が、できる。
要するに、少々ほおっておいても、子供は興味と環境さえあれば自ら学んでいく。
これが、この時期の子供の能力のすごさです。
トレーナーの目で子供をみると、そう思うのですが、
親の目で子供をみると、やっぱり細かいところまで言いたく
なっちゃいます(笑)。
今のトレーナー活動はバレーボール競技を中心に見ていますが、
トレーニング指導で一番心がけることは
「競技以外で使う筋肉をしっかりと活性化すること」
どうしても1つの競技ばかりやっていると、
技術が高くなればなるほど、
その競技で必要とされる筋肉が限定されがちになるので、
結局「局所的に疲労」し、「徐々に痛み」につながります。
そういった視点からは、
子供の「早期の競技スポーツ化」、基本的に私は反対です。
ま、理屈は理屈として~
こんなこと言ってばかりでは、なんもできなくなっちゃうので~
子供の「可能性」と「運」を信じて、
親としてできることを頑張りたい。
またトレーナーとして選手を預かる以上は、
親心を持って、頑張らなきゃ、ですね。
2012年04月05日
出会い
今日は、ご近所のバドミントン選手が
「インソール(靴底)を作ってもらった」
というので、一緒に見学に行ってきました。
トレーナー仲間でも、やはり何人かソールを専門的に学んでいる方も知っているし、実際私も、様々なパッドを靴底に貼ったりして、選手の足の怪我の予防や改善に、と勉強したこともありました(…そういえば…)
奄美でも、こうやって、選手のサポートをしている方がいらっしゃる事、
そういう方と、出会えた事が本当に有難い。スーパーなバド選手に、感謝(^^)。
またお互いに、それぞれの特技をいかしながら、協力出来たら面白いなぁーと思います。
結構、トレーナーって、それぞれの考え方ややり方が様々なので、あまり仲間と情報を共有したがりません(ーー;)
でもねー、それも寂しいから…(笑)
狭い島でこそ、こうしてネットワークを広げながら、お互い切磋琢磨出来たらいいな、と思います。
こうしてブログで、公開しているのもそういう目的ですが…
「こういう人達も島には居るんだな〜」
と、興味持たれた方は、
まずは一言コメント、下さいね(^_^)
「インソール(靴底)を作ってもらった」
というので、一緒に見学に行ってきました。
トレーナー仲間でも、やはり何人かソールを専門的に学んでいる方も知っているし、実際私も、様々なパッドを靴底に貼ったりして、選手の足の怪我の予防や改善に、と勉強したこともありました(…そういえば…)
奄美でも、こうやって、選手のサポートをしている方がいらっしゃる事、
そういう方と、出会えた事が本当に有難い。スーパーなバド選手に、感謝(^^)。
またお互いに、それぞれの特技をいかしながら、協力出来たら面白いなぁーと思います。
結構、トレーナーって、それぞれの考え方ややり方が様々なので、あまり仲間と情報を共有したがりません(ーー;)
でもねー、それも寂しいから…(笑)
狭い島でこそ、こうしてネットワークを広げながら、お互い切磋琢磨出来たらいいな、と思います。
こうしてブログで、公開しているのもそういう目的ですが…
「こういう人達も島には居るんだな〜」
と、興味持たれた方は、
まずは一言コメント、下さいね(^_^)
2012年03月17日
母校にて
今年も三ヶ月が過ぎようとしています。
一年、あっと言う間だったなぁ…
年初め、チームは私の母校である鹿屋体育大学の高校生合宿に参加しました。
毎年、ブラブラ~と遊びに行っていた合宿へ、島からも行けるなんて!
高校生から見ると、
大学生、怖いだろうなあ~(笑)
案の上、容赦なくしごかれ、怒られてた高校生達…
大学生も、各チームの監督さん(卒業生)にゲーム監督、練習全てを一任されて、必死に指導してくれました。
その時の、トレーニング指導を。


ま、似たような事はしているわけです。
大学生のトレーニング風景。

ま、似たような事は今も昔も変わらず…
目標と、毎年変わるテーマ

常に、目標を目にする事は大事です。
V2目指して頑張って!
おまけ。こんな所もあります。


また、新年をここで迎えられるといいな…と思うのは私だけかな(^_^;)
一年、あっと言う間だったなぁ…
年初め、チームは私の母校である鹿屋体育大学の高校生合宿に参加しました。
毎年、ブラブラ~と遊びに行っていた合宿へ、島からも行けるなんて!
高校生から見ると、
大学生、怖いだろうなあ~(笑)
案の上、容赦なくしごかれ、怒られてた高校生達…
大学生も、各チームの監督さん(卒業生)にゲーム監督、練習全てを一任されて、必死に指導してくれました。
その時の、トレーニング指導を。


ま、似たような事はしているわけです。
大学生のトレーニング風景。

ま、似たような事は今も昔も変わらず…
目標と、毎年変わるテーマ

常に、目標を目にする事は大事です。
V2目指して頑張って!
おまけ。こんな所もあります。


また、新年をここで迎えられるといいな…と思うのは私だけかな(^_^;)
2012年02月21日
「深イイ」言葉
今日、納得した「深イイ」言葉。
「並外れた結果を出すのに、並外れた努力はいらない。
ただ、日々の、普通の物事を、完璧にすればいいだけだ」
ウォーレン・バフェット
・・・だよね~。
そうだ、そうだ。
毎日、コツコツの努力が大事。
頑張ろう。
「並外れた結果を出すのに、並外れた努力はいらない。
ただ、日々の、普通の物事を、完璧にすればいいだけだ」
ウォーレン・バフェット
・・・だよね~。
そうだ、そうだ。
毎日、コツコツの努力が大事。
頑張ろう。
2012年02月20日
カラダの記憶
久々に体調が思わしくない日が続いていました・・・
「健康」のありがたさを感じます。
昨日は、家庭婦人の大会で、
まあ、なんとか試合に出れて良かった・・・
そのかわり、今日は声がハスキーボイス(涙)。
私が所属しているチームも、最近「ウォームアップ」を兼ねて
トレーニング?してくれています。
たぶん、プレーするよりキツイです(笑)
一緒にしながら、皆さんがいつも言ってくれることは、
同じフォームや、今までやったことがあるような動きでも、
ちょっとした動作のアドバイスで
「負荷のかかる場所が全く違うこと」に気づく、こと。
そして・・・残念なことに「自分でそのあと同じようにやってみても、うまくできない」ということ。
動きのクセ、今までの思い込み、も含めて、
「変わる」ということは、非常に時間と頭とエネルギーを使います。
プレーなんて、なおさら・・・でしょうね。。
でも、必ず努力すれば「変わる」と思っています!
人間のこうした、動きや感覚・・・なにかが「出来る」ようになる能力が著しく発達する時期が
「ゴールデンエイジ」と呼ばれる、8歳から12歳前後になります。
ここでピークを迎え、この時期が過ぎると、
何か新しい動作を身につけたりするには時間がとてもかかってしまうので、
この時期にさまざまな運動体験をして身体に刺激を与えておくことで、
一生、どこかで、役に立つことになる、と言われています。
これは「スキャモンの発育曲線」という発育発達の基礎となる考え方ですが、
先週の、指導者講習会の中でも取り上げられていたようです。
指導者のみならず、こういう知識は、親でも知っていて損はないなあ・・・と思っていたら、
昨年、以前娘がいた幼稚園でも保護者対象に
「あそび」の実技とともに講義を依頼された事がありました。
うちの長女も、ちょうどそのゴールデンエイジ。
奄美という、自然あふれる環境の中で、いろんな体験をさせたいです。
もっと、木登りや山登りが出来ると思ってたんですけど・・・(笑)
「島」も現代の流れに沿って変わりつつ、あるようですね・・・。
大人でも「昔はできてたのにいまは・・・」って動き、
体力的なものは落ちていても、身体は絶対に記憶として覚えている。
私の動作のアドバイスが、少しでも身体が昔の感覚を思い出す
きっかけになるといいなあ・・・と思います。
子供たちは、「今」が本当に大切な時期だと、痛感します。
私も何か、子供達の為にも出来ることはないかな?
「健康」のありがたさを感じます。
昨日は、家庭婦人の大会で、
まあ、なんとか試合に出れて良かった・・・
そのかわり、今日は声がハスキーボイス(涙)。
私が所属しているチームも、最近「ウォームアップ」を兼ねて
トレーニング?してくれています。
たぶん、プレーするよりキツイです(笑)
一緒にしながら、皆さんがいつも言ってくれることは、
同じフォームや、今までやったことがあるような動きでも、
ちょっとした動作のアドバイスで
「負荷のかかる場所が全く違うこと」に気づく、こと。
そして・・・残念なことに「自分でそのあと同じようにやってみても、うまくできない」ということ。
動きのクセ、今までの思い込み、も含めて、
「変わる」ということは、非常に時間と頭とエネルギーを使います。
プレーなんて、なおさら・・・でしょうね。。
でも、必ず努力すれば「変わる」と思っています!
人間のこうした、動きや感覚・・・なにかが「出来る」ようになる能力が著しく発達する時期が
「ゴールデンエイジ」と呼ばれる、8歳から12歳前後になります。
ここでピークを迎え、この時期が過ぎると、
何か新しい動作を身につけたりするには時間がとてもかかってしまうので、
この時期にさまざまな運動体験をして身体に刺激を与えておくことで、
一生、どこかで、役に立つことになる、と言われています。
これは「スキャモンの発育曲線」という発育発達の基礎となる考え方ですが、
先週の、指導者講習会の中でも取り上げられていたようです。
指導者のみならず、こういう知識は、親でも知っていて損はないなあ・・・と思っていたら、
昨年、以前娘がいた幼稚園でも保護者対象に
「あそび」の実技とともに講義を依頼された事がありました。
うちの長女も、ちょうどそのゴールデンエイジ。
奄美という、自然あふれる環境の中で、いろんな体験をさせたいです。
もっと、木登りや山登りが出来ると思ってたんですけど・・・(笑)
「島」も現代の流れに沿って変わりつつ、あるようですね・・・。
大人でも「昔はできてたのにいまは・・・」って動き、
体力的なものは落ちていても、身体は絶対に記憶として覚えている。
私の動作のアドバイスが、少しでも身体が昔の感覚を思い出す
きっかけになるといいなあ・・・と思います。
子供たちは、「今」が本当に大切な時期だと、痛感します。
私も何か、子供達の為にも出来ることはないかな?
2012年02月15日
恩師、奄美に。
昨日、大学時代の恩師が奄美に来られました。
昨夜行われた小・中・高校バレーボール指導者対象の講習会の講師として招かれた為です。
2010年度全日本インカレ、日本一のチームの監督です。
スゴい人なんですが、
スゴく見えないのが…いいところ(笑)
講義は聞けませんでしたが、
私にとっては、
「奄美に先生がいる」
ことが、不思議で不思議で。
大学時代、「日本一を目指す」ということがどれだけ大変な事か、私は分からず、迷いだらけの日々を送っていました。
そんな中「トレーナー」というモノに出会い、
この仕事の理解と、私にチーム内での役割を与えて下さったことが、今の私の原点です。
卒業してからも、事あるごとに選抜チームへのスタッフ帯同に声をかけて頂いて、
様々な経験をさせて頂きました。
今日は午前中、観光案内を(^^)
主人も一緒に(同大学卒)、いい大人三人で…。



モノの見る視点が、面白いです。
指導には大切なことですね。
昔と変わらず、助けられ、励まされ、
今となってわかるような、
先生の思いだったり…
いや、分からないな(笑)
でも、純粋に「頑張ろう」と勇気づけられた2日間でした。
昨夜行われた小・中・高校バレーボール指導者対象の講習会の講師として招かれた為です。
2010年度全日本インカレ、日本一のチームの監督です。
スゴい人なんですが、
スゴく見えないのが…いいところ(笑)
講義は聞けませんでしたが、
私にとっては、
「奄美に先生がいる」
ことが、不思議で不思議で。
大学時代、「日本一を目指す」ということがどれだけ大変な事か、私は分からず、迷いだらけの日々を送っていました。
そんな中「トレーナー」というモノに出会い、
この仕事の理解と、私にチーム内での役割を与えて下さったことが、今の私の原点です。
卒業してからも、事あるごとに選抜チームへのスタッフ帯同に声をかけて頂いて、
様々な経験をさせて頂きました。
今日は午前中、観光案内を(^^)
主人も一緒に(同大学卒)、いい大人三人で…。



モノの見る視点が、面白いです。
指導には大切なことですね。
昔と変わらず、助けられ、励まされ、
今となってわかるような、
先生の思いだったり…
いや、分からないな(笑)
でも、純粋に「頑張ろう」と勇気づけられた2日間でした。