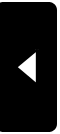2015年10月19日
中学生の合同練習会にて・・・
昨日は、中学女子バレーボール部の合同練習会の合間に
「ケガの処置」に関する講義をちょこっと(20分間)させてもらいました。

話を聞いてもらう間に、
実際に 「RICE処置」 と 「アイスバケツ」 で足関節捻挫に対する初期の処置を
中学生に体験してもらいました。
15分間のアイシング、どうだったかな・・・。
ホントは・・・こんな時間を割いてもらって、皆さんの前でエラそうに
話するつもりはなかったのです(一保護者の分際で・・・!)。
「せっかくなので」と先生の計らい、です。。恐縮です(汗)。
準備不足で、時間もやはり足りませんでしたが、
聞いていたうちの長女が 「 大丈夫、わかりやすかったよ、ママ 」 と
中学生にも理解できるレベルで話が出来たようなので
まあ・・・いっか。
「ケガの処置」に関する講義をちょこっと(20分間)させてもらいました。

話を聞いてもらう間に、
実際に 「RICE処置」 と 「アイスバケツ」 で足関節捻挫に対する初期の処置を
中学生に体験してもらいました。
15分間のアイシング、どうだったかな・・・。
ホントは・・・こんな時間を割いてもらって、皆さんの前でエラそうに
話するつもりはなかったのです(一保護者の分際で・・・!)。
「せっかくなので」と先生の計らい、です。。恐縮です(汗)。
準備不足で、時間もやはり足りませんでしたが、
聞いていたうちの長女が 「 大丈夫、わかりやすかったよ、ママ 」 と
中学生にも理解できるレベルで話が出来たようなので
まあ・・・いっか。
2015年10月06日
ココロも、トレーニング。
数年前から、心理学についての書籍を手にすることが多くなりました。
「コンディショニング」の中に心理的サポートという役割も含まれるのがこの仕事です。
まさしく、「 ココロとカラダは繋がっている 」のだなあ、と実感します。
先日、奄美パークに 「 メンタリスト Daigo 」の講演会を聞きに行きました。
読書が趣味、というだけあって、話し方がスマートな方でした。
Daigo さん、自分の過去の実話をベースに
「 自分を変える 」というテーマでお話されたのが非常に興味深かった。
内容までは書けませんが、「 自己分析 」 と 「 目標設定 」から自分を変えていくことが出来る。
メンタル面のスキル(技術)を学ぶことで、実際、自らを変えた当人だということが
この 「 メンタリスト 」として成功をつかむきっかけとなったようです。
私が一番面白かったのは、ココですが、
テレビでよくする 「人の心を読む」かのように、ペン8色から
観客が引き当てた色を当てる 「パフォーマンス」 は本当に驚きでしたね。
私と出会うスポーツ選手は、「ケガをして練習ができない」状況が大半です。
そして、「こいつは、治療も出来ないくせに、何をする人だろう?」と
疑心暗鬼の目で、来ます(笑)。
そんな疑心暗鬼+マイナスオーラ全開でやってきますから、
「原因」が見えていても、聞く耳をもってもらうまでに、「パフォーマンス」が大事です。
ペンの色をあてることは絶対できませんが(笑)
ホンの数センチのテープで、動きを変えることはできます。
そういう 「パフォーマンス」 が結構大事だと、講演の中でも触れられていまして
これも私なりの 「 心理作戦 」だったんだな、と納得しました。
その作戦が成功したら、次は 「 自己分析 」です。
動きながら、自分のカラダと向き合うことを追求します。
頭で考えた動きを、身体で表現し、五感を研ぎ澄まして、身体の変化を感じてもらいます。
そこで、自分のカラダに気づいてもらう。
「ココが硬い」とか「これが出来ない」とか「ココが弱い」とか。
マイナスの子に、出来ない事ばかりに目を向けさせて、余計凹ましては本末転倒なので
「 やれば、できるんだよ 」
・・・身体の使い方を知り、出来ることが増える。徐々に笑顔が見えてきます。
そこで、やっと、本人が原因を知る。いや、知ろうとする。そしてどうにかしたい、と欲する。
選手にとって、「痛みを取る事」は、最終目標ではなく、優先順位の問題であって、
最終目標はあくまで
「パフォーマンスを高める」 ことなのです。
目標が明確に定まれば、あとはやるべきことがおのずと見えてきます。
今は、練習には同じように参加できないかもしれないけど、
その練習時間で、自分はどう時間を使うべきか
そこまで判断してくれる選手は、賢い。
「 考え方が変われば、行動が変わる 」
ココロも、適切なアプローチで地道にトレーニングを積めば、
「弱い心」もきっと、強くなれる。
トレーナー活動を通じて、私が一番学んだことの一つかもしれません。
「コンディショニング」の中に心理的サポートという役割も含まれるのがこの仕事です。
まさしく、「 ココロとカラダは繋がっている 」のだなあ、と実感します。
先日、奄美パークに 「 メンタリスト Daigo 」の講演会を聞きに行きました。
読書が趣味、というだけあって、話し方がスマートな方でした。
Daigo さん、自分の過去の実話をベースに
「 自分を変える 」というテーマでお話されたのが非常に興味深かった。
内容までは書けませんが、「 自己分析 」 と 「 目標設定 」から自分を変えていくことが出来る。
メンタル面のスキル(技術)を学ぶことで、実際、自らを変えた当人だということが
この 「 メンタリスト 」として成功をつかむきっかけとなったようです。
私が一番面白かったのは、ココですが、
テレビでよくする 「人の心を読む」かのように、ペン8色から
観客が引き当てた色を当てる 「パフォーマンス」 は本当に驚きでしたね。
私と出会うスポーツ選手は、「ケガをして練習ができない」状況が大半です。
そして、「こいつは、治療も出来ないくせに、何をする人だろう?」と
疑心暗鬼の目で、来ます(笑)。
そんな疑心暗鬼+マイナスオーラ全開でやってきますから、
「原因」が見えていても、聞く耳をもってもらうまでに、「パフォーマンス」が大事です。
ペンの色をあてることは絶対できませんが(笑)
ホンの数センチのテープで、動きを変えることはできます。
そういう 「パフォーマンス」 が結構大事だと、講演の中でも触れられていまして
これも私なりの 「 心理作戦 」だったんだな、と納得しました。
その作戦が成功したら、次は 「 自己分析 」です。
動きながら、自分のカラダと向き合うことを追求します。
頭で考えた動きを、身体で表現し、五感を研ぎ澄まして、身体の変化を感じてもらいます。
そこで、自分のカラダに気づいてもらう。
「ココが硬い」とか「これが出来ない」とか「ココが弱い」とか。
マイナスの子に、出来ない事ばかりに目を向けさせて、余計凹ましては本末転倒なので
「 やれば、できるんだよ 」
・・・身体の使い方を知り、出来ることが増える。徐々に笑顔が見えてきます。
そこで、やっと、本人が原因を知る。いや、知ろうとする。そしてどうにかしたい、と欲する。
選手にとって、「痛みを取る事」は、最終目標ではなく、優先順位の問題であって、
最終目標はあくまで
「パフォーマンスを高める」 ことなのです。
目標が明確に定まれば、あとはやるべきことがおのずと見えてきます。
今は、練習には同じように参加できないかもしれないけど、
その練習時間で、自分はどう時間を使うべきか
そこまで判断してくれる選手は、賢い。
「 考え方が変われば、行動が変わる 」
ココロも、適切なアプローチで地道にトレーニングを積めば、
「弱い心」もきっと、強くなれる。
トレーナー活動を通じて、私が一番学んだことの一つかもしれません。
2015年10月03日
「運動」と「トレーニング」
「温故知新」
” 昔のことをよく学び そこから新しい知識や 道理を得ること
また 過去の事柄を研究して 現在の事態に対処すること ”
トレーニングの世界も、常に新しいツールが生み出されています。
「コアトレーニング」や「体幹トレーニング」も
言葉が先走り、流行めいた時期も
もはや大昔のことのような感覚です。
(無論、重要なトレーニングの1つであることは、間違いありません。)
情報が交錯し、グローバル化したスピード時代の中で
自分の 「信念」 と自問自答しながら、何の情報を、何の為に活用していくのか?
自らの判断基準を、明確にしていくために
「 温故知新 (故きを温め、新しきを知る) 」
基本は、大切だと思います。
少し、時間に余裕があるときには
トレーニング理論の基礎 となる本を読み返したり、
活躍されているトレーナーさんの考え方をネットで検索したりします。
トレーニングには昔から変わらない 「 原則 」 というものがあり
その中核となるのが
「 漸進性の原則 」・・・身体を強化するには、少しづつ(=漸進)負荷を挙げて、身体をその負荷に適応させていく
「 過負荷の原則 」・・・身体を強化するには、「慣れている」刺激よりも、
さらに大きな刺激(=過負荷)を身体に与える必要がある
日常生活と違う動作(スポーツだったり、行事だったり)をすると、疲れますよね?
普段の生活で、「座る」仕事の多い人が、旅行で、いつもになく「歩く」とする。
次の日、足が痛かったり、筋肉痛があることに気づく。
「日頃、運動不足だからなあ・・・」と、旅行をきっかけに、ウォーキングの時間を日常生活に取り入れる。
最初は10分の運動が、1週間後、15分、2週間後、20分に増やしてみる。
そのうち、「ウォーキング」から「ランニング」に。まず5分のランニングから始める。
・10分のウォーキングから、15分、20分と時間を増やす。
・ウォーキングからランニングにする。
いずれも 「 漸進性・過負荷の原則 」 に当てはまります。
運動の内容 (ウォーキング→ランニング) をかえたり、回数、時間、頻度など、
「 トレーニング 」とは、こういった負荷を変えることで、刺激に変化をあたえ
環境の変化に身体を適応させていくことをさします。
「 運動 」とは、同じ負荷、同じ刺激で、内容に変化をもたないものをさします。
これは、どちらが良くて、どちらが間違いというものではなく、
「 目的 」の違いで選択が変わります。
週1回でも、「 身体を動かして、すっきりしたい 」 という目的ならば
後者の、「運動」という定義は適当かな、と思います。
「 運動 」と 「 トレーニング 」 の違い
基本、原則、基礎は、全ての原点
不変なものであり、深いもの。
何か、新しい物事が巡ってくるその瞬間のために
今は、基本を丁寧に学び直して
その一瞬を見逃さないよう、待つ時期なのかな、と思います。。
” 昔のことをよく学び そこから新しい知識や 道理を得ること
また 過去の事柄を研究して 現在の事態に対処すること ”
トレーニングの世界も、常に新しいツールが生み出されています。
「コアトレーニング」や「体幹トレーニング」も
言葉が先走り、流行めいた時期も
もはや大昔のことのような感覚です。
(無論、重要なトレーニングの1つであることは、間違いありません。)
情報が交錯し、グローバル化したスピード時代の中で
自分の 「信念」 と自問自答しながら、何の情報を、何の為に活用していくのか?
自らの判断基準を、明確にしていくために
「 温故知新 (故きを温め、新しきを知る) 」
基本は、大切だと思います。
少し、時間に余裕があるときには
トレーニング理論の基礎 となる本を読み返したり、
活躍されているトレーナーさんの考え方をネットで検索したりします。
トレーニングには昔から変わらない 「 原則 」 というものがあり
その中核となるのが
「 漸進性の原則 」・・・身体を強化するには、少しづつ(=漸進)負荷を挙げて、身体をその負荷に適応させていく
「 過負荷の原則 」・・・身体を強化するには、「慣れている」刺激よりも、
さらに大きな刺激(=過負荷)を身体に与える必要がある
日常生活と違う動作(スポーツだったり、行事だったり)をすると、疲れますよね?
普段の生活で、「座る」仕事の多い人が、旅行で、いつもになく「歩く」とする。
次の日、足が痛かったり、筋肉痛があることに気づく。
「日頃、運動不足だからなあ・・・」と、旅行をきっかけに、ウォーキングの時間を日常生活に取り入れる。
最初は10分の運動が、1週間後、15分、2週間後、20分に増やしてみる。
そのうち、「ウォーキング」から「ランニング」に。まず5分のランニングから始める。
・10分のウォーキングから、15分、20分と時間を増やす。
・ウォーキングからランニングにする。
いずれも 「 漸進性・過負荷の原則 」 に当てはまります。
運動の内容 (ウォーキング→ランニング) をかえたり、回数、時間、頻度など、
「 トレーニング 」とは、こういった負荷を変えることで、刺激に変化をあたえ
環境の変化に身体を適応させていくことをさします。
「 運動 」とは、同じ負荷、同じ刺激で、内容に変化をもたないものをさします。
これは、どちらが良くて、どちらが間違いというものではなく、
「 目的 」の違いで選択が変わります。
週1回でも、「 身体を動かして、すっきりしたい 」 という目的ならば
後者の、「運動」という定義は適当かな、と思います。
「 運動 」と 「 トレーニング 」 の違い
基本、原則、基礎は、全ての原点
不変なものであり、深いもの。
何か、新しい物事が巡ってくるその瞬間のために
今は、基本を丁寧に学び直して
その一瞬を見逃さないよう、待つ時期なのかな、と思います。。
2015年10月01日
いくつになっても…
チーム指導以外にも、一般の方々へのトレーニング指導や
「パーソナルトレーナー」として
マンツーマンでのトレーニング指導も行っています。
最高齢は80歳オーバーのクライアント。
現在約8ヶ月。毎週一回、自宅に伺って、1時間ほど身体を動かしています。
人生初の80歳へのトレーニング指導…正直、自分自身にも不安もありました。。
が、とにかくアクティブなおばあちゃん!
病院へも一切かからず、このお年で投薬もなし。タラソへも積極的に通われています。
スタートは、徒手抵抗のストレッチから開始。
「膝の痛みの改善」が一番の課題だったのですが、加齢による筋力の萎縮と関節の拘縮がある。
毎週、毎週、少しずつ、少しずつ
会話しながら、動きを確認しながら手探りで指導を始めました。
トレーニングを開始して4ヶ月くらいから、自体重をコントロールしていく方向に切り替えると、意外と「動ける」。
話を聞いて…納得。
自営業の為、以前は重い荷物を持って、忙しく働かれていたようです。。
関節は拘縮しているものの、
とても身体の使い方が上手。
生活習慣の中で、筋力が身に付いてらっしゃったようです。
この自体重でのトレーニングを開始してから、歩行時の膝の痛みは改善されました。
80年の積み重ねが、今にあるのだ、
そう確信しています。
例えば、今ではこんな動きも出来ます。

股関節のストレッチ

肩甲骨の内・外転
今日は、自体重で「デッドリフト」も
正しいフォームで出来るようになりました!
ちょうど、「椅子からの立ち上がり」によく似た動作です。
「20年連れ添って初めてパーソナルトレーナーと呼べる」
と私の恩師はおっしゃっていました。
それくらい、クライアントの健康を守る為に寄り添う仕事なのだと思います。
病院とは違い、痛みが消えてからが本当のトレーニング。
健康を維持し続けるには
身体を動かし続けるしかない。
日々変化していく身体に、トレーナーは
「クライアント自身が自分の健康どう向き合うのか」
お手伝いをするのが
パーソナルトレーナーの本来の仕事なのかな。。と思います。
今、私自身が未来をみた時
このクライアントのように80歳を越えても
健康に、素敵なライフスタイルを
私も送りたいなぁ。。
「パーソナルトレーナー」として
マンツーマンでのトレーニング指導も行っています。
最高齢は80歳オーバーのクライアント。
現在約8ヶ月。毎週一回、自宅に伺って、1時間ほど身体を動かしています。
人生初の80歳へのトレーニング指導…正直、自分自身にも不安もありました。。
が、とにかくアクティブなおばあちゃん!
病院へも一切かからず、このお年で投薬もなし。タラソへも積極的に通われています。
スタートは、徒手抵抗のストレッチから開始。
「膝の痛みの改善」が一番の課題だったのですが、加齢による筋力の萎縮と関節の拘縮がある。
毎週、毎週、少しずつ、少しずつ
会話しながら、動きを確認しながら手探りで指導を始めました。
トレーニングを開始して4ヶ月くらいから、自体重をコントロールしていく方向に切り替えると、意外と「動ける」。
話を聞いて…納得。
自営業の為、以前は重い荷物を持って、忙しく働かれていたようです。。
関節は拘縮しているものの、
とても身体の使い方が上手。
生活習慣の中で、筋力が身に付いてらっしゃったようです。
この自体重でのトレーニングを開始してから、歩行時の膝の痛みは改善されました。
80年の積み重ねが、今にあるのだ、
そう確信しています。
例えば、今ではこんな動きも出来ます。

股関節のストレッチ

肩甲骨の内・外転
今日は、自体重で「デッドリフト」も
正しいフォームで出来るようになりました!
ちょうど、「椅子からの立ち上がり」によく似た動作です。
「20年連れ添って初めてパーソナルトレーナーと呼べる」
と私の恩師はおっしゃっていました。
それくらい、クライアントの健康を守る為に寄り添う仕事なのだと思います。
病院とは違い、痛みが消えてからが本当のトレーニング。
健康を維持し続けるには
身体を動かし続けるしかない。
日々変化していく身体に、トレーナーは
「クライアント自身が自分の健康どう向き合うのか」
お手伝いをするのが
パーソナルトレーナーの本来の仕事なのかな。。と思います。
今、私自身が未来をみた時
このクライアントのように80歳を越えても
健康に、素敵なライフスタイルを
私も送りたいなぁ。。
2015年09月23日
人生負け勝ち
先月、全日本女子バレーボール代表の元監督、柳本さんが奄美に来島されました。
その時、うちの旦那が講習会に参加した長女の名前の入ったサインを
ちゃっかりもらってて、我が家に飾ってあります。
ふと、それが目に入りました。
柳本監督の座右の銘 「人生負け勝ち」
確か、本も書かれていたような。昔拝読した覚えがあります。
『人は勝っているとき、必ず「負けの芽」を育んでいる。
そして負けの中には次へつながる「勝ちの芽」がある。
勝ちは負けの隣にある―。
才能をいかに引き出すか、苦境でいかに我慢させるか。』
そういう意味が込められているようです。。。
確かになあ。。
昨日の 「負け」 から、改めて、現在のトレーニングメニューを見直してみました。
プランニングに活用した参考文献など、もう一度深く読み込んでみましたら、
大事なところを、読み落としていたり、
大事だと思っていたはずなのに、ポイントが少しずれてしまっていたり。
現在のメニューを設定した時には、それはそれで 「よし」と思って指導したけど
そのメニューの意図を、もっと深く、伝えていけるかもしれない、
今なら、もっと伝わるかもしれない。
そう直感的におもいました。
今日のウエイトトレーニングの指導は、もう一度今のメニューの復習をやりました。
日頃からしつこく指導しているフォームなど、
現在やっているトレーニングの 『意味』 を伝えたいと思った・・・のですが
言葉が、でない。
「こんな感じなんだけど、わかる?」とか
「こんなイメージで・・・」とか
ブログでは、とうてい伝わらないくらい、言葉足らずで、
「いや、ごめん、違う。こうじゃない」
とか・・・ホント、最悪な指導(苦)。とにかく、デモを見せて、感覚を伝えるしか、ない。
でも、あまりに私が、ごちゃごちゃしているのが分かったんでしょうね・・・
逆に、選手が、いつもになくお互いに話をしたり、アドバイスしあったりし始めて、
最終的に・・・いつもより、伝えたいことが、伝わった気がしました・・・(笑)。
自分の中で、カタチにならなかった感覚が、
今日は新しく、沢山みつかった気がします。
「負ける」 のも、悪くない。
その時、うちの旦那が講習会に参加した長女の名前の入ったサインを
ちゃっかりもらってて、我が家に飾ってあります。
ふと、それが目に入りました。
柳本監督の座右の銘 「人生負け勝ち」
確か、本も書かれていたような。昔拝読した覚えがあります。
『人は勝っているとき、必ず「負けの芽」を育んでいる。
そして負けの中には次へつながる「勝ちの芽」がある。
勝ちは負けの隣にある―。
才能をいかに引き出すか、苦境でいかに我慢させるか。』
そういう意味が込められているようです。。。
確かになあ。。
昨日の 「負け」 から、改めて、現在のトレーニングメニューを見直してみました。
プランニングに活用した参考文献など、もう一度深く読み込んでみましたら、
大事なところを、読み落としていたり、
大事だと思っていたはずなのに、ポイントが少しずれてしまっていたり。
現在のメニューを設定した時には、それはそれで 「よし」と思って指導したけど
そのメニューの意図を、もっと深く、伝えていけるかもしれない、
今なら、もっと伝わるかもしれない。
そう直感的におもいました。
今日のウエイトトレーニングの指導は、もう一度今のメニューの復習をやりました。
日頃からしつこく指導しているフォームなど、
現在やっているトレーニングの 『意味』 を伝えたいと思った・・・のですが
言葉が、でない。
「こんな感じなんだけど、わかる?」とか
「こんなイメージで・・・」とか
ブログでは、とうてい伝わらないくらい、言葉足らずで、
「いや、ごめん、違う。こうじゃない」
とか・・・ホント、最悪な指導(苦)。とにかく、デモを見せて、感覚を伝えるしか、ない。
でも、あまりに私が、ごちゃごちゃしているのが分かったんでしょうね・・・
逆に、選手が、いつもになくお互いに話をしたり、アドバイスしあったりし始めて、
最終的に・・・いつもより、伝えたいことが、伝わった気がしました・・・(笑)。
自分の中で、カタチにならなかった感覚が、
今日は新しく、沢山みつかった気がします。
「負ける」 のも、悪くない。
2015年09月20日
トレーナーの役割
「トレーナー」の役割、日本では非常に曖昧です。
なぜなら 『職業』 としてまだまだ確立されていないからです。
例えば、スポーツ選手が、ケガをしたら、
大半は整骨院、鍼灸院、などの治療院に行く。病院で受診する。
これは、「何をしてくれる場所なのか」明確だからです。
「トレーナーは、こういうサービスをしてくれる人」とはっきり世間一般に提示できればいい。ごく簡単に言うと
「カラダの使い方を、学べる場所」
なのかな…。
島や小さな地域に病院が限られてて、その病院が全ての患者を引き受けなければならないように、
トレーナーも、スポーツ選手の絶対数に比べれば数は非常に少なく、
その場、その時でさまざまなニーズに対応しなければなりません。
逆に言えば、トレーナーのパーソナリティ(個性)に委ねることも出来る。
例えば、
ヘアスタイルは、いつも同じ美容師さん、とか
子供が熱が出たら、小児科はここに行く、とか
車の調子が悪い時は、必ずこの整備士さんに任せる、とか
何か、今のスポーツ活動の状況から 「変わりたい」 とき、
相談にのれる場所(人)としてありたい、と思います。
一番、多い相談は 「ケガ」 をしたとき。
「みてください」と私のところへ来られる方(クライアント)は、たいてい治療してみても解決しない方です。
でもきっとそのクライアントも
私の出来る「サービス」がわからないので、たいてい半信半疑です(笑)。
そのお気持ちもよく分かるので、私の出来る事は精一杯対応しますが
クライアントのニーズと、私がサービスした内容に食い違いが起こることもありますし、
うまくマッチすることもあります。
靭帯損傷(捻挫など)や骨折をした場合でも、
その部分を治すことはできませんが、原因は見つけます。
診断は出来ませんが、整形外科の画像診断で詳しい情報が必要であると判断した場合は、
受診を勧めます。
トレーナーの私が出来る一番の 「サービス」 は
ケガの原因をどう、自分で 「解決」 していくのか?
つまり、クライアント自身が どういう 『努力』 をすべきなのか。
その方法を、提示し、ともに乗り越えていく。
一過性ではなく、クライアントと長く付き合っていく仕事だと思っています。
クライアントのスポーツ人生を見守り、ともに歩んでいく「サポート」が
トレーナーの一番の役割だと思っています。
理想は程遠く、まだまだ、人間的に未熟な面が多い。
失敗も多く、日々反省の毎日です。
それでも、この仕事を通じての人との出会いは
最高の財産です。
なぜなら 『職業』 としてまだまだ確立されていないからです。
例えば、スポーツ選手が、ケガをしたら、
大半は整骨院、鍼灸院、などの治療院に行く。病院で受診する。
これは、「何をしてくれる場所なのか」明確だからです。
「トレーナーは、こういうサービスをしてくれる人」とはっきり世間一般に提示できればいい。ごく簡単に言うと
「カラダの使い方を、学べる場所」
なのかな…。
島や小さな地域に病院が限られてて、その病院が全ての患者を引き受けなければならないように、
トレーナーも、スポーツ選手の絶対数に比べれば数は非常に少なく、
その場、その時でさまざまなニーズに対応しなければなりません。
逆に言えば、トレーナーのパーソナリティ(個性)に委ねることも出来る。
例えば、
ヘアスタイルは、いつも同じ美容師さん、とか
子供が熱が出たら、小児科はここに行く、とか
車の調子が悪い時は、必ずこの整備士さんに任せる、とか
何か、今のスポーツ活動の状況から 「変わりたい」 とき、
相談にのれる場所(人)としてありたい、と思います。
一番、多い相談は 「ケガ」 をしたとき。
「みてください」と私のところへ来られる方(クライアント)は、たいてい治療してみても解決しない方です。
でもきっとそのクライアントも
私の出来る「サービス」がわからないので、たいてい半信半疑です(笑)。
そのお気持ちもよく分かるので、私の出来る事は精一杯対応しますが
クライアントのニーズと、私がサービスした内容に食い違いが起こることもありますし、
うまくマッチすることもあります。
靭帯損傷(捻挫など)や骨折をした場合でも、
その部分を治すことはできませんが、原因は見つけます。
診断は出来ませんが、整形外科の画像診断で詳しい情報が必要であると判断した場合は、
受診を勧めます。
トレーナーの私が出来る一番の 「サービス」 は
ケガの原因をどう、自分で 「解決」 していくのか?
つまり、クライアント自身が どういう 『努力』 をすべきなのか。
その方法を、提示し、ともに乗り越えていく。
一過性ではなく、クライアントと長く付き合っていく仕事だと思っています。
クライアントのスポーツ人生を見守り、ともに歩んでいく「サポート」が
トレーナーの一番の役割だと思っています。
理想は程遠く、まだまだ、人間的に未熟な面が多い。
失敗も多く、日々反省の毎日です。
それでも、この仕事を通じての人との出会いは
最高の財産です。
2015年09月19日
名瀬小家庭教育学級
昨夜はお隣校区の名瀬小学校の
家庭教育学級で「親子でストレッチング」担当しました。
なんとびっくり…参加者100人越え。


興味もってる方、こんなにが多いんだ…
と再認識です。
日頃、なかなか身体を動かす機会のないお父さん、お母さん。
「子供さんは、途中飽きても構いません。どうぞ、自分自身のために、時間をお使い下さい。」
自分の身体と向き合う時間、大事だと思います。
ちょっと「疲れたー」というくらい、身体を動かしてみると
身体は軽くなります。
反省もいろいろあります。毎回、学ぶことが沢山です。
体育館を出ると、風が心地よくて。
秋ですね。。
今日も、新たな出会いに感謝です。
家庭教育学級で「親子でストレッチング」担当しました。
なんとびっくり…参加者100人越え。


興味もってる方、こんなにが多いんだ…
と再認識です。
日頃、なかなか身体を動かす機会のないお父さん、お母さん。
「子供さんは、途中飽きても構いません。どうぞ、自分自身のために、時間をお使い下さい。」
自分の身体と向き合う時間、大事だと思います。
ちょっと「疲れたー」というくらい、身体を動かしてみると
身体は軽くなります。
反省もいろいろあります。毎回、学ぶことが沢山です。
体育館を出ると、風が心地よくて。
秋ですね。。
今日も、新たな出会いに感謝です。
2015年09月17日
下腿部(膝から下)の痛み
膝から下の部分への痛みを訴えた選手が2名いたので、みました。
1人は、ふくらはぎ(外側)の痛み
1人は、足関節(捻挫の自覚はなし)の痛みでしたが、
接骨院の治療師からは「下腿部からの負担だろう」とのこと。
立ち方と動作から、痛めてしまう原因は予測できます。
前者は、股関節が硬く、動く範囲が狭まることで、負担がかかっている。
1か月前は、反対側ですが、アキレス腱炎を起こしている。
後者は、柔軟性は高いのですが、それを支持できる筋力が不足している。
時折、腰痛が起こる、と聞けば
明らかに体幹の弱さがうかがえます。
同じ部位の痛みでも、原因は様々です。
こういう子は負荷がかかると、場所をかえて痛みが出る部位がある。
さて・・・
「トレーナー」はここから何が彼女たちに何をするのか?
私が 「みた」 ところで、この部位の治療は行いません。
もちろん、原因は伝えます。分かる範囲で、はっきりと伝えます。
本人の持っている体力的な面と、動作の分析を合わせて、「なぜ痛みがでるのか」説明します。
次に、その問題解決の為のアプローチを指導します。
特に「身体の使い方」を徹底して教えます。
例えば、ストレッチ一つ、癖を直したり、意識する場所を確認するだけで変わります。
膝下に負担のかかる子は、
だいたいお尻を締められない (股関節まわりの筋を含む、体幹筋の弱さによるもの) が多いので、
「こういう事をやれば、出来るようになるよ」と
実際本人が「こういう感じ」と感覚を理解するまで、指導します。
こちらのイメージと相手のイメージを繋げて、初めて選手自身が
目指すべき目標が見えるのだと思います。
やはり 「体幹」 は重要です。
1人は、ふくらはぎ(外側)の痛み
1人は、足関節(捻挫の自覚はなし)の痛みでしたが、
接骨院の治療師からは「下腿部からの負担だろう」とのこと。
立ち方と動作から、痛めてしまう原因は予測できます。
前者は、股関節が硬く、動く範囲が狭まることで、負担がかかっている。
1か月前は、反対側ですが、アキレス腱炎を起こしている。
後者は、柔軟性は高いのですが、それを支持できる筋力が不足している。
時折、腰痛が起こる、と聞けば
明らかに体幹の弱さがうかがえます。
同じ部位の痛みでも、原因は様々です。
こういう子は負荷がかかると、場所をかえて痛みが出る部位がある。
さて・・・
「トレーナー」はここから何が彼女たちに何をするのか?
私が 「みた」 ところで、この部位の治療は行いません。
もちろん、原因は伝えます。分かる範囲で、はっきりと伝えます。
本人の持っている体力的な面と、動作の分析を合わせて、「なぜ痛みがでるのか」説明します。
次に、その問題解決の為のアプローチを指導します。
特に「身体の使い方」を徹底して教えます。
例えば、ストレッチ一つ、癖を直したり、意識する場所を確認するだけで変わります。
膝下に負担のかかる子は、
だいたいお尻を締められない (股関節まわりの筋を含む、体幹筋の弱さによるもの) が多いので、
「こういう事をやれば、出来るようになるよ」と
実際本人が「こういう感じ」と感覚を理解するまで、指導します。
こちらのイメージと相手のイメージを繋げて、初めて選手自身が
目指すべき目標が見えるのだと思います。
やはり 「体幹」 は重要です。
2015年09月15日
素早く、動く。
運動会シーズンです。
一昨日、初めての中学校の体育祭でした。
中学生にもなれば、子供達だけで、運営が出来るんだ・・・
私はとても子供達の成長に感動しました。
体育祭でもついつい職業病で・・・走る動作を分析しながら観てしまう私(笑)。
素早く、動く。
これもトレーニングの目的の中で大事な「体力要素」の一つですが
「スピード」と「アジリティ」と、大きく二つの要素に分けられます
「スピード」とは 動作速度を高めるために必要な、技術と能力。
つまり、「速く身体を動かす」ということ。
「アジリティ」とは、動作速度または動作様式を急激に変化させるために必要な、技術と能力。
つまり、「速く身体を動かす中で、方向転換をする」ということ
「走る」動作って、単純だし、何かしら「走る」場面って多いので、
速く走れる子は、 「センス(感覚・能力)」があって、遅い子は 「センス」がない と思われがちです。
「走る」のも技術、そう捉えれば、
技術を身につければ、速く走る(動く)こともできるようになる。
子供の「かけっこ教室」に参加すると
様々な走り方(技術)を教えてくださって、意外と知らない事が多い。
「走り方」なんて…詳しく教えてもらった事が無い。そういう人がほとんどではないでしょうか?
チームトレーニングも
今年は 『走る動作』 トレーニング(ランニングスキル) から始めてみました。
ポイントは4つ。陸上部ではないので、ごくごくシンプルに。。
①股関節の回転半径を短くする
②両脚を前後に幅広く、速く動かす
③肘から後ろに、肩の高さまで腕を引く
④片足で立った時に、頭までまっすぐコアが崩れない姿勢
最初ははちゃめちゃだった動作も、少しかっこよく(?)なってきましたよ。
私は、大学時代、陸上部の先生にトレーニング指導を受けていて
「バレーボールになぜ走るフォームって必要なのかな?」と疑問に思ったこともありました。
今更ですが、納得。
選手も理屈でイメージ作り。あとは実践。
わかっちゃいるけど、難しい。
ラダーを使ってみたり、ミニハードルを使ってみたり
手をかえ、品をかえ、ひたすらコツコツ、理想の動き作りを時間をかけて目指します。
きちんと指導する側のイメージをやってみせて、修正して、できたら褒めて、伝え続ける。
指導者の気持ちがブレるような事は、子供達には伝わりません。
これですね。まさに、これ。
やってみせ、言って聞かせて、させてみせ、ほめてやらねば、人は動かじ。 (山本五十六)
何が一番大変かって・・・自分のカラダを鍛え続けて、見本となることです・・・(涙)
一昨日、初めての中学校の体育祭でした。
中学生にもなれば、子供達だけで、運営が出来るんだ・・・
私はとても子供達の成長に感動しました。
体育祭でもついつい職業病で・・・走る動作を分析しながら観てしまう私(笑)。
素早く、動く。
これもトレーニングの目的の中で大事な「体力要素」の一つですが
「スピード」と「アジリティ」と、大きく二つの要素に分けられます
「スピード」とは 動作速度を高めるために必要な、技術と能力。
つまり、「速く身体を動かす」ということ。
「アジリティ」とは、動作速度または動作様式を急激に変化させるために必要な、技術と能力。
つまり、「速く身体を動かす中で、方向転換をする」ということ
「走る」動作って、単純だし、何かしら「走る」場面って多いので、
速く走れる子は、 「センス(感覚・能力)」があって、遅い子は 「センス」がない と思われがちです。
「走る」のも技術、そう捉えれば、
技術を身につければ、速く走る(動く)こともできるようになる。
子供の「かけっこ教室」に参加すると
様々な走り方(技術)を教えてくださって、意外と知らない事が多い。
「走り方」なんて…詳しく教えてもらった事が無い。そういう人がほとんどではないでしょうか?
チームトレーニングも
今年は 『走る動作』 トレーニング(ランニングスキル) から始めてみました。
ポイントは4つ。陸上部ではないので、ごくごくシンプルに。。
①股関節の回転半径を短くする
②両脚を前後に幅広く、速く動かす
③肘から後ろに、肩の高さまで腕を引く
④片足で立った時に、頭までまっすぐコアが崩れない姿勢
最初ははちゃめちゃだった動作も、少しかっこよく(?)なってきましたよ。
私は、大学時代、陸上部の先生にトレーニング指導を受けていて
「バレーボールになぜ走るフォームって必要なのかな?」と疑問に思ったこともありました。
今更ですが、納得。
選手も理屈でイメージ作り。あとは実践。
わかっちゃいるけど、難しい。
ラダーを使ってみたり、ミニハードルを使ってみたり
手をかえ、品をかえ、ひたすらコツコツ、理想の動き作りを時間をかけて目指します。
きちんと指導する側のイメージをやってみせて、修正して、できたら褒めて、伝え続ける。
指導者の気持ちがブレるような事は、子供達には伝わりません。
これですね。まさに、これ。
やってみせ、言って聞かせて、させてみせ、ほめてやらねば、人は動かじ。 (山本五十六)
何が一番大変かって・・・自分のカラダを鍛え続けて、見本となることです・・・(涙)
2015年09月10日
コンディショニング
「コンディショニング」って何でしょう?
まさしく「コンディション(状態・状況)を整える」事なのだと思います。
日本体育協会アスレチックトレーナーでは
「勝つための全ての準備」
と定義付けられ、その要因は以下の3つ。
①環境を整える
②身体を整える
③心を整える
フィジカル(身体的)トレーニングの「コンディショニング」はスポーツ生理学という、運動時に必要とされるエネルギーシステム(代謝)を強調したプログラム、といえます。
ここには競技特性が大きく関与し、
多くのプログラムには運動/休息比が用いられます。
例えば、バレーボール(国際大会)の場合、
・1プレー3~10秒
・1ラリー5~30秒
・1セット20~30秒
・1試合60~120分
・プレー間20~30秒(休息)
・セット間3分(休息)
で、行われます。
「コンディショニング」を考える上では、この競技の特徴の中で、「いかに最高のパフォーマンスを出せるか」ということを考慮したうえで
「準備」を整えなければなりません。
これこそ、まさに”ゲームのための身体づくり”と言えます。
「体力をつける」ためにスピードの強弱、セットの時間や休息時間を無視した「走り続ける」トレーニングだけでは
例え選手が一生懸命トレーニングを積んだとしても、ケガが絶えなかったり、体力の改善が見えなかったりすることはよく現場でみられます。
「コンディショニングプログラム」はおそらく選手が一番嫌がるプログラムかもしれません。。
だから一番テンションが下がます・・・
今日は「頑張れ!自分に負けるな!」と叱咤激励。。キツいのも、よく分かるから…観ていてこちらも、力が入ります。
だから、写真も撮り忘れてしまいました(笑)
また時間があるときに、詳しく紹介したいと思います。
まさしく「コンディション(状態・状況)を整える」事なのだと思います。
日本体育協会アスレチックトレーナーでは
「勝つための全ての準備」
と定義付けられ、その要因は以下の3つ。
①環境を整える
②身体を整える
③心を整える
フィジカル(身体的)トレーニングの「コンディショニング」はスポーツ生理学という、運動時に必要とされるエネルギーシステム(代謝)を強調したプログラム、といえます。
ここには競技特性が大きく関与し、
多くのプログラムには運動/休息比が用いられます。
例えば、バレーボール(国際大会)の場合、
・1プレー3~10秒
・1ラリー5~30秒
・1セット20~30秒
・1試合60~120分
・プレー間20~30秒(休息)
・セット間3分(休息)
で、行われます。
「コンディショニング」を考える上では、この競技の特徴の中で、「いかに最高のパフォーマンスを出せるか」ということを考慮したうえで
「準備」を整えなければなりません。
これこそ、まさに”ゲームのための身体づくり”と言えます。
「体力をつける」ためにスピードの強弱、セットの時間や休息時間を無視した「走り続ける」トレーニングだけでは
例え選手が一生懸命トレーニングを積んだとしても、ケガが絶えなかったり、体力の改善が見えなかったりすることはよく現場でみられます。
「コンディショニングプログラム」はおそらく選手が一番嫌がるプログラムかもしれません。。
だから一番テンションが下がます・・・
今日は「頑張れ!自分に負けるな!」と叱咤激励。。キツいのも、よく分かるから…観ていてこちらも、力が入ります。
だから、写真も撮り忘れてしまいました(笑)
また時間があるときに、詳しく紹介したいと思います。
2015年09月08日
ウエイトトレーニング
最近、 ”スムージー” という飲み物にはまっていて、
グリーンスムージーからちょっとハマって、小松菜とオレンジ、バナナはおススメです。
今日はちょっと腐れかけたバナナとグアバと牛乳でつくりました。種はあるけど美味しいです。
本日は7時半からの練習。
練習後にウエイトトレーニングをやりました。
今年のチームは早い段階から導入できたので、夏休みも週2回やってきました。
変化をつけるために「高重量の日」と「低重量の日」に設定しています。
9月から、シーズンの変わり目を期にメニューと負荷を変えています。
スペースと器具と時間の関係で、沢山のメニューを行うことはできませんが
「ビッグⅢ」と呼ばれる
・スクワット
・ベンチプレス
・デッドリフト
・・・に加えて、爆発的なパワーの獲得のために
・クリーン
・・・をベースにプログラムを立てています。
<パワー改善のメニュー>
・クリーン
・ジャンプアップ
<コアリフト メニュー>
・パラレルスクワット
・デッドリフト
・ベンチプレス
<体幹メニュー>
・ダンベル・ロウ
・トランクローテーション
・サイドベンド
<肩のメニュー>
・エンプティカン
・バックプレスwithバックエクステンション
・インバーテッド・ロウ
ウエイトトレーニングは、体幹と下肢、体幹と上肢、体幹と下肢と肩甲骨周囲筋群・・・というように
一つのメニューでいろんな筋肉との協調性を図ることができるので便利です。
例えば、スクワット。下半身のトレーニングとしてベーシックなメニューですが
下げる深さによって、下半身の筋を最大限につかわざるおえない。
また、深くさげれば股関節周りの柔軟性の改善にも役立ち、重さを肩にささえることで
体幹にもしっかり圧がかかり、バランスを取る必要がでてきます。

しっかりと意図をつたえて、十分深くさげてもらうパラレルスクワット(太ももと床が平行になる角度)またはそれ以下のディープスクワットに挑戦するように伝えていますが・・・まあ、なかなか伝わらないのは、「個々のトレーニングに対する意識」の問題です。
負けずにしつこく、伝えます(笑)。

クリーン。膝下からバーを、爆発的に引き上げる。ジャンプ力改善のパワートレーニング。

デッドリフト。バレーボールはこの姿勢がキープできることで大きくパフォーマンスに生かされます。

ベンチプレス。だいぶ意識して重さにチャレンジするように。女子選手で差がつくメニューの一つ。

インバーテッド・ロウ。意外と「引く」動作は重要です。懸垂の準備段階として。
もっと胸に引き寄せてほしかった。使い方が下手な例になってしまいました・・・(笑)

バックプレスとバックエクステンションを同時に行っています。体幹と肩回りの協調性を図ります。
基本的に、トレーニングはなんでもやってみればいい、と思います。
まずは、やってみることです。
いっぱい試行錯誤してきましたが、今はこれで落ち着いてる感じです。
「いや、もっとこうした方がいいかもしれない」
と、常に考えて工夫していきたいと思います。
グリーンスムージーからちょっとハマって、小松菜とオレンジ、バナナはおススメです。
今日はちょっと腐れかけたバナナとグアバと牛乳でつくりました。種はあるけど美味しいです。
本日は7時半からの練習。
練習後にウエイトトレーニングをやりました。
今年のチームは早い段階から導入できたので、夏休みも週2回やってきました。
変化をつけるために「高重量の日」と「低重量の日」に設定しています。
9月から、シーズンの変わり目を期にメニューと負荷を変えています。
スペースと器具と時間の関係で、沢山のメニューを行うことはできませんが
「ビッグⅢ」と呼ばれる
・スクワット
・ベンチプレス
・デッドリフト
・・・に加えて、爆発的なパワーの獲得のために
・クリーン
・・・をベースにプログラムを立てています。
<パワー改善のメニュー>
・クリーン
・ジャンプアップ
<コアリフト メニュー>
・パラレルスクワット
・デッドリフト
・ベンチプレス
<体幹メニュー>
・ダンベル・ロウ
・トランクローテーション
・サイドベンド
<肩のメニュー>
・エンプティカン
・バックプレスwithバックエクステンション
・インバーテッド・ロウ
ウエイトトレーニングは、体幹と下肢、体幹と上肢、体幹と下肢と肩甲骨周囲筋群・・・というように
一つのメニューでいろんな筋肉との協調性を図ることができるので便利です。
例えば、スクワット。下半身のトレーニングとしてベーシックなメニューですが
下げる深さによって、下半身の筋を最大限につかわざるおえない。
また、深くさげれば股関節周りの柔軟性の改善にも役立ち、重さを肩にささえることで
体幹にもしっかり圧がかかり、バランスを取る必要がでてきます。

しっかりと意図をつたえて、十分深くさげてもらうパラレルスクワット(太ももと床が平行になる角度)またはそれ以下のディープスクワットに挑戦するように伝えていますが・・・まあ、なかなか伝わらないのは、「個々のトレーニングに対する意識」の問題です。
負けずにしつこく、伝えます(笑)。

クリーン。膝下からバーを、爆発的に引き上げる。ジャンプ力改善のパワートレーニング。

デッドリフト。バレーボールはこの姿勢がキープできることで大きくパフォーマンスに生かされます。

ベンチプレス。だいぶ意識して重さにチャレンジするように。女子選手で差がつくメニューの一つ。

インバーテッド・ロウ。意外と「引く」動作は重要です。懸垂の準備段階として。
もっと胸に引き寄せてほしかった。使い方が下手な例になってしまいました・・・(笑)

バックプレスとバックエクステンションを同時に行っています。体幹と肩回りの協調性を図ります。
基本的に、トレーニングはなんでもやってみればいい、と思います。
まずは、やってみることです。
いっぱい試行錯誤してきましたが、今はこれで落ち着いてる感じです。
「いや、もっとこうした方がいいかもしれない」
と、常に考えて工夫していきたいと思います。
2015年09月06日
負荷をかける
体育祭シーズンですね。
大高の体育祭を今年も観に行きました。
ムカデのスピードと応援団の気迫は圧巻ですね。高校生達の自主性によるエネルギーは素晴らしい。
今月は「フィジカルトレーニング」について
取り入れた情報と、自分の実践状況と経験と考えを踏まえて
書き込んでいきます。半分は自分の活動と考え方の整理です。
(興味ある方が「へー」と思ってもらえればいいかな。)
まず、根本的な私のフィジカルトレーニングに対する考え方。
フィジカル(身体)トレーニングは「負荷」をかけないと意味がありません。
自分のカラダを追い込んで、追い込んで、追い込んでこそ・・・成長できると思っています。
かといって、急にハードトレーニングをさせても、これこそ無意味です。
だから、まずは「自分の体重をコントロールできるか」が負荷をどれくらいかけるかの最初のチェックになります。
体力測定も然りです。これは個々の現状を他者と比較しつつ、成長を数値で表し、トレーニング効果を可視化するためのものです。
指導者が毎日きちんと選手を観察できていれば、粗方その数字は納得できるものになるはずです。
負荷は自体重のみでも、動作コントロールが「きちんと」できれば、十分変化がみられます(注:大半は間違った動きに気づく事なく、サボっています)。
チームのトレーニングを担当していますが、私の中ではまだまだ半分くらいしか、させきれていません。
大事なことですが、本当に自分が成長するには、個々のモチベーションの高さが必要だと思っています。
これは、こちらからいくら要求しても、ほぼ伝わりません。
やらせることもできますが、「強制」はサボりにすぐ繋がります。
まだまだ、フィジカルトレーニングの必要性を選手に伝えきれていないのだと思います。私の責任もあります。
あとは、目指すべき目標やイメージが明確でないのでしょう。ここを伝えるには実際、試合をこなして、自分達の実力を目の当たりにしないと難しいかも。もう少し時間が必要です。
そういう状況の中でも、「負荷をかける」ことは可能な範囲で行うべきだと思います。
選手は素直です。言われた事はやります。だから、知らない間に身体は負荷に耐え得る能力を身につける。パフォーマンスも時間かければ上手くなります。
ただ、「やらされているトレーニングは面白くないだろうな」と思います…
「人間は自分に出来ないと思う事、上手くやれないと思う事はやらない」
…習性があるようなので、やはり待つしかないな、と思うのです。
応援団のように…自主性ある部活動に。
自分で上手くなるための工夫し、「負荷」をかけられるような選手が現れるのを楽しみにしながら…
「フィジカルトレーニング」の必要性を伝えて、実際に形として残していきたいと思います。
これも一つ私の「負荷」として、チャレンジしたいと思います。
大高の体育祭を今年も観に行きました。
ムカデのスピードと応援団の気迫は圧巻ですね。高校生達の自主性によるエネルギーは素晴らしい。
今月は「フィジカルトレーニング」について
取り入れた情報と、自分の実践状況と経験と考えを踏まえて
書き込んでいきます。半分は自分の活動と考え方の整理です。
(興味ある方が「へー」と思ってもらえればいいかな。)
まず、根本的な私のフィジカルトレーニングに対する考え方。
フィジカル(身体)トレーニングは「負荷」をかけないと意味がありません。
自分のカラダを追い込んで、追い込んで、追い込んでこそ・・・成長できると思っています。
かといって、急にハードトレーニングをさせても、これこそ無意味です。
だから、まずは「自分の体重をコントロールできるか」が負荷をどれくらいかけるかの最初のチェックになります。
体力測定も然りです。これは個々の現状を他者と比較しつつ、成長を数値で表し、トレーニング効果を可視化するためのものです。
指導者が毎日きちんと選手を観察できていれば、粗方その数字は納得できるものになるはずです。
負荷は自体重のみでも、動作コントロールが「きちんと」できれば、十分変化がみられます(注:大半は間違った動きに気づく事なく、サボっています)。
チームのトレーニングを担当していますが、私の中ではまだまだ半分くらいしか、させきれていません。
大事なことですが、本当に自分が成長するには、個々のモチベーションの高さが必要だと思っています。
これは、こちらからいくら要求しても、ほぼ伝わりません。
やらせることもできますが、「強制」はサボりにすぐ繋がります。
まだまだ、フィジカルトレーニングの必要性を選手に伝えきれていないのだと思います。私の責任もあります。
あとは、目指すべき目標やイメージが明確でないのでしょう。ここを伝えるには実際、試合をこなして、自分達の実力を目の当たりにしないと難しいかも。もう少し時間が必要です。
そういう状況の中でも、「負荷をかける」ことは可能な範囲で行うべきだと思います。
選手は素直です。言われた事はやります。だから、知らない間に身体は負荷に耐え得る能力を身につける。パフォーマンスも時間かければ上手くなります。
ただ、「やらされているトレーニングは面白くないだろうな」と思います…
「人間は自分に出来ないと思う事、上手くやれないと思う事はやらない」
…習性があるようなので、やはり待つしかないな、と思うのです。
応援団のように…自主性ある部活動に。
自分で上手くなるための工夫し、「負荷」をかけられるような選手が現れるのを楽しみにしながら…
「フィジカルトレーニング」の必要性を伝えて、実際に形として残していきたいと思います。
これも一つ私の「負荷」として、チャレンジしたいと思います。
2015年09月04日
「体力」をつけるには?part2
昨日のチームのトレーニング。
久々の5km走。雨の中頑張っていたようです。
「体力」とは「体力要素」の総称であり、体力要素とは
・スピード
・アジリティ(方向転換能力)
・パワー(ジャンプなど爆発的な運動)
・筋力
・柔軟性
…など細かくわけられます。
学校で行う体力測定のような感じですね。
トレーニングを行うという事は、必ずそこに「目的」があります。
1番に掲げるべき目的は
「パフォーマンスの向上」
です。
先週、講習をした「体幹トレーニング」も
最終的には、「選手のパフォーマンスにどう繋げていくのか?」ということが大事だと思います。
すでにトレーニング導入前の段階で必要性の分析は出来ています。
バレーボール競技で最も重要な「体力」は「パワー」です。
「パワー」と聞いて、何が思い浮かびますか?
恐らく大半の方は「ボールをたたく力」「ボールのスピード」とイメージされるでしょう。
「パワー」の要素には
ジャンプや、短い距離、停止状態からの爆発的なスタートも含まれます。
「パワーをつける」には筋力が必要です。
「パワーをつける」には体幹(コア)の安定性がさらに必要です。
「パワーをつける」にはスピードが必要です。
さて、「パワー」という「体力」をつけるには、どうしたらいいのでしょうね・・・
何から、始めましょうか・・・
・・・・。
・・・というのを、考えて、実践して、反省して、時に失敗して、勉強して、継続していく地味な仕事が
私たちトレーナーの役割なのだと思います。
だから「走らせる」事、一つにしても、私は悩むのです。
人間のエネルギーシステムや、筋肉の構造、タイプ・・・科学的な事を知れば知るほど、
悩むのです。
が・・・
監督の一言でふっきれました。
「たかだか週1回の10kmくらい、走りきれるくらいの体力(ベース)がないとダメでしょ。」
あ、そうだね・・・週1回くらいじゃ、身体はそんなに適応は示さないか・・・
それ以上に、パワー系のトレーニングをやっているわけだから。
これも「トレーニングの目的」の一つの見解です。
1人で考え込むと、視野が狭くなりますね・・・
「体力」をつけるには?
科学的なデータはあっても、最終的にはトレーニングを行う選手のレベルに応じます。
そして、プログラムを実施させていて強く思うのは、
内容云々を考えるよりも難しいこと。
個人の「うまくなりたい・強くなりたい」という
目標と想いを、どう引き上げるか、です・・・(やっぱり)。
久々の5km走。雨の中頑張っていたようです。
「体力」とは「体力要素」の総称であり、体力要素とは
・スピード
・アジリティ(方向転換能力)
・パワー(ジャンプなど爆発的な運動)
・筋力
・柔軟性
…など細かくわけられます。
学校で行う体力測定のような感じですね。
トレーニングを行うという事は、必ずそこに「目的」があります。
1番に掲げるべき目的は
「パフォーマンスの向上」
です。
先週、講習をした「体幹トレーニング」も
最終的には、「選手のパフォーマンスにどう繋げていくのか?」ということが大事だと思います。
すでにトレーニング導入前の段階で必要性の分析は出来ています。
バレーボール競技で最も重要な「体力」は「パワー」です。
「パワー」と聞いて、何が思い浮かびますか?
恐らく大半の方は「ボールをたたく力」「ボールのスピード」とイメージされるでしょう。
「パワー」の要素には
ジャンプや、短い距離、停止状態からの爆発的なスタートも含まれます。
「パワーをつける」には筋力が必要です。
「パワーをつける」には体幹(コア)の安定性がさらに必要です。
「パワーをつける」にはスピードが必要です。
さて、「パワー」という「体力」をつけるには、どうしたらいいのでしょうね・・・
何から、始めましょうか・・・
・・・・。
・・・というのを、考えて、実践して、反省して、時に失敗して、勉強して、継続していく地味な仕事が
私たちトレーナーの役割なのだと思います。
だから「走らせる」事、一つにしても、私は悩むのです。
人間のエネルギーシステムや、筋肉の構造、タイプ・・・科学的な事を知れば知るほど、
悩むのです。
が・・・
監督の一言でふっきれました。
「たかだか週1回の10kmくらい、走りきれるくらいの体力(ベース)がないとダメでしょ。」
あ、そうだね・・・週1回くらいじゃ、身体はそんなに適応は示さないか・・・
それ以上に、パワー系のトレーニングをやっているわけだから。
これも「トレーニングの目的」の一つの見解です。
1人で考え込むと、視野が狭くなりますね・・・
「体力」をつけるには?
科学的なデータはあっても、最終的にはトレーニングを行う選手のレベルに応じます。
そして、プログラムを実施させていて強く思うのは、
内容云々を考えるよりも難しいこと。
個人の「うまくなりたい・強くなりたい」という
目標と想いを、どう引き上げるか、です・・・(やっぱり)。
2015年09月03日
「体力」をつけるには?
今日も、書きます。今日は久々「トレーニング」についてです。
「体力」といえば、何が思い浮かびますか?
「体力をつける」と聞いて、どんな手段が思い浮かびますか?
恐らく、半数以上の人は
「走る」
「長い距離を走れる体力」
「長い時間走れると体力がつく」
私も、そう信じてきた人間です。
そして、「体力をつけろ!」と言われるたびに、走らされてきた1人です。
専門用語言えば『最大酸素摂取量(Vo2max)』が高まれば、長時間プレーすることや疲労からより早く回復することが可能になる、という考え方です。
(*最大酸素摂取量・・・全身の細胞レベルで利用することが出来る酸素量の最大値)
最近、トレーニングプログラムを立てる中で私の迷いは、この
「走る」
ということでした。
現在プログラムを立てている種目は「バレーボール」のみですが、
バレーボールという競技は、ジャンプや方向転換の能力(パワー)、スピードの要素が求められる競技です。
プログラムを立てる上で、考えなければならないポイントは
「スポーツの特異性」
です。
どういう意味かといいますと、
バレーボールの試合中、ずっと同じペースで走り続けるような場面はない、ということです。
いわゆる「体力=走る」というセオリーは当てはまらない競技、ということになります。
しかもチームスポーツのほとんどすべては「スピード」と「パワー」が要求されます。
以下は文献でよく目にする文言です。
-パワー系選手の有酸素トレーニングを実施すると、結果的に『最大酸素摂取量』は高まったが、パフォーマンスには変化がみられなかった。
-「サッカー選手は1試合で約10km走る」「テニスの試合は2時間以上続く」のだから、より早い回復には有酸素系システム(長く運動を続ける機能)が重要だ。
続けて、こう述べてあります。
-しかし、このようなことは問題ではない。問題なのは、どのくらいのスピードで、どのくらいの時間で、である。テニスの試合では約2時間プレーしているが、そのうちスプリント(ダッシュ)と休息の比率はどのくらいだろうか。
もう一つ、よく目にする文言ですが・・・
-持久性トレーニングに集中しすぎると、スピードの発達に悪影響を及ぼす可能性があることも考慮しなければならない。逆をとれば、スプリンターを長距離選手にするのは簡単だともいえる。
そうなんですよ・・・
身体、というのは適応するからトレーニングの効果が反映されるわけで、
いくら「体力をつける」ために長い距離を走れるようになったとしても、
競技特異性からみれば、
昔から言われていた「長い距離を走れる体力」は
バレーボールやサッカー、テニスやバドミントンなどの技術改善にはならない、わけです。
当然といえば、当然です。
では、それでもやっぱり「走る」トレーニングをチーム取り入れるべきと思っている・・・
しかも、「長距離走」です。
そこには、「トレーニングの目的」が関係します。
長くなりそうなので、また続きは明日書く事にします。。
「体力」といえば、何が思い浮かびますか?
「体力をつける」と聞いて、どんな手段が思い浮かびますか?
恐らく、半数以上の人は
「走る」
「長い距離を走れる体力」
「長い時間走れると体力がつく」
私も、そう信じてきた人間です。
そして、「体力をつけろ!」と言われるたびに、走らされてきた1人です。
専門用語言えば『最大酸素摂取量(Vo2max)』が高まれば、長時間プレーすることや疲労からより早く回復することが可能になる、という考え方です。
(*最大酸素摂取量・・・全身の細胞レベルで利用することが出来る酸素量の最大値)
最近、トレーニングプログラムを立てる中で私の迷いは、この
「走る」
ということでした。
現在プログラムを立てている種目は「バレーボール」のみですが、
バレーボールという競技は、ジャンプや方向転換の能力(パワー)、スピードの要素が求められる競技です。
プログラムを立てる上で、考えなければならないポイントは
「スポーツの特異性」
です。
どういう意味かといいますと、
バレーボールの試合中、ずっと同じペースで走り続けるような場面はない、ということです。
いわゆる「体力=走る」というセオリーは当てはまらない競技、ということになります。
しかもチームスポーツのほとんどすべては「スピード」と「パワー」が要求されます。
以下は文献でよく目にする文言です。
-パワー系選手の有酸素トレーニングを実施すると、結果的に『最大酸素摂取量』は高まったが、パフォーマンスには変化がみられなかった。
-「サッカー選手は1試合で約10km走る」「テニスの試合は2時間以上続く」のだから、より早い回復には有酸素系システム(長く運動を続ける機能)が重要だ。
続けて、こう述べてあります。
-しかし、このようなことは問題ではない。問題なのは、どのくらいのスピードで、どのくらいの時間で、である。テニスの試合では約2時間プレーしているが、そのうちスプリント(ダッシュ)と休息の比率はどのくらいだろうか。
もう一つ、よく目にする文言ですが・・・
-持久性トレーニングに集中しすぎると、スピードの発達に悪影響を及ぼす可能性があることも考慮しなければならない。逆をとれば、スプリンターを長距離選手にするのは簡単だともいえる。
そうなんですよ・・・
身体、というのは適応するからトレーニングの効果が反映されるわけで、
いくら「体力をつける」ために長い距離を走れるようになったとしても、
競技特異性からみれば、
昔から言われていた「長い距離を走れる体力」は
バレーボールやサッカー、テニスやバドミントンなどの技術改善にはならない、わけです。
当然といえば、当然です。
では、それでもやっぱり「走る」トレーニングをチーム取り入れるべきと思っている・・・
しかも、「長距離走」です。
そこには、「トレーニングの目的」が関係します。
長くなりそうなので、また続きは明日書く事にします。。
2015年09月02日
ASAスポーツ講習会
8月29日に行った「ASAスポーツ講習会」の報告です。
約30名の受講者のみなさん、暑い中ありがとうございました。

今回のテーマは「体幹トレーニング」でした。
最近よく耳にする「体幹」や「コア」という言葉・・・
その違いや、「体幹トレーニング」の本質的なことを解説したうえで
皆さんとトレーニング!
イメージは「腹筋・背筋」でしょうけれど・・・
根本的に、体幹を強化したうえで、
・上肢と下肢の動作をいかにコントロールしていくか?
・動作の安定性をどう身につけるか?
・・・というのが本来、体幹トレーニングを取り入れる上で大切な事だと思います。
デッドリフト・スクワット・・・このような『体幹と下肢』をどう連動させて動作を作っていくか?
正しいフォームで動作を行うことで、全身の筋を効率よく使う。
この繰り返しを行うことで、「体幹トレーニング」が本来の意味をなすのだと思います。
受講者の皆さんには・・・いろんな目的をもって講習に参加してくださったわけですが、
「自分のカラダを自分の思うようにコントロールする」
という事を、実技目標にかがげて、取り組んでもらいました。
実技前の動きに比べて、少し身体も軽く感じてくださったでしょうか?
1度では効果はありませんが、それぞれの感覚を大事に、取り組んで下さるとありがたいです。
次回の内容は、まだ決めていませんが・・・
「こんな事、知っておきたい!」という内容があればコメントに依頼頂けると助かります。
もっと、「スポーツとケガ」についてお知らせしても興味深いのかな?と思ったりします。
予防策を知るのが一番、と個人的には思うのですが
現場では、予防より「対処」の方が、ニーズが高いのかもしれませんね。。。
約30名の受講者のみなさん、暑い中ありがとうございました。

今回のテーマは「体幹トレーニング」でした。
最近よく耳にする「体幹」や「コア」という言葉・・・
その違いや、「体幹トレーニング」の本質的なことを解説したうえで
皆さんとトレーニング!
イメージは「腹筋・背筋」でしょうけれど・・・
根本的に、体幹を強化したうえで、
・上肢と下肢の動作をいかにコントロールしていくか?
・動作の安定性をどう身につけるか?
・・・というのが本来、体幹トレーニングを取り入れる上で大切な事だと思います。
デッドリフト・スクワット・・・このような『体幹と下肢』をどう連動させて動作を作っていくか?
正しいフォームで動作を行うことで、全身の筋を効率よく使う。
この繰り返しを行うことで、「体幹トレーニング」が本来の意味をなすのだと思います。
受講者の皆さんには・・・いろんな目的をもって講習に参加してくださったわけですが、
「自分のカラダを自分の思うようにコントロールする」
という事を、実技目標にかがげて、取り組んでもらいました。
実技前の動きに比べて、少し身体も軽く感じてくださったでしょうか?
1度では効果はありませんが、それぞれの感覚を大事に、取り組んで下さるとありがたいです。
次回の内容は、まだ決めていませんが・・・
「こんな事、知っておきたい!」という内容があればコメントに依頼頂けると助かります。
もっと、「スポーツとケガ」についてお知らせしても興味深いのかな?と思ったりします。
予防策を知るのが一番、と個人的には思うのですが
現場では、予防より「対処」の方が、ニーズが高いのかもしれませんね。。。
2015年06月07日
中学生の部活動でのストレッチング指導
昨日は朝日中にて、
男女バスケットボール部へストレッチングの指導をしました(^^)



学校の部活動で、直接、練習現場で指導するのは(ウチのチーム以外では)稀な活動です。そしてバスケット部の指導は初めて!
普段、バレーの現場で活動している事が多いのですが、競技が違えばウォームアップの取り入れ方や内容の違い、雰囲気も違います。
でも、アップの内容や構成が本当にしっかりしていて、かなり先生ご自身が勉強されているんだなぁ…という実感。
お話聞いていると…思い出しました!バスケットボールは指導者育成のシステムが確立されているので、アップやストレッチングに関してもトップから降りてくるモノを導入されているんですよね。。
観ているこちらも勉強になりました!
メニューは豊富ですが、個々それぞれ同じメニューのはずなのに、動きが違う。
これが何故なのか、どう改善していくのかを分析して、アドバイスしていくのが、私の仕事、という事になります。
今回は、「講習会」では絶対出来ない面白い時間でした。普段の練習の流れに順次ながら、いつもやっているストレッチングのフォーム指導や、ポイントを伝えたり…
先生が以前から気になってらっしゃった、時間の使い方の部分で、「この隙間の時間がもったいないので、何かストレッチングをさせたいんです」と目的をしっかり伝えて下さったので、実際のその時間に合わせて、その中で子供達にいろいろさせてみました。
私は入れ替わり立ち代り目の前にいる子供達に…目が回りましたが(笑)
最初は身体の使い方が分からなくて、悲鳴を上げていた子供達も…
さすが、中学生!習得が早い!
あちこちで、「出来た!」との声。嬉しいよね、出来なかった事が出来るようになるって。私もその笑顔は、嬉しい(^^)
身体が硬い、と思っていた子も、
身体の使い方一つで、どんどん身体が思うように動いていきます。
それが、バスケとどう繋がるか…までを観察する余裕は、今回なかったなぁ。
やはり個々で少しづつ伝えたいポイントや言葉の選択が違う…けどタイムオーバー!
最後は保護者や先生方も一緒に、クールダウンの指導とケアを兼ねたストレッチングの提供をさせていただきました。
先生方や、保護者の方々が日頃、少し疑問に思ってらっしゃった事などにも、お話しながらお答え出来たのかな?と。。
やはり、人間ですから…時間を共に過ごして、少しづつお互いを理解する所から、私の仕事は始まります。
いい出会いに感謝して、またチャンスがあればさらにイイものをお伝え出来たらなぁ、と思いました。
男女バスケットボール部へストレッチングの指導をしました(^^)



学校の部活動で、直接、練習現場で指導するのは(ウチのチーム以外では)稀な活動です。そしてバスケット部の指導は初めて!
普段、バレーの現場で活動している事が多いのですが、競技が違えばウォームアップの取り入れ方や内容の違い、雰囲気も違います。
でも、アップの内容や構成が本当にしっかりしていて、かなり先生ご自身が勉強されているんだなぁ…という実感。
お話聞いていると…思い出しました!バスケットボールは指導者育成のシステムが確立されているので、アップやストレッチングに関してもトップから降りてくるモノを導入されているんですよね。。
観ているこちらも勉強になりました!
メニューは豊富ですが、個々それぞれ同じメニューのはずなのに、動きが違う。
これが何故なのか、どう改善していくのかを分析して、アドバイスしていくのが、私の仕事、という事になります。
今回は、「講習会」では絶対出来ない面白い時間でした。普段の練習の流れに順次ながら、いつもやっているストレッチングのフォーム指導や、ポイントを伝えたり…
先生が以前から気になってらっしゃった、時間の使い方の部分で、「この隙間の時間がもったいないので、何かストレッチングをさせたいんです」と目的をしっかり伝えて下さったので、実際のその時間に合わせて、その中で子供達にいろいろさせてみました。
私は入れ替わり立ち代り目の前にいる子供達に…目が回りましたが(笑)
最初は身体の使い方が分からなくて、悲鳴を上げていた子供達も…
さすが、中学生!習得が早い!
あちこちで、「出来た!」との声。嬉しいよね、出来なかった事が出来るようになるって。私もその笑顔は、嬉しい(^^)
身体が硬い、と思っていた子も、
身体の使い方一つで、どんどん身体が思うように動いていきます。
それが、バスケとどう繋がるか…までを観察する余裕は、今回なかったなぁ。
やはり個々で少しづつ伝えたいポイントや言葉の選択が違う…けどタイムオーバー!
最後は保護者や先生方も一緒に、クールダウンの指導とケアを兼ねたストレッチングの提供をさせていただきました。
先生方や、保護者の方々が日頃、少し疑問に思ってらっしゃった事などにも、お話しながらお答え出来たのかな?と。。
やはり、人間ですから…時間を共に過ごして、少しづつお互いを理解する所から、私の仕事は始まります。
いい出会いに感謝して、またチャンスがあればさらにイイものをお伝え出来たらなぁ、と思いました。
2015年05月25日
自分の身は、自分で守る
昨日、資格の継続研修を鹿児島で受けてきました。
日本赤十字社の救急法救急員の資格です。
この資格を初めて取得したのは、おそらく2000年。
日赤の資格は3年間有効。奇しくも更新は5回目、ということになります。
確か、この年のNSCA-CPT(NSCA公認パーソナルトレーナー)の受験をするのにCPR(心肺蘇生法)の資格保持が必須で、
受講したのがきっかけだと思います。
ここ数年で、継続研修が資格有効期間内ならば1日で終わるシステムになったため、
今回も、1日でめでたく資格を更新することができました。
トレーナーだから、という理由でこの資格を保持してきましたが、
最近の大災害や、先日の地震のことを思うと、
スポーツ現場だけでなく、もしかしたら自然災害などでも必要とされる知識なのでは?と
今回受講しながら思いました。
鹿児島県は、今年度から防災強化県として今後、学校関係で防災についての勉強会が行われる、と
指導員の方が言われていました。
火山や地震が多いからです。
そこで
「自助」「共助」「公助」
という言葉を掲げられていました。
東北の災害で、亡くなられた方の90%は即死だったといいます。
うち、生き残られた方の95%は「自助」と「共助」で生き延びられたとそうです。
自力でどうにか乗り切るか、周りの協力を得られて生き延びることができた。
「公助」、つまり消防や自衛隊など国の助けで生きられた方はたった5%。
県や国の助けを待っていたのでは、遅い、というデータが最近ようやく上がってきた、とのこと。
どういうことを意味するのか?
要するに、災害発生時は、「自分の身は、自分で守る」という事、だそうです。
それは、こういう知識を身につけておくことかもしれないし、
過信せず、早めに避難することかもしれないし、
日頃から体力をつけておくことかもしれないし、
その時が起こらないとわからないことなのかもしれないのですが、
「災害に対する意識を、もっと各自がもっておく」ということは今すぐできることなのかもしれません。
スポーツの現場についても、同様のことを思います。
ケガが起きない方がいい、予防が完璧にできれば問題ないのですが、
まず、絶対起こらないということは、ありえません。
スポーツ現場は、「ケガも起こりうる」ということを前提として、
大人は最低限の知識と技術を持っておくべきだと、
私は講習会の場で訴えます。
ケガや痛みに関しても、
必ず、痛みがひどくなる前には「サイン」が出ます。
疲れて、身体が疲労している状態でも「サイン」が出ます。
日頃から、その「サイン」に気づけるかどうかもやはり大事。
でも、その「サイン」に気づいても、訴えることができない環境、
頼る場所がわからないという現状は
日本のスポーツ界の、まだまだ大きな問題です。
でも、ケガの予防に対する意識を日頃から持っておけるかどうかで、
やはり選択肢は準備できるのではないでしょうか?
「自分の身は、自分で守る」
「生きる力」じゃないですけど、
やはり、スポーツ選手もスポーツが出来るだけでなく、
きちんと自己管理できる選手に育ててあげたいと思います。
日本赤十字社の救急法救急員の資格です。
この資格を初めて取得したのは、おそらく2000年。
日赤の資格は3年間有効。奇しくも更新は5回目、ということになります。
確か、この年のNSCA-CPT(NSCA公認パーソナルトレーナー)の受験をするのにCPR(心肺蘇生法)の資格保持が必須で、
受講したのがきっかけだと思います。
ここ数年で、継続研修が資格有効期間内ならば1日で終わるシステムになったため、
今回も、1日でめでたく資格を更新することができました。
トレーナーだから、という理由でこの資格を保持してきましたが、
最近の大災害や、先日の地震のことを思うと、
スポーツ現場だけでなく、もしかしたら自然災害などでも必要とされる知識なのでは?と
今回受講しながら思いました。
鹿児島県は、今年度から防災強化県として今後、学校関係で防災についての勉強会が行われる、と
指導員の方が言われていました。
火山や地震が多いからです。
そこで
「自助」「共助」「公助」
という言葉を掲げられていました。
東北の災害で、亡くなられた方の90%は即死だったといいます。
うち、生き残られた方の95%は「自助」と「共助」で生き延びられたとそうです。
自力でどうにか乗り切るか、周りの協力を得られて生き延びることができた。
「公助」、つまり消防や自衛隊など国の助けで生きられた方はたった5%。
県や国の助けを待っていたのでは、遅い、というデータが最近ようやく上がってきた、とのこと。
どういうことを意味するのか?
要するに、災害発生時は、「自分の身は、自分で守る」という事、だそうです。
それは、こういう知識を身につけておくことかもしれないし、
過信せず、早めに避難することかもしれないし、
日頃から体力をつけておくことかもしれないし、
その時が起こらないとわからないことなのかもしれないのですが、
「災害に対する意識を、もっと各自がもっておく」ということは今すぐできることなのかもしれません。
スポーツの現場についても、同様のことを思います。
ケガが起きない方がいい、予防が完璧にできれば問題ないのですが、
まず、絶対起こらないということは、ありえません。
スポーツ現場は、「ケガも起こりうる」ということを前提として、
大人は最低限の知識と技術を持っておくべきだと、
私は講習会の場で訴えます。
ケガや痛みに関しても、
必ず、痛みがひどくなる前には「サイン」が出ます。
疲れて、身体が疲労している状態でも「サイン」が出ます。
日頃から、その「サイン」に気づけるかどうかもやはり大事。
でも、その「サイン」に気づいても、訴えることができない環境、
頼る場所がわからないという現状は
日本のスポーツ界の、まだまだ大きな問題です。
でも、ケガの予防に対する意識を日頃から持っておけるかどうかで、
やはり選択肢は準備できるのではないでしょうか?
「自分の身は、自分で守る」
「生きる力」じゃないですけど、
やはり、スポーツ選手もスポーツが出来るだけでなく、
きちんと自己管理できる選手に育ててあげたいと思います。
2015年05月21日
競技力向上とケガ
ジュニア選手の痛みに関して、時々ご相談受けることがあります。
「捻った記憶はないけれど、練習後に足首が痛む」
「捻挫してアイシングをしたけれど、それからどうしてあげたらいいのか?」
「腰痛があるのだが、成長期の子供は整骨院などに連れて行ってもいいのか?」
「病院に連れて行った方がいいのか?整骨院などがいいのか?」
我が子が、痛みを訴える。
ささいな疑問でも、いざとなると、不安に感じたり、どう対応してあげたらいいのか、
何を選択したらいいのかわからない。
親としては、悩むところですよね。
私も、小学生の頃から、痛みを訴えて親を悩ませていた一人です。
中学生に至っては、腰痛で悩まされ、
高校でとうとう、ヘルニアの診断で入院。
なぜ、痛みが出たのかわからないけど、痛いと訴える。
「いい」と聞けば、母は私を治療に連れて行ってくれました。
今考えると・・・本当に親に迷惑かけてきたなあ・・・という思いです。
昨日は、以前からご相談を受けていたジュニア選手のもとを尋ねました。
診断は、「腰椎分離症」。いわゆる腰の骨に骨折の形跡がみられる
成長期特有のスポーツ障害の一つです。
ご連絡いただいたのは、その選手を指導されている先生から。
先生自身も、ネットで調べたり、整形外科での診断と指示に従われながら・・・
でも、「どうしたらいいのか、自分では対応できない」という判断でご相談いただいていました。
安静期間を経て、痛みもほぼ解消されていたようなので、
動作の確認をしながら、原因をみつけて、選手本人が出来る事を一緒にやってみました。
観ていて、怖かったかもしれませんね・・・今まで安静にしていた子がストレッチングでかなり身体を動かしていたので。。
でも、そのレベルで身体を動かせないと、競技でかかる負担はもっとですから・・・
痛みなく、自分のカラダをコントロールできることが大前提です。
ですが、本人も先生も「どこまで動かしていいのかわからない怖さ」があります。
ここが、競技復帰のむずかしさです。
私も、昨日の指導だけで、本人に伝わっているとは思わないし、
これから長い目で動作の確認をしていかないと、再発の可能性もあります。
どこまでそのことをお伝えできたかわかりませんが・・・
せっかくのご縁なので、遠慮なく呼んでもらえたらいいなと思います。
先生が呟かれた一言が心に響きました。
「いい能力を持った選手だと思うんですよ、でも私が焦っていたのでしょうね、こんな事になってしまって本当に申し訳なくて。」
素直な思いを、伝えて頂いて
競技力向上と健康のバランスの難しさを改めて感じます。
その為に、私達トレーナーという役割がいるのですが、まだまだそのように認識して頂くには活動や実績が足りないのでしょうね。。。黒子の立場なので決して目立ちはしないのですが、担う役割は大きいです。
どう、認識を広めようかなぁ…
地道にコツコツ、やるしかないですね!
「捻った記憶はないけれど、練習後に足首が痛む」
「捻挫してアイシングをしたけれど、それからどうしてあげたらいいのか?」
「腰痛があるのだが、成長期の子供は整骨院などに連れて行ってもいいのか?」
「病院に連れて行った方がいいのか?整骨院などがいいのか?」
我が子が、痛みを訴える。
ささいな疑問でも、いざとなると、不安に感じたり、どう対応してあげたらいいのか、
何を選択したらいいのかわからない。
親としては、悩むところですよね。
私も、小学生の頃から、痛みを訴えて親を悩ませていた一人です。
中学生に至っては、腰痛で悩まされ、
高校でとうとう、ヘルニアの診断で入院。
なぜ、痛みが出たのかわからないけど、痛いと訴える。
「いい」と聞けば、母は私を治療に連れて行ってくれました。
今考えると・・・本当に親に迷惑かけてきたなあ・・・という思いです。
昨日は、以前からご相談を受けていたジュニア選手のもとを尋ねました。
診断は、「腰椎分離症」。いわゆる腰の骨に骨折の形跡がみられる
成長期特有のスポーツ障害の一つです。
ご連絡いただいたのは、その選手を指導されている先生から。
先生自身も、ネットで調べたり、整形外科での診断と指示に従われながら・・・
でも、「どうしたらいいのか、自分では対応できない」という判断でご相談いただいていました。
安静期間を経て、痛みもほぼ解消されていたようなので、
動作の確認をしながら、原因をみつけて、選手本人が出来る事を一緒にやってみました。
観ていて、怖かったかもしれませんね・・・今まで安静にしていた子がストレッチングでかなり身体を動かしていたので。。
でも、そのレベルで身体を動かせないと、競技でかかる負担はもっとですから・・・
痛みなく、自分のカラダをコントロールできることが大前提です。
ですが、本人も先生も「どこまで動かしていいのかわからない怖さ」があります。
ここが、競技復帰のむずかしさです。
私も、昨日の指導だけで、本人に伝わっているとは思わないし、
これから長い目で動作の確認をしていかないと、再発の可能性もあります。
どこまでそのことをお伝えできたかわかりませんが・・・
せっかくのご縁なので、遠慮なく呼んでもらえたらいいなと思います。
先生が呟かれた一言が心に響きました。
「いい能力を持った選手だと思うんですよ、でも私が焦っていたのでしょうね、こんな事になってしまって本当に申し訳なくて。」
素直な思いを、伝えて頂いて
競技力向上と健康のバランスの難しさを改めて感じます。
その為に、私達トレーナーという役割がいるのですが、まだまだそのように認識して頂くには活動や実績が足りないのでしょうね。。。黒子の立場なので決して目立ちはしないのですが、担う役割は大きいです。
どう、認識を広めようかなぁ…
地道にコツコツ、やるしかないですね!
2015年05月11日
柔軟性と筋力のバランス
深く選手のカラダと付き合っていくと、最終的にはこの問題は非常に重要です。
「身体が硬いとケガをしやすい」
何をもって「硬い」とするか・・・ですが、
股関節の可動域が狭い、もしくは上手な股関節の動かし方を身体が知らない人は確かに痛みが出てきやすいです。
硬くても、適度な運動量ならば、問題はありませんが
無理がたたって、あちこちに痛みを抱える選手は少なくありません。
ですが、関節の硬さは筋力不足を補う「安定性」の確保の役割も果たします。
逆に関節の柔らかい人は、「安定性」が欠けるので、筋力がないと身体の負担も大きくなります。
つまり、身体が硬いから・・・といってストレッチングばかりやって柔軟性を高めすぎても
もともと備わっている筋力がなければ、「力が入らない」状態が起きる可能性があります。
とはいえ、一般的なストレッチングでは急激に柔軟性が高くなることはまずありません。
日々の積み重ねで可動域を高めながら、技術練習の幅を広げて、めいいっぱい身体を使う。
その刺激が、筋力強化にも繋がり、最終的にバランスよく柔軟性と筋力が高められるのかもしれません。
GW4日間、チーム帯同して選手のカラダの変化をみてきました。
ホント、人は「生もの」です。負荷のかかり方でどんどん変化していきます。
ですが、日々の積み重ね、トレーニングの効果は、少々のことでは崩れません。
周りの評価と、選手の評価と、自分の観る目がきちんと一致するような仕事は当たり前で
さらに、その先選手を、どのように成長させられるか布石を置けるような仕事が出来るように
精進していきたいと思うところです。
「身体が硬いとケガをしやすい」
何をもって「硬い」とするか・・・ですが、
股関節の可動域が狭い、もしくは上手な股関節の動かし方を身体が知らない人は確かに痛みが出てきやすいです。
硬くても、適度な運動量ならば、問題はありませんが
無理がたたって、あちこちに痛みを抱える選手は少なくありません。
ですが、関節の硬さは筋力不足を補う「安定性」の確保の役割も果たします。
逆に関節の柔らかい人は、「安定性」が欠けるので、筋力がないと身体の負担も大きくなります。
つまり、身体が硬いから・・・といってストレッチングばかりやって柔軟性を高めすぎても
もともと備わっている筋力がなければ、「力が入らない」状態が起きる可能性があります。
とはいえ、一般的なストレッチングでは急激に柔軟性が高くなることはまずありません。
日々の積み重ねで可動域を高めながら、技術練習の幅を広げて、めいいっぱい身体を使う。
その刺激が、筋力強化にも繋がり、最終的にバランスよく柔軟性と筋力が高められるのかもしれません。
GW4日間、チーム帯同して選手のカラダの変化をみてきました。
ホント、人は「生もの」です。負荷のかかり方でどんどん変化していきます。
ですが、日々の積み重ね、トレーニングの効果は、少々のことでは崩れません。
周りの評価と、選手の評価と、自分の観る目がきちんと一致するような仕事は当たり前で
さらに、その先選手を、どのように成長させられるか布石を置けるような仕事が出来るように
精進していきたいと思うところです。
2015年04月25日
エビデンス(根拠)を基に…
「根拠?なんだっけ?エビデンスっいうの?
初めて聞いた言葉だったけど、これって大切な事だなぁ、って思ったよ!」
昨日、講師を担当した「スポーツ指導者研修会」の講話の後の懇親会で、頂いた言葉でした。

最近、トレーニング界でも頻繁に耳にするのが「エビデンスに基づいた実践指導を」という文言。
講習をするにあたり、やはり自分の考えは二の次で、研究文献などで発表されているデータを基に内容を構成していくわけですが、
数ある文献から引用する言葉を選択のは、発表者自身であって、
やはりそこには、発表者の経験だったり、発見だったり、主張だったりが含まれるわけです。
同じタイトルで講義したとしても、当然講師のカラーが反映される。
ちょっと前まで、「正しい知識を伝えなきゃ!」と意気込んで講義していたのですが、そう思うようになったら…
「これは、私が正しいと思い込んでるだけ、かもしれない」と逆に、違う意見や考え方を求め、欲するようになりました。いや、それでも…受講者のニーズに平均的に応えられる目線で、情報はアウトプットしたいな、とはおもいますけどね。
そういう時代背景からか、文献を読んでいても、「これは、実際まだ研究されてない」とか「こう思われているけど、ホントのところは解明が不十分」とかいう文言を見かける(昔からそうだったかもしれないけど、私がそれに気づけるようになった?)事が多くなり、意外とエビデンス(根拠)はないけど、世間一般、当たり前に信じられている事って多いわけです。
例えば、昨日のテーマは「水分補給」で、一昔前には「水を、運動中に飲んではいけない」と信じて疑わなかった訳です。ところが、急に「水はこまめに補給を」とか挙句の果てには「喉が渇く前に」とか、「はぁ?喉が渇く前に水なんて飲めるかっ!」て事、思いませんでしたか?
そしたら、いろんなスポーツドリンクが出てきて…昔は「ポカリスエット」飲めるの憧れてたけど(今も高級な感じするなぁ…)
はて、さて、それじゃあ、何飲めばいいの?って話になってきて、
ネットで簡単に調べられる時代になって情報が豊富すぎて…何を信じていいのか、何が本当なのかわからなくなってきて…
っていう人も、多いような気がします。
情報が手軽に入る時代は、便利なようで、不便。意外と使いこなせていない…
のは…結局、大人なんですよね。。
今回、ようやく私もそんなところに気がついて、講義も肩の力を抜いて出来るようになった、気がします。
結局、答えはそれぞれの現場にあります。
沢山の情報を、選択するのは指導者自身で、そこには指導者の経験が非常に大切で、異なる考えでも信念をもって指導にあたる。うまくいかない時には、見方を変えられる柔軟性も必要なのかな…
頭が硬い、硬いと言われ続けた私ですが、「面白い!」と言われて
少しだけ自分の成長を実感できた夜でした。
初めて聞いた言葉だったけど、これって大切な事だなぁ、って思ったよ!」
昨日、講師を担当した「スポーツ指導者研修会」の講話の後の懇親会で、頂いた言葉でした。

最近、トレーニング界でも頻繁に耳にするのが「エビデンスに基づいた実践指導を」という文言。
講習をするにあたり、やはり自分の考えは二の次で、研究文献などで発表されているデータを基に内容を構成していくわけですが、
数ある文献から引用する言葉を選択のは、発表者自身であって、
やはりそこには、発表者の経験だったり、発見だったり、主張だったりが含まれるわけです。
同じタイトルで講義したとしても、当然講師のカラーが反映される。
ちょっと前まで、「正しい知識を伝えなきゃ!」と意気込んで講義していたのですが、そう思うようになったら…
「これは、私が正しいと思い込んでるだけ、かもしれない」と逆に、違う意見や考え方を求め、欲するようになりました。いや、それでも…受講者のニーズに平均的に応えられる目線で、情報はアウトプットしたいな、とはおもいますけどね。
そういう時代背景からか、文献を読んでいても、「これは、実際まだ研究されてない」とか「こう思われているけど、ホントのところは解明が不十分」とかいう文言を見かける(昔からそうだったかもしれないけど、私がそれに気づけるようになった?)事が多くなり、意外とエビデンス(根拠)はないけど、世間一般、当たり前に信じられている事って多いわけです。
例えば、昨日のテーマは「水分補給」で、一昔前には「水を、運動中に飲んではいけない」と信じて疑わなかった訳です。ところが、急に「水はこまめに補給を」とか挙句の果てには「喉が渇く前に」とか、「はぁ?喉が渇く前に水なんて飲めるかっ!」て事、思いませんでしたか?
そしたら、いろんなスポーツドリンクが出てきて…昔は「ポカリスエット」飲めるの憧れてたけど(今も高級な感じするなぁ…)
はて、さて、それじゃあ、何飲めばいいの?って話になってきて、
ネットで簡単に調べられる時代になって情報が豊富すぎて…何を信じていいのか、何が本当なのかわからなくなってきて…
っていう人も、多いような気がします。
情報が手軽に入る時代は、便利なようで、不便。意外と使いこなせていない…
のは…結局、大人なんですよね。。
今回、ようやく私もそんなところに気がついて、講義も肩の力を抜いて出来るようになった、気がします。
結局、答えはそれぞれの現場にあります。
沢山の情報を、選択するのは指導者自身で、そこには指導者の経験が非常に大切で、異なる考えでも信念をもって指導にあたる。うまくいかない時には、見方を変えられる柔軟性も必要なのかな…
頭が硬い、硬いと言われ続けた私ですが、「面白い!」と言われて
少しだけ自分の成長を実感できた夜でした。