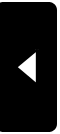2015年09月10日
コンディショニング
「コンディショニング」って何でしょう?
まさしく「コンディション(状態・状況)を整える」事なのだと思います。
日本体育協会アスレチックトレーナーでは
「勝つための全ての準備」
と定義付けられ、その要因は以下の3つ。
①環境を整える
②身体を整える
③心を整える
フィジカル(身体的)トレーニングの「コンディショニング」はスポーツ生理学という、運動時に必要とされるエネルギーシステム(代謝)を強調したプログラム、といえます。
ここには競技特性が大きく関与し、
多くのプログラムには運動/休息比が用いられます。
例えば、バレーボール(国際大会)の場合、
・1プレー3~10秒
・1ラリー5~30秒
・1セット20~30秒
・1試合60~120分
・プレー間20~30秒(休息)
・セット間3分(休息)
で、行われます。
「コンディショニング」を考える上では、この競技の特徴の中で、「いかに最高のパフォーマンスを出せるか」ということを考慮したうえで
「準備」を整えなければなりません。
これこそ、まさに”ゲームのための身体づくり”と言えます。
「体力をつける」ためにスピードの強弱、セットの時間や休息時間を無視した「走り続ける」トレーニングだけでは
例え選手が一生懸命トレーニングを積んだとしても、ケガが絶えなかったり、体力の改善が見えなかったりすることはよく現場でみられます。
「コンディショニングプログラム」はおそらく選手が一番嫌がるプログラムかもしれません。。
だから一番テンションが下がます・・・
今日は「頑張れ!自分に負けるな!」と叱咤激励。。キツいのも、よく分かるから…観ていてこちらも、力が入ります。
だから、写真も撮り忘れてしまいました(笑)
また時間があるときに、詳しく紹介したいと思います。
まさしく「コンディション(状態・状況)を整える」事なのだと思います。
日本体育協会アスレチックトレーナーでは
「勝つための全ての準備」
と定義付けられ、その要因は以下の3つ。
①環境を整える
②身体を整える
③心を整える
フィジカル(身体的)トレーニングの「コンディショニング」はスポーツ生理学という、運動時に必要とされるエネルギーシステム(代謝)を強調したプログラム、といえます。
ここには競技特性が大きく関与し、
多くのプログラムには運動/休息比が用いられます。
例えば、バレーボール(国際大会)の場合、
・1プレー3~10秒
・1ラリー5~30秒
・1セット20~30秒
・1試合60~120分
・プレー間20~30秒(休息)
・セット間3分(休息)
で、行われます。
「コンディショニング」を考える上では、この競技の特徴の中で、「いかに最高のパフォーマンスを出せるか」ということを考慮したうえで
「準備」を整えなければなりません。
これこそ、まさに”ゲームのための身体づくり”と言えます。
「体力をつける」ためにスピードの強弱、セットの時間や休息時間を無視した「走り続ける」トレーニングだけでは
例え選手が一生懸命トレーニングを積んだとしても、ケガが絶えなかったり、体力の改善が見えなかったりすることはよく現場でみられます。
「コンディショニングプログラム」はおそらく選手が一番嫌がるプログラムかもしれません。。
だから一番テンションが下がます・・・
今日は「頑張れ!自分に負けるな!」と叱咤激励。。キツいのも、よく分かるから…観ていてこちらも、力が入ります。
だから、写真も撮り忘れてしまいました(笑)
また時間があるときに、詳しく紹介したいと思います。
2015年09月08日
ウエイトトレーニング
最近、 ”スムージー” という飲み物にはまっていて、
グリーンスムージーからちょっとハマって、小松菜とオレンジ、バナナはおススメです。
今日はちょっと腐れかけたバナナとグアバと牛乳でつくりました。種はあるけど美味しいです。
本日は7時半からの練習。
練習後にウエイトトレーニングをやりました。
今年のチームは早い段階から導入できたので、夏休みも週2回やってきました。
変化をつけるために「高重量の日」と「低重量の日」に設定しています。
9月から、シーズンの変わり目を期にメニューと負荷を変えています。
スペースと器具と時間の関係で、沢山のメニューを行うことはできませんが
「ビッグⅢ」と呼ばれる
・スクワット
・ベンチプレス
・デッドリフト
・・・に加えて、爆発的なパワーの獲得のために
・クリーン
・・・をベースにプログラムを立てています。
<パワー改善のメニュー>
・クリーン
・ジャンプアップ
<コアリフト メニュー>
・パラレルスクワット
・デッドリフト
・ベンチプレス
<体幹メニュー>
・ダンベル・ロウ
・トランクローテーション
・サイドベンド
<肩のメニュー>
・エンプティカン
・バックプレスwithバックエクステンション
・インバーテッド・ロウ
ウエイトトレーニングは、体幹と下肢、体幹と上肢、体幹と下肢と肩甲骨周囲筋群・・・というように
一つのメニューでいろんな筋肉との協調性を図ることができるので便利です。
例えば、スクワット。下半身のトレーニングとしてベーシックなメニューですが
下げる深さによって、下半身の筋を最大限につかわざるおえない。
また、深くさげれば股関節周りの柔軟性の改善にも役立ち、重さを肩にささえることで
体幹にもしっかり圧がかかり、バランスを取る必要がでてきます。

しっかりと意図をつたえて、十分深くさげてもらうパラレルスクワット(太ももと床が平行になる角度)またはそれ以下のディープスクワットに挑戦するように伝えていますが・・・まあ、なかなか伝わらないのは、「個々のトレーニングに対する意識」の問題です。
負けずにしつこく、伝えます(笑)。

クリーン。膝下からバーを、爆発的に引き上げる。ジャンプ力改善のパワートレーニング。

デッドリフト。バレーボールはこの姿勢がキープできることで大きくパフォーマンスに生かされます。

ベンチプレス。だいぶ意識して重さにチャレンジするように。女子選手で差がつくメニューの一つ。

インバーテッド・ロウ。意外と「引く」動作は重要です。懸垂の準備段階として。
もっと胸に引き寄せてほしかった。使い方が下手な例になってしまいました・・・(笑)

バックプレスとバックエクステンションを同時に行っています。体幹と肩回りの協調性を図ります。
基本的に、トレーニングはなんでもやってみればいい、と思います。
まずは、やってみることです。
いっぱい試行錯誤してきましたが、今はこれで落ち着いてる感じです。
「いや、もっとこうした方がいいかもしれない」
と、常に考えて工夫していきたいと思います。
グリーンスムージーからちょっとハマって、小松菜とオレンジ、バナナはおススメです。
今日はちょっと腐れかけたバナナとグアバと牛乳でつくりました。種はあるけど美味しいです。
本日は7時半からの練習。
練習後にウエイトトレーニングをやりました。
今年のチームは早い段階から導入できたので、夏休みも週2回やってきました。
変化をつけるために「高重量の日」と「低重量の日」に設定しています。
9月から、シーズンの変わり目を期にメニューと負荷を変えています。
スペースと器具と時間の関係で、沢山のメニューを行うことはできませんが
「ビッグⅢ」と呼ばれる
・スクワット
・ベンチプレス
・デッドリフト
・・・に加えて、爆発的なパワーの獲得のために
・クリーン
・・・をベースにプログラムを立てています。
<パワー改善のメニュー>
・クリーン
・ジャンプアップ
<コアリフト メニュー>
・パラレルスクワット
・デッドリフト
・ベンチプレス
<体幹メニュー>
・ダンベル・ロウ
・トランクローテーション
・サイドベンド
<肩のメニュー>
・エンプティカン
・バックプレスwithバックエクステンション
・インバーテッド・ロウ
ウエイトトレーニングは、体幹と下肢、体幹と上肢、体幹と下肢と肩甲骨周囲筋群・・・というように
一つのメニューでいろんな筋肉との協調性を図ることができるので便利です。
例えば、スクワット。下半身のトレーニングとしてベーシックなメニューですが
下げる深さによって、下半身の筋を最大限につかわざるおえない。
また、深くさげれば股関節周りの柔軟性の改善にも役立ち、重さを肩にささえることで
体幹にもしっかり圧がかかり、バランスを取る必要がでてきます。

しっかりと意図をつたえて、十分深くさげてもらうパラレルスクワット(太ももと床が平行になる角度)またはそれ以下のディープスクワットに挑戦するように伝えていますが・・・まあ、なかなか伝わらないのは、「個々のトレーニングに対する意識」の問題です。
負けずにしつこく、伝えます(笑)。

クリーン。膝下からバーを、爆発的に引き上げる。ジャンプ力改善のパワートレーニング。

デッドリフト。バレーボールはこの姿勢がキープできることで大きくパフォーマンスに生かされます。

ベンチプレス。だいぶ意識して重さにチャレンジするように。女子選手で差がつくメニューの一つ。

インバーテッド・ロウ。意外と「引く」動作は重要です。懸垂の準備段階として。
もっと胸に引き寄せてほしかった。使い方が下手な例になってしまいました・・・(笑)

バックプレスとバックエクステンションを同時に行っています。体幹と肩回りの協調性を図ります。
基本的に、トレーニングはなんでもやってみればいい、と思います。
まずは、やってみることです。
いっぱい試行錯誤してきましたが、今はこれで落ち着いてる感じです。
「いや、もっとこうした方がいいかもしれない」
と、常に考えて工夫していきたいと思います。
2015年09月07日
コアとジャンプトレーニング
体育祭も終わり、今日と明日は代休です。
今日は体育館が15時50分からしか使えなかったので…休みの日などは1時間前からウォームアップを兼ねてフィジカルトレーニングを導入しています。
今日からコアトレーニング(体幹トレの表現)とジャンプトレーニングのメニューを変更するので、その指導を行いました。
今のところコアトレは4週間、ジャンプは2週間でメニューを段階的に変更しています。
全体の達成度を観察すると、これくらいが適当かなあ、という感覚と
スキルトレーニング(バレーボールの技術練習)の現状と、期分け(ピリオダイゼーション)によるものです。
頻度はコアはアクティブストレッチング後毎日、ジャンプは週2回でプログラムを組んでいます。
トレーニング(ウォームアップ)時間はおおよそ20分で設定しています(ウエイトトレーニングは1時間)。
9月までの3ヶ月間はコアもジャンプも「スタビリティ(安定性)」を目的に進めてきましたが、
シーズンが変わり(準備期間→試合期間)少しづつプレースタイルに近づけたり、
動作を大きくした中で身体をコントロールするようなメニューを取り入れてみています。
新チームも一年間で考えればまだまだ準備段階なので、プレースタイルに近い、といっても
基本動作の繰り返しと積み重ねで、この先に続く大会にピーキングを図ります。
下記は今日指導したメニューです。
〈 コアトレーニング・メニュー 〉
⑴90°スクワット(体幹と下半身)
⑵バックエクステンション(背筋)
⑶クイックヒップリフト(臀部とハムストリングス)
⑷デッドバグ(導入編:股関節屈曲)
⑸サイドブリッジ(体側部と肩の安定性)
⑹肘立て伏せ(コアの安定性と肩甲骨の可動)

クイックヒップリフト

サイドブリッジ(臀部の拳上と下降)

90°スクワット
〈 ジャンプトレーニング・メニュー 〉
(1)バックペダル→ワンステップジャンプ
(2)デプスジャンプToテーブル
(3)ラテラルジャンプ

ワンステップジャンプ。助走からのバックスウィングを大きく、強く踏み込んでジャンプ。

ラテラルジャンプ。時間をかけて行っているトレーニングの一つです。
繰り返し、こちらの求めるイメージとカラダの使い方を指導しています。
プレーになれば、ボールのスピード、高さに合わせてジャンプしなければならないわけですが、
トレーニングはそういう制限を取り払った「分習法」なので、とにかくポータブルテーブルに向かって
力強く、おもいっきりジャンプをするように伝えました。
コアもジャンプもこの段階に来るまで、基礎トレーニングを積んでいます。
ジャンプもスキル(技術)なので、ポイントを伝え、「ケガの予防」をまず図りました。
だいぶ出来るようになりましたが、まだスピードと筋力が足りませんね。
指導もコツコツ、積み重ねと継続の地道な繰り返しです。。。
今日は体育館が15時50分からしか使えなかったので…休みの日などは1時間前からウォームアップを兼ねてフィジカルトレーニングを導入しています。
今日からコアトレーニング(体幹トレの表現)とジャンプトレーニングのメニューを変更するので、その指導を行いました。
今のところコアトレは4週間、ジャンプは2週間でメニューを段階的に変更しています。
全体の達成度を観察すると、これくらいが適当かなあ、という感覚と
スキルトレーニング(バレーボールの技術練習)の現状と、期分け(ピリオダイゼーション)によるものです。
頻度はコアはアクティブストレッチング後毎日、ジャンプは週2回でプログラムを組んでいます。
トレーニング(ウォームアップ)時間はおおよそ20分で設定しています(ウエイトトレーニングは1時間)。
9月までの3ヶ月間はコアもジャンプも「スタビリティ(安定性)」を目的に進めてきましたが、
シーズンが変わり(準備期間→試合期間)少しづつプレースタイルに近づけたり、
動作を大きくした中で身体をコントロールするようなメニューを取り入れてみています。
新チームも一年間で考えればまだまだ準備段階なので、プレースタイルに近い、といっても
基本動作の繰り返しと積み重ねで、この先に続く大会にピーキングを図ります。
下記は今日指導したメニューです。
〈 コアトレーニング・メニュー 〉
⑴90°スクワット(体幹と下半身)
⑵バックエクステンション(背筋)
⑶クイックヒップリフト(臀部とハムストリングス)
⑷デッドバグ(導入編:股関節屈曲)
⑸サイドブリッジ(体側部と肩の安定性)
⑹肘立て伏せ(コアの安定性と肩甲骨の可動)

クイックヒップリフト

サイドブリッジ(臀部の拳上と下降)

90°スクワット
〈 ジャンプトレーニング・メニュー 〉
(1)バックペダル→ワンステップジャンプ
(2)デプスジャンプToテーブル
(3)ラテラルジャンプ

ワンステップジャンプ。助走からのバックスウィングを大きく、強く踏み込んでジャンプ。

ラテラルジャンプ。時間をかけて行っているトレーニングの一つです。
繰り返し、こちらの求めるイメージとカラダの使い方を指導しています。
プレーになれば、ボールのスピード、高さに合わせてジャンプしなければならないわけですが、
トレーニングはそういう制限を取り払った「分習法」なので、とにかくポータブルテーブルに向かって
力強く、おもいっきりジャンプをするように伝えました。
コアもジャンプもこの段階に来るまで、基礎トレーニングを積んでいます。
ジャンプもスキル(技術)なので、ポイントを伝え、「ケガの予防」をまず図りました。
だいぶ出来るようになりましたが、まだスピードと筋力が足りませんね。
指導もコツコツ、積み重ねと継続の地道な繰り返しです。。。
2015年09月06日
負荷をかける
体育祭シーズンですね。
大高の体育祭を今年も観に行きました。
ムカデのスピードと応援団の気迫は圧巻ですね。高校生達の自主性によるエネルギーは素晴らしい。
今月は「フィジカルトレーニング」について
取り入れた情報と、自分の実践状況と経験と考えを踏まえて
書き込んでいきます。半分は自分の活動と考え方の整理です。
(興味ある方が「へー」と思ってもらえればいいかな。)
まず、根本的な私のフィジカルトレーニングに対する考え方。
フィジカル(身体)トレーニングは「負荷」をかけないと意味がありません。
自分のカラダを追い込んで、追い込んで、追い込んでこそ・・・成長できると思っています。
かといって、急にハードトレーニングをさせても、これこそ無意味です。
だから、まずは「自分の体重をコントロールできるか」が負荷をどれくらいかけるかの最初のチェックになります。
体力測定も然りです。これは個々の現状を他者と比較しつつ、成長を数値で表し、トレーニング効果を可視化するためのものです。
指導者が毎日きちんと選手を観察できていれば、粗方その数字は納得できるものになるはずです。
負荷は自体重のみでも、動作コントロールが「きちんと」できれば、十分変化がみられます(注:大半は間違った動きに気づく事なく、サボっています)。
チームのトレーニングを担当していますが、私の中ではまだまだ半分くらいしか、させきれていません。
大事なことですが、本当に自分が成長するには、個々のモチベーションの高さが必要だと思っています。
これは、こちらからいくら要求しても、ほぼ伝わりません。
やらせることもできますが、「強制」はサボりにすぐ繋がります。
まだまだ、フィジカルトレーニングの必要性を選手に伝えきれていないのだと思います。私の責任もあります。
あとは、目指すべき目標やイメージが明確でないのでしょう。ここを伝えるには実際、試合をこなして、自分達の実力を目の当たりにしないと難しいかも。もう少し時間が必要です。
そういう状況の中でも、「負荷をかける」ことは可能な範囲で行うべきだと思います。
選手は素直です。言われた事はやります。だから、知らない間に身体は負荷に耐え得る能力を身につける。パフォーマンスも時間かければ上手くなります。
ただ、「やらされているトレーニングは面白くないだろうな」と思います…
「人間は自分に出来ないと思う事、上手くやれないと思う事はやらない」
…習性があるようなので、やはり待つしかないな、と思うのです。
応援団のように…自主性ある部活動に。
自分で上手くなるための工夫し、「負荷」をかけられるような選手が現れるのを楽しみにしながら…
「フィジカルトレーニング」の必要性を伝えて、実際に形として残していきたいと思います。
これも一つ私の「負荷」として、チャレンジしたいと思います。
大高の体育祭を今年も観に行きました。
ムカデのスピードと応援団の気迫は圧巻ですね。高校生達の自主性によるエネルギーは素晴らしい。
今月は「フィジカルトレーニング」について
取り入れた情報と、自分の実践状況と経験と考えを踏まえて
書き込んでいきます。半分は自分の活動と考え方の整理です。
(興味ある方が「へー」と思ってもらえればいいかな。)
まず、根本的な私のフィジカルトレーニングに対する考え方。
フィジカル(身体)トレーニングは「負荷」をかけないと意味がありません。
自分のカラダを追い込んで、追い込んで、追い込んでこそ・・・成長できると思っています。
かといって、急にハードトレーニングをさせても、これこそ無意味です。
だから、まずは「自分の体重をコントロールできるか」が負荷をどれくらいかけるかの最初のチェックになります。
体力測定も然りです。これは個々の現状を他者と比較しつつ、成長を数値で表し、トレーニング効果を可視化するためのものです。
指導者が毎日きちんと選手を観察できていれば、粗方その数字は納得できるものになるはずです。
負荷は自体重のみでも、動作コントロールが「きちんと」できれば、十分変化がみられます(注:大半は間違った動きに気づく事なく、サボっています)。
チームのトレーニングを担当していますが、私の中ではまだまだ半分くらいしか、させきれていません。
大事なことですが、本当に自分が成長するには、個々のモチベーションの高さが必要だと思っています。
これは、こちらからいくら要求しても、ほぼ伝わりません。
やらせることもできますが、「強制」はサボりにすぐ繋がります。
まだまだ、フィジカルトレーニングの必要性を選手に伝えきれていないのだと思います。私の責任もあります。
あとは、目指すべき目標やイメージが明確でないのでしょう。ここを伝えるには実際、試合をこなして、自分達の実力を目の当たりにしないと難しいかも。もう少し時間が必要です。
そういう状況の中でも、「負荷をかける」ことは可能な範囲で行うべきだと思います。
選手は素直です。言われた事はやります。だから、知らない間に身体は負荷に耐え得る能力を身につける。パフォーマンスも時間かければ上手くなります。
ただ、「やらされているトレーニングは面白くないだろうな」と思います…
「人間は自分に出来ないと思う事、上手くやれないと思う事はやらない」
…習性があるようなので、やはり待つしかないな、と思うのです。
応援団のように…自主性ある部活動に。
自分で上手くなるための工夫し、「負荷」をかけられるような選手が現れるのを楽しみにしながら…
「フィジカルトレーニング」の必要性を伝えて、実際に形として残していきたいと思います。
これも一つ私の「負荷」として、チャレンジしたいと思います。
2015年09月05日
地方でも広がる?パーソナルトレーナー?
トレーナーを夢みて、トレーナーになりたくて、地元広島で就職活動している時に出会った先生と
この便利な世の中、Facebookで繋がり、先生の活動や考え方を遠くからでも学ばせていただいています。
そのFBで投稿されていた記事、「しーまブログ」にてシェアさせていただきます。

投稿された文面に、先生もおっしゃられていましたが、トレーナー(パーソナルトレーナー)という言葉はあまりに曖昧で、仕事の中身もトレーナーそれぞれ、バラバラです。
本来チームやスポーツ選手に対するトレーニング指導専門のトレーナーは
「フィジカルトレーナー」
と分類されるし、
ケガの応急処置やテーピング、ケガからの競技復帰までのフォローを専門とするトレーナーは
「アスレティックトレーナー」
と分類されます。
だいぶ、減ってきてはいますが・・・「トレーナーに相談すれば、ケガを治してくれる」
と、受動的な認識をされる方も日本には沢山います。実際、「トレーナー」はとても曖昧がゆえに、
治療資格(鍼灸師・柔道整復師・理学療法士など)を取得し、現場でトレーナー活動される方は重宝されます。
でも、実際は治療師とトレーナーは『別物』であり、それぞれ役割を相互理解しながら選手のフォローを担うのがベストです。
この記事でも触れられていますが、「パーソナルトレーナー」の火付け役が
今はやりの・・・『ライザップ』
広島でも予約待ち、といいますから・・・ホント、コマーシャルの影響は大きいですね!
『ライザップ』については・・・トレーニング終了後、果たして、どう体型をキープしていくのか・・・・そこに興味がありますね。
最近「米国のパーソナルトレーナー最新事情」という記事を読みました。
スポーツ大国アメリカにおいては、「パーソナルトレーナー」の認知度、浸透度、そして職業としての「パーソナルトレーナー」の社会的地位は日本でのイメージよりもはるかに上回るそうです。
日本でも、認知度は向上してきているものの、フィットネス参加率が人口のわずか3%、その中のさらにコアなユーザーのみが「パーソナルトレーナー」を利用している程度にとどまっている・・・(これでは仕事にはなりませんね・・・)
日本でも「ピアノを身につけたい」と思えばピアノの先生に習うために個人レッスンに通いますが、アメリカでは「カラダ作りをしたい」と思えば「パーソナルトレーナー」にトレーニングを習うようです。
私が一般の方にトレーニング指導している「コア・コンディショニング」に来られる方も、
「カラダづくりをしたい」、とレッスンに来られています。
しかしながら、これでは「パーソナルトレーナー」とは呼べません。
1人1人、カラダも違えば、ニーズも違う。言葉のとらえ方も、動作の感覚も違う。
その日の体調も違うじゃないですか。
レッスンしながらも、毎回毎回、「これでいいかなあ?本当に伝わったかなあ・・・?」
その繰り返しです。
ですが、この「フィットネス・スタイル」でもクライアントさんが笑顔で喜んでくださったらいいのかな、と思いつつ
私の中では葛藤の毎日です。
いつか、「カラダを鍛えること」で健康を獲得できたり、
「カラダを鍛えること」でパフォーマンスを改善できる、という
世の中の流れを、作れたらいいなと思います。
そのためには「本物」であること。
1)実力が本物であるということ
2)常に情報をアップデートし、勉強していること
3)プロ意識が高く、社会人として自立している
4)コミュニケーション能力が高いこと
5)自分自身が身体を鍛えていること
そう。環境を嘆く前に、私自身、やるべきことはまだまだある。
意識を高くもち、これからも「本物」を目指します。
この便利な世の中、Facebookで繋がり、先生の活動や考え方を遠くからでも学ばせていただいています。
そのFBで投稿されていた記事、「しーまブログ」にてシェアさせていただきます。

投稿された文面に、先生もおっしゃられていましたが、トレーナー(パーソナルトレーナー)という言葉はあまりに曖昧で、仕事の中身もトレーナーそれぞれ、バラバラです。
本来チームやスポーツ選手に対するトレーニング指導専門のトレーナーは
「フィジカルトレーナー」
と分類されるし、
ケガの応急処置やテーピング、ケガからの競技復帰までのフォローを専門とするトレーナーは
「アスレティックトレーナー」
と分類されます。
だいぶ、減ってきてはいますが・・・「トレーナーに相談すれば、ケガを治してくれる」
と、受動的な認識をされる方も日本には沢山います。実際、「トレーナー」はとても曖昧がゆえに、
治療資格(鍼灸師・柔道整復師・理学療法士など)を取得し、現場でトレーナー活動される方は重宝されます。
でも、実際は治療師とトレーナーは『別物』であり、それぞれ役割を相互理解しながら選手のフォローを担うのがベストです。
この記事でも触れられていますが、「パーソナルトレーナー」の火付け役が
今はやりの・・・『ライザップ』
広島でも予約待ち、といいますから・・・ホント、コマーシャルの影響は大きいですね!
『ライザップ』については・・・トレーニング終了後、果たして、どう体型をキープしていくのか・・・・そこに興味がありますね。
最近「米国のパーソナルトレーナー最新事情」という記事を読みました。
スポーツ大国アメリカにおいては、「パーソナルトレーナー」の認知度、浸透度、そして職業としての「パーソナルトレーナー」の社会的地位は日本でのイメージよりもはるかに上回るそうです。
日本でも、認知度は向上してきているものの、フィットネス参加率が人口のわずか3%、その中のさらにコアなユーザーのみが「パーソナルトレーナー」を利用している程度にとどまっている・・・(これでは仕事にはなりませんね・・・)
日本でも「ピアノを身につけたい」と思えばピアノの先生に習うために個人レッスンに通いますが、アメリカでは「カラダ作りをしたい」と思えば「パーソナルトレーナー」にトレーニングを習うようです。
私が一般の方にトレーニング指導している「コア・コンディショニング」に来られる方も、
「カラダづくりをしたい」、とレッスンに来られています。
しかしながら、これでは「パーソナルトレーナー」とは呼べません。
1人1人、カラダも違えば、ニーズも違う。言葉のとらえ方も、動作の感覚も違う。
その日の体調も違うじゃないですか。
レッスンしながらも、毎回毎回、「これでいいかなあ?本当に伝わったかなあ・・・?」
その繰り返しです。
ですが、この「フィットネス・スタイル」でもクライアントさんが笑顔で喜んでくださったらいいのかな、と思いつつ
私の中では葛藤の毎日です。
いつか、「カラダを鍛えること」で健康を獲得できたり、
「カラダを鍛えること」でパフォーマンスを改善できる、という
世の中の流れを、作れたらいいなと思います。
そのためには「本物」であること。
1)実力が本物であるということ
2)常に情報をアップデートし、勉強していること
3)プロ意識が高く、社会人として自立している
4)コミュニケーション能力が高いこと
5)自分自身が身体を鍛えていること
そう。環境を嘆く前に、私自身、やるべきことはまだまだある。
意識を高くもち、これからも「本物」を目指します。
2015年09月04日
「体力」をつけるには?part2
昨日のチームのトレーニング。
久々の5km走。雨の中頑張っていたようです。
「体力」とは「体力要素」の総称であり、体力要素とは
・スピード
・アジリティ(方向転換能力)
・パワー(ジャンプなど爆発的な運動)
・筋力
・柔軟性
…など細かくわけられます。
学校で行う体力測定のような感じですね。
トレーニングを行うという事は、必ずそこに「目的」があります。
1番に掲げるべき目的は
「パフォーマンスの向上」
です。
先週、講習をした「体幹トレーニング」も
最終的には、「選手のパフォーマンスにどう繋げていくのか?」ということが大事だと思います。
すでにトレーニング導入前の段階で必要性の分析は出来ています。
バレーボール競技で最も重要な「体力」は「パワー」です。
「パワー」と聞いて、何が思い浮かびますか?
恐らく大半の方は「ボールをたたく力」「ボールのスピード」とイメージされるでしょう。
「パワー」の要素には
ジャンプや、短い距離、停止状態からの爆発的なスタートも含まれます。
「パワーをつける」には筋力が必要です。
「パワーをつける」には体幹(コア)の安定性がさらに必要です。
「パワーをつける」にはスピードが必要です。
さて、「パワー」という「体力」をつけるには、どうしたらいいのでしょうね・・・
何から、始めましょうか・・・
・・・・。
・・・というのを、考えて、実践して、反省して、時に失敗して、勉強して、継続していく地味な仕事が
私たちトレーナーの役割なのだと思います。
だから「走らせる」事、一つにしても、私は悩むのです。
人間のエネルギーシステムや、筋肉の構造、タイプ・・・科学的な事を知れば知るほど、
悩むのです。
が・・・
監督の一言でふっきれました。
「たかだか週1回の10kmくらい、走りきれるくらいの体力(ベース)がないとダメでしょ。」
あ、そうだね・・・週1回くらいじゃ、身体はそんなに適応は示さないか・・・
それ以上に、パワー系のトレーニングをやっているわけだから。
これも「トレーニングの目的」の一つの見解です。
1人で考え込むと、視野が狭くなりますね・・・
「体力」をつけるには?
科学的なデータはあっても、最終的にはトレーニングを行う選手のレベルに応じます。
そして、プログラムを実施させていて強く思うのは、
内容云々を考えるよりも難しいこと。
個人の「うまくなりたい・強くなりたい」という
目標と想いを、どう引き上げるか、です・・・(やっぱり)。
久々の5km走。雨の中頑張っていたようです。
「体力」とは「体力要素」の総称であり、体力要素とは
・スピード
・アジリティ(方向転換能力)
・パワー(ジャンプなど爆発的な運動)
・筋力
・柔軟性
…など細かくわけられます。
学校で行う体力測定のような感じですね。
トレーニングを行うという事は、必ずそこに「目的」があります。
1番に掲げるべき目的は
「パフォーマンスの向上」
です。
先週、講習をした「体幹トレーニング」も
最終的には、「選手のパフォーマンスにどう繋げていくのか?」ということが大事だと思います。
すでにトレーニング導入前の段階で必要性の分析は出来ています。
バレーボール競技で最も重要な「体力」は「パワー」です。
「パワー」と聞いて、何が思い浮かびますか?
恐らく大半の方は「ボールをたたく力」「ボールのスピード」とイメージされるでしょう。
「パワー」の要素には
ジャンプや、短い距離、停止状態からの爆発的なスタートも含まれます。
「パワーをつける」には筋力が必要です。
「パワーをつける」には体幹(コア)の安定性がさらに必要です。
「パワーをつける」にはスピードが必要です。
さて、「パワー」という「体力」をつけるには、どうしたらいいのでしょうね・・・
何から、始めましょうか・・・
・・・・。
・・・というのを、考えて、実践して、反省して、時に失敗して、勉強して、継続していく地味な仕事が
私たちトレーナーの役割なのだと思います。
だから「走らせる」事、一つにしても、私は悩むのです。
人間のエネルギーシステムや、筋肉の構造、タイプ・・・科学的な事を知れば知るほど、
悩むのです。
が・・・
監督の一言でふっきれました。
「たかだか週1回の10kmくらい、走りきれるくらいの体力(ベース)がないとダメでしょ。」
あ、そうだね・・・週1回くらいじゃ、身体はそんなに適応は示さないか・・・
それ以上に、パワー系のトレーニングをやっているわけだから。
これも「トレーニングの目的」の一つの見解です。
1人で考え込むと、視野が狭くなりますね・・・
「体力」をつけるには?
科学的なデータはあっても、最終的にはトレーニングを行う選手のレベルに応じます。
そして、プログラムを実施させていて強く思うのは、
内容云々を考えるよりも難しいこと。
個人の「うまくなりたい・強くなりたい」という
目標と想いを、どう引き上げるか、です・・・(やっぱり)。
2015年09月03日
「体力」をつけるには?
今日も、書きます。今日は久々「トレーニング」についてです。
「体力」といえば、何が思い浮かびますか?
「体力をつける」と聞いて、どんな手段が思い浮かびますか?
恐らく、半数以上の人は
「走る」
「長い距離を走れる体力」
「長い時間走れると体力がつく」
私も、そう信じてきた人間です。
そして、「体力をつけろ!」と言われるたびに、走らされてきた1人です。
専門用語言えば『最大酸素摂取量(Vo2max)』が高まれば、長時間プレーすることや疲労からより早く回復することが可能になる、という考え方です。
(*最大酸素摂取量・・・全身の細胞レベルで利用することが出来る酸素量の最大値)
最近、トレーニングプログラムを立てる中で私の迷いは、この
「走る」
ということでした。
現在プログラムを立てている種目は「バレーボール」のみですが、
バレーボールという競技は、ジャンプや方向転換の能力(パワー)、スピードの要素が求められる競技です。
プログラムを立てる上で、考えなければならないポイントは
「スポーツの特異性」
です。
どういう意味かといいますと、
バレーボールの試合中、ずっと同じペースで走り続けるような場面はない、ということです。
いわゆる「体力=走る」というセオリーは当てはまらない競技、ということになります。
しかもチームスポーツのほとんどすべては「スピード」と「パワー」が要求されます。
以下は文献でよく目にする文言です。
-パワー系選手の有酸素トレーニングを実施すると、結果的に『最大酸素摂取量』は高まったが、パフォーマンスには変化がみられなかった。
-「サッカー選手は1試合で約10km走る」「テニスの試合は2時間以上続く」のだから、より早い回復には有酸素系システム(長く運動を続ける機能)が重要だ。
続けて、こう述べてあります。
-しかし、このようなことは問題ではない。問題なのは、どのくらいのスピードで、どのくらいの時間で、である。テニスの試合では約2時間プレーしているが、そのうちスプリント(ダッシュ)と休息の比率はどのくらいだろうか。
もう一つ、よく目にする文言ですが・・・
-持久性トレーニングに集中しすぎると、スピードの発達に悪影響を及ぼす可能性があることも考慮しなければならない。逆をとれば、スプリンターを長距離選手にするのは簡単だともいえる。
そうなんですよ・・・
身体、というのは適応するからトレーニングの効果が反映されるわけで、
いくら「体力をつける」ために長い距離を走れるようになったとしても、
競技特異性からみれば、
昔から言われていた「長い距離を走れる体力」は
バレーボールやサッカー、テニスやバドミントンなどの技術改善にはならない、わけです。
当然といえば、当然です。
では、それでもやっぱり「走る」トレーニングをチーム取り入れるべきと思っている・・・
しかも、「長距離走」です。
そこには、「トレーニングの目的」が関係します。
長くなりそうなので、また続きは明日書く事にします。。
「体力」といえば、何が思い浮かびますか?
「体力をつける」と聞いて、どんな手段が思い浮かびますか?
恐らく、半数以上の人は
「走る」
「長い距離を走れる体力」
「長い時間走れると体力がつく」
私も、そう信じてきた人間です。
そして、「体力をつけろ!」と言われるたびに、走らされてきた1人です。
専門用語言えば『最大酸素摂取量(Vo2max)』が高まれば、長時間プレーすることや疲労からより早く回復することが可能になる、という考え方です。
(*最大酸素摂取量・・・全身の細胞レベルで利用することが出来る酸素量の最大値)
最近、トレーニングプログラムを立てる中で私の迷いは、この
「走る」
ということでした。
現在プログラムを立てている種目は「バレーボール」のみですが、
バレーボールという競技は、ジャンプや方向転換の能力(パワー)、スピードの要素が求められる競技です。
プログラムを立てる上で、考えなければならないポイントは
「スポーツの特異性」
です。
どういう意味かといいますと、
バレーボールの試合中、ずっと同じペースで走り続けるような場面はない、ということです。
いわゆる「体力=走る」というセオリーは当てはまらない競技、ということになります。
しかもチームスポーツのほとんどすべては「スピード」と「パワー」が要求されます。
以下は文献でよく目にする文言です。
-パワー系選手の有酸素トレーニングを実施すると、結果的に『最大酸素摂取量』は高まったが、パフォーマンスには変化がみられなかった。
-「サッカー選手は1試合で約10km走る」「テニスの試合は2時間以上続く」のだから、より早い回復には有酸素系システム(長く運動を続ける機能)が重要だ。
続けて、こう述べてあります。
-しかし、このようなことは問題ではない。問題なのは、どのくらいのスピードで、どのくらいの時間で、である。テニスの試合では約2時間プレーしているが、そのうちスプリント(ダッシュ)と休息の比率はどのくらいだろうか。
もう一つ、よく目にする文言ですが・・・
-持久性トレーニングに集中しすぎると、スピードの発達に悪影響を及ぼす可能性があることも考慮しなければならない。逆をとれば、スプリンターを長距離選手にするのは簡単だともいえる。
そうなんですよ・・・
身体、というのは適応するからトレーニングの効果が反映されるわけで、
いくら「体力をつける」ために長い距離を走れるようになったとしても、
競技特異性からみれば、
昔から言われていた「長い距離を走れる体力」は
バレーボールやサッカー、テニスやバドミントンなどの技術改善にはならない、わけです。
当然といえば、当然です。
では、それでもやっぱり「走る」トレーニングをチーム取り入れるべきと思っている・・・
しかも、「長距離走」です。
そこには、「トレーニングの目的」が関係します。
長くなりそうなので、また続きは明日書く事にします。。
2015年09月02日
ASAスポーツ講習会
8月29日に行った「ASAスポーツ講習会」の報告です。
約30名の受講者のみなさん、暑い中ありがとうございました。

今回のテーマは「体幹トレーニング」でした。
最近よく耳にする「体幹」や「コア」という言葉・・・
その違いや、「体幹トレーニング」の本質的なことを解説したうえで
皆さんとトレーニング!
イメージは「腹筋・背筋」でしょうけれど・・・
根本的に、体幹を強化したうえで、
・上肢と下肢の動作をいかにコントロールしていくか?
・動作の安定性をどう身につけるか?
・・・というのが本来、体幹トレーニングを取り入れる上で大切な事だと思います。
デッドリフト・スクワット・・・このような『体幹と下肢』をどう連動させて動作を作っていくか?
正しいフォームで動作を行うことで、全身の筋を効率よく使う。
この繰り返しを行うことで、「体幹トレーニング」が本来の意味をなすのだと思います。
受講者の皆さんには・・・いろんな目的をもって講習に参加してくださったわけですが、
「自分のカラダを自分の思うようにコントロールする」
という事を、実技目標にかがげて、取り組んでもらいました。
実技前の動きに比べて、少し身体も軽く感じてくださったでしょうか?
1度では効果はありませんが、それぞれの感覚を大事に、取り組んで下さるとありがたいです。
次回の内容は、まだ決めていませんが・・・
「こんな事、知っておきたい!」という内容があればコメントに依頼頂けると助かります。
もっと、「スポーツとケガ」についてお知らせしても興味深いのかな?と思ったりします。
予防策を知るのが一番、と個人的には思うのですが
現場では、予防より「対処」の方が、ニーズが高いのかもしれませんね。。。
約30名の受講者のみなさん、暑い中ありがとうございました。

今回のテーマは「体幹トレーニング」でした。
最近よく耳にする「体幹」や「コア」という言葉・・・
その違いや、「体幹トレーニング」の本質的なことを解説したうえで
皆さんとトレーニング!
イメージは「腹筋・背筋」でしょうけれど・・・
根本的に、体幹を強化したうえで、
・上肢と下肢の動作をいかにコントロールしていくか?
・動作の安定性をどう身につけるか?
・・・というのが本来、体幹トレーニングを取り入れる上で大切な事だと思います。
デッドリフト・スクワット・・・このような『体幹と下肢』をどう連動させて動作を作っていくか?
正しいフォームで動作を行うことで、全身の筋を効率よく使う。
この繰り返しを行うことで、「体幹トレーニング」が本来の意味をなすのだと思います。
受講者の皆さんには・・・いろんな目的をもって講習に参加してくださったわけですが、
「自分のカラダを自分の思うようにコントロールする」
という事を、実技目標にかがげて、取り組んでもらいました。
実技前の動きに比べて、少し身体も軽く感じてくださったでしょうか?
1度では効果はありませんが、それぞれの感覚を大事に、取り組んで下さるとありがたいです。
次回の内容は、まだ決めていませんが・・・
「こんな事、知っておきたい!」という内容があればコメントに依頼頂けると助かります。
もっと、「スポーツとケガ」についてお知らせしても興味深いのかな?と思ったりします。
予防策を知るのが一番、と個人的には思うのですが
現場では、予防より「対処」の方が、ニーズが高いのかもしれませんね。。。
2015年05月25日
自分の身は、自分で守る
昨日、資格の継続研修を鹿児島で受けてきました。
日本赤十字社の救急法救急員の資格です。
この資格を初めて取得したのは、おそらく2000年。
日赤の資格は3年間有効。奇しくも更新は5回目、ということになります。
確か、この年のNSCA-CPT(NSCA公認パーソナルトレーナー)の受験をするのにCPR(心肺蘇生法)の資格保持が必須で、
受講したのがきっかけだと思います。
ここ数年で、継続研修が資格有効期間内ならば1日で終わるシステムになったため、
今回も、1日でめでたく資格を更新することができました。
トレーナーだから、という理由でこの資格を保持してきましたが、
最近の大災害や、先日の地震のことを思うと、
スポーツ現場だけでなく、もしかしたら自然災害などでも必要とされる知識なのでは?と
今回受講しながら思いました。
鹿児島県は、今年度から防災強化県として今後、学校関係で防災についての勉強会が行われる、と
指導員の方が言われていました。
火山や地震が多いからです。
そこで
「自助」「共助」「公助」
という言葉を掲げられていました。
東北の災害で、亡くなられた方の90%は即死だったといいます。
うち、生き残られた方の95%は「自助」と「共助」で生き延びられたとそうです。
自力でどうにか乗り切るか、周りの協力を得られて生き延びることができた。
「公助」、つまり消防や自衛隊など国の助けで生きられた方はたった5%。
県や国の助けを待っていたのでは、遅い、というデータが最近ようやく上がってきた、とのこと。
どういうことを意味するのか?
要するに、災害発生時は、「自分の身は、自分で守る」という事、だそうです。
それは、こういう知識を身につけておくことかもしれないし、
過信せず、早めに避難することかもしれないし、
日頃から体力をつけておくことかもしれないし、
その時が起こらないとわからないことなのかもしれないのですが、
「災害に対する意識を、もっと各自がもっておく」ということは今すぐできることなのかもしれません。
スポーツの現場についても、同様のことを思います。
ケガが起きない方がいい、予防が完璧にできれば問題ないのですが、
まず、絶対起こらないということは、ありえません。
スポーツ現場は、「ケガも起こりうる」ということを前提として、
大人は最低限の知識と技術を持っておくべきだと、
私は講習会の場で訴えます。
ケガや痛みに関しても、
必ず、痛みがひどくなる前には「サイン」が出ます。
疲れて、身体が疲労している状態でも「サイン」が出ます。
日頃から、その「サイン」に気づけるかどうかもやはり大事。
でも、その「サイン」に気づいても、訴えることができない環境、
頼る場所がわからないという現状は
日本のスポーツ界の、まだまだ大きな問題です。
でも、ケガの予防に対する意識を日頃から持っておけるかどうかで、
やはり選択肢は準備できるのではないでしょうか?
「自分の身は、自分で守る」
「生きる力」じゃないですけど、
やはり、スポーツ選手もスポーツが出来るだけでなく、
きちんと自己管理できる選手に育ててあげたいと思います。
日本赤十字社の救急法救急員の資格です。
この資格を初めて取得したのは、おそらく2000年。
日赤の資格は3年間有効。奇しくも更新は5回目、ということになります。
確か、この年のNSCA-CPT(NSCA公認パーソナルトレーナー)の受験をするのにCPR(心肺蘇生法)の資格保持が必須で、
受講したのがきっかけだと思います。
ここ数年で、継続研修が資格有効期間内ならば1日で終わるシステムになったため、
今回も、1日でめでたく資格を更新することができました。
トレーナーだから、という理由でこの資格を保持してきましたが、
最近の大災害や、先日の地震のことを思うと、
スポーツ現場だけでなく、もしかしたら自然災害などでも必要とされる知識なのでは?と
今回受講しながら思いました。
鹿児島県は、今年度から防災強化県として今後、学校関係で防災についての勉強会が行われる、と
指導員の方が言われていました。
火山や地震が多いからです。
そこで
「自助」「共助」「公助」
という言葉を掲げられていました。
東北の災害で、亡くなられた方の90%は即死だったといいます。
うち、生き残られた方の95%は「自助」と「共助」で生き延びられたとそうです。
自力でどうにか乗り切るか、周りの協力を得られて生き延びることができた。
「公助」、つまり消防や自衛隊など国の助けで生きられた方はたった5%。
県や国の助けを待っていたのでは、遅い、というデータが最近ようやく上がってきた、とのこと。
どういうことを意味するのか?
要するに、災害発生時は、「自分の身は、自分で守る」という事、だそうです。
それは、こういう知識を身につけておくことかもしれないし、
過信せず、早めに避難することかもしれないし、
日頃から体力をつけておくことかもしれないし、
その時が起こらないとわからないことなのかもしれないのですが、
「災害に対する意識を、もっと各自がもっておく」ということは今すぐできることなのかもしれません。
スポーツの現場についても、同様のことを思います。
ケガが起きない方がいい、予防が完璧にできれば問題ないのですが、
まず、絶対起こらないということは、ありえません。
スポーツ現場は、「ケガも起こりうる」ということを前提として、
大人は最低限の知識と技術を持っておくべきだと、
私は講習会の場で訴えます。
ケガや痛みに関しても、
必ず、痛みがひどくなる前には「サイン」が出ます。
疲れて、身体が疲労している状態でも「サイン」が出ます。
日頃から、その「サイン」に気づけるかどうかもやはり大事。
でも、その「サイン」に気づいても、訴えることができない環境、
頼る場所がわからないという現状は
日本のスポーツ界の、まだまだ大きな問題です。
でも、ケガの予防に対する意識を日頃から持っておけるかどうかで、
やはり選択肢は準備できるのではないでしょうか?
「自分の身は、自分で守る」
「生きる力」じゃないですけど、
やはり、スポーツ選手もスポーツが出来るだけでなく、
きちんと自己管理できる選手に育ててあげたいと思います。
2015年05月21日
競技力向上とケガ
ジュニア選手の痛みに関して、時々ご相談受けることがあります。
「捻った記憶はないけれど、練習後に足首が痛む」
「捻挫してアイシングをしたけれど、それからどうしてあげたらいいのか?」
「腰痛があるのだが、成長期の子供は整骨院などに連れて行ってもいいのか?」
「病院に連れて行った方がいいのか?整骨院などがいいのか?」
我が子が、痛みを訴える。
ささいな疑問でも、いざとなると、不安に感じたり、どう対応してあげたらいいのか、
何を選択したらいいのかわからない。
親としては、悩むところですよね。
私も、小学生の頃から、痛みを訴えて親を悩ませていた一人です。
中学生に至っては、腰痛で悩まされ、
高校でとうとう、ヘルニアの診断で入院。
なぜ、痛みが出たのかわからないけど、痛いと訴える。
「いい」と聞けば、母は私を治療に連れて行ってくれました。
今考えると・・・本当に親に迷惑かけてきたなあ・・・という思いです。
昨日は、以前からご相談を受けていたジュニア選手のもとを尋ねました。
診断は、「腰椎分離症」。いわゆる腰の骨に骨折の形跡がみられる
成長期特有のスポーツ障害の一つです。
ご連絡いただいたのは、その選手を指導されている先生から。
先生自身も、ネットで調べたり、整形外科での診断と指示に従われながら・・・
でも、「どうしたらいいのか、自分では対応できない」という判断でご相談いただいていました。
安静期間を経て、痛みもほぼ解消されていたようなので、
動作の確認をしながら、原因をみつけて、選手本人が出来る事を一緒にやってみました。
観ていて、怖かったかもしれませんね・・・今まで安静にしていた子がストレッチングでかなり身体を動かしていたので。。
でも、そのレベルで身体を動かせないと、競技でかかる負担はもっとですから・・・
痛みなく、自分のカラダをコントロールできることが大前提です。
ですが、本人も先生も「どこまで動かしていいのかわからない怖さ」があります。
ここが、競技復帰のむずかしさです。
私も、昨日の指導だけで、本人に伝わっているとは思わないし、
これから長い目で動作の確認をしていかないと、再発の可能性もあります。
どこまでそのことをお伝えできたかわかりませんが・・・
せっかくのご縁なので、遠慮なく呼んでもらえたらいいなと思います。
先生が呟かれた一言が心に響きました。
「いい能力を持った選手だと思うんですよ、でも私が焦っていたのでしょうね、こんな事になってしまって本当に申し訳なくて。」
素直な思いを、伝えて頂いて
競技力向上と健康のバランスの難しさを改めて感じます。
その為に、私達トレーナーという役割がいるのですが、まだまだそのように認識して頂くには活動や実績が足りないのでしょうね。。。黒子の立場なので決して目立ちはしないのですが、担う役割は大きいです。
どう、認識を広めようかなぁ…
地道にコツコツ、やるしかないですね!
「捻った記憶はないけれど、練習後に足首が痛む」
「捻挫してアイシングをしたけれど、それからどうしてあげたらいいのか?」
「腰痛があるのだが、成長期の子供は整骨院などに連れて行ってもいいのか?」
「病院に連れて行った方がいいのか?整骨院などがいいのか?」
我が子が、痛みを訴える。
ささいな疑問でも、いざとなると、不安に感じたり、どう対応してあげたらいいのか、
何を選択したらいいのかわからない。
親としては、悩むところですよね。
私も、小学生の頃から、痛みを訴えて親を悩ませていた一人です。
中学生に至っては、腰痛で悩まされ、
高校でとうとう、ヘルニアの診断で入院。
なぜ、痛みが出たのかわからないけど、痛いと訴える。
「いい」と聞けば、母は私を治療に連れて行ってくれました。
今考えると・・・本当に親に迷惑かけてきたなあ・・・という思いです。
昨日は、以前からご相談を受けていたジュニア選手のもとを尋ねました。
診断は、「腰椎分離症」。いわゆる腰の骨に骨折の形跡がみられる
成長期特有のスポーツ障害の一つです。
ご連絡いただいたのは、その選手を指導されている先生から。
先生自身も、ネットで調べたり、整形外科での診断と指示に従われながら・・・
でも、「どうしたらいいのか、自分では対応できない」という判断でご相談いただいていました。
安静期間を経て、痛みもほぼ解消されていたようなので、
動作の確認をしながら、原因をみつけて、選手本人が出来る事を一緒にやってみました。
観ていて、怖かったかもしれませんね・・・今まで安静にしていた子がストレッチングでかなり身体を動かしていたので。。
でも、そのレベルで身体を動かせないと、競技でかかる負担はもっとですから・・・
痛みなく、自分のカラダをコントロールできることが大前提です。
ですが、本人も先生も「どこまで動かしていいのかわからない怖さ」があります。
ここが、競技復帰のむずかしさです。
私も、昨日の指導だけで、本人に伝わっているとは思わないし、
これから長い目で動作の確認をしていかないと、再発の可能性もあります。
どこまでそのことをお伝えできたかわかりませんが・・・
せっかくのご縁なので、遠慮なく呼んでもらえたらいいなと思います。
先生が呟かれた一言が心に響きました。
「いい能力を持った選手だと思うんですよ、でも私が焦っていたのでしょうね、こんな事になってしまって本当に申し訳なくて。」
素直な思いを、伝えて頂いて
競技力向上と健康のバランスの難しさを改めて感じます。
その為に、私達トレーナーという役割がいるのですが、まだまだそのように認識して頂くには活動や実績が足りないのでしょうね。。。黒子の立場なので決して目立ちはしないのですが、担う役割は大きいです。
どう、認識を広めようかなぁ…
地道にコツコツ、やるしかないですね!
2015年01月13日
動作の視点
いつも久々の投稿です。
それでも、いつも誰かがブログを覗いてくれているんだ。。。ということに気づいて、
ちょっとたまには自分史がてら、書いてみようと思います。
年始に恒例の母校の合宿へ。チームに帯同しました。
この合宿は、鹿屋OB、OGが関わるチームのみ参加できる合宿です。
要するに、この時期にこんなところにいるってことは、
春高には出場できなかった、ということですが・・・
それでも九州県内でもベスト4に入るチームも。
みんな、それぞれ頑張っているんだなあ、と嬉しく思います。
私にとって、毎年年始は「リセット」です。
自分の1年間を、いやこれまでを 『師匠』 に再会することで
確認したり、修正したり、時には180°考え方を変えることになったり、
今まで積み重ねたものを捨てたり・・・
決して、「答え」を頂けるわけではありません。
ただ、みて学ぶ。言葉を聞いて、キーワードを拾う。
話を聞く中で、自分の視野の狭さに気づかされる。
そして、自分はまだまだだ、と思い知らされる。
でも、不思議なもんで・・・こうした経験は確実に考え方が変わり、
選手の動き一つ、見えてくるものが変わってくるのです。
「スパイク打つ時、肩が痛いんです」
「どういう動作で痛いの?」
「ええっと、こういう時・・・」
と、選手が痛みを探す、この一瞬の行動の中に原因が隠されています。
師匠だったら、どうみるのかな・・・?
こういう気持ちになりつつも、この思考は逆に、自分の迷いになります。
洋服のしわのより方や、肘の捻り方や、体幹の動き・・・いや、肩の軟部組織自体の問題か?
ありとあらゆる、自分の今までの引き出しを引っ張ってみるのですが、
いや、やっぱ、違うんじゃね?他に見方はないのかな?とか。
試しに、師匠に何か観るポイントがあるのか?と聞いてみたら・・・
「そんなのは、その時で違うから、なんともいえない。自分なりにいろいろみてみたら。」
・・・・だよね(笑)。
そんな、モヤモヤが本当はとっても大事なことだと思うことにしています。
卒業以来初めて、図書館に行きました。
「トレーナーになりたい」
そう思って、大学時代に自ら本で学んだ場所が、大学の図書館です。
ここには、膨大な数の体育に関する本があります。
私にとっては、宝の山です。

改めて、沢山の本を眺めながら、自分はどうしたいのだろう?とふと思いました。
答えは、これまた何も見つからなかったけど、
今、自分がやるべきことは、ここで書物をあさることではなく、
選手をしっかりと向き合うことだ、ということは分かりました。
師匠には、ほど遠いけれど、
来年、もしまたお会いできるならば、もう少し成長している姿を見せたいな。
今年も、また1年が始まりました。
頑張ろう。

それでも、いつも誰かがブログを覗いてくれているんだ。。。ということに気づいて、
ちょっとたまには自分史がてら、書いてみようと思います。
年始に恒例の母校の合宿へ。チームに帯同しました。
この合宿は、鹿屋OB、OGが関わるチームのみ参加できる合宿です。
要するに、この時期にこんなところにいるってことは、
春高には出場できなかった、ということですが・・・
それでも九州県内でもベスト4に入るチームも。
みんな、それぞれ頑張っているんだなあ、と嬉しく思います。
私にとって、毎年年始は「リセット」です。
自分の1年間を、いやこれまでを 『師匠』 に再会することで
確認したり、修正したり、時には180°考え方を変えることになったり、
今まで積み重ねたものを捨てたり・・・
決して、「答え」を頂けるわけではありません。
ただ、みて学ぶ。言葉を聞いて、キーワードを拾う。
話を聞く中で、自分の視野の狭さに気づかされる。
そして、自分はまだまだだ、と思い知らされる。
でも、不思議なもんで・・・こうした経験は確実に考え方が変わり、
選手の動き一つ、見えてくるものが変わってくるのです。
「スパイク打つ時、肩が痛いんです」
「どういう動作で痛いの?」
「ええっと、こういう時・・・」
と、選手が痛みを探す、この一瞬の行動の中に原因が隠されています。
師匠だったら、どうみるのかな・・・?
こういう気持ちになりつつも、この思考は逆に、自分の迷いになります。
洋服のしわのより方や、肘の捻り方や、体幹の動き・・・いや、肩の軟部組織自体の問題か?
ありとあらゆる、自分の今までの引き出しを引っ張ってみるのですが、
いや、やっぱ、違うんじゃね?他に見方はないのかな?とか。
試しに、師匠に何か観るポイントがあるのか?と聞いてみたら・・・
「そんなのは、その時で違うから、なんともいえない。自分なりにいろいろみてみたら。」
・・・・だよね(笑)。
そんな、モヤモヤが本当はとっても大事なことだと思うことにしています。
卒業以来初めて、図書館に行きました。
「トレーナーになりたい」
そう思って、大学時代に自ら本で学んだ場所が、大学の図書館です。
ここには、膨大な数の体育に関する本があります。
私にとっては、宝の山です。

改めて、沢山の本を眺めながら、自分はどうしたいのだろう?とふと思いました。
答えは、これまた何も見つからなかったけど、
今、自分がやるべきことは、ここで書物をあさることではなく、
選手をしっかりと向き合うことだ、ということは分かりました。
師匠には、ほど遠いけれど、
来年、もしまたお会いできるならば、もう少し成長している姿を見せたいな。
今年も、また1年が始まりました。
頑張ろう。

2014年11月19日
スポーツとは・・・
保有している資格の情報誌の巻頭のコラム。
このようなタイトルでした。

精神科医・香山リカさんのコラムです。
香山さん自身は、全くスポーツをされないそうなのですが、
精神科医という立場から、スポーツと向き合うと、また違った魅力がある、そうです。
奄美に来て、島がこんなにスポーツが盛んだなんて知りませんでした。
マスゲームも、あんなに速いムカデ競争も、俵担ぎも見たことなかった。
先日行われた市民体育祭も、今年3度目の出場でした。
夜な夜な行われる練習にびっくりしながらも、
それゆえの真剣勝負に毎年、開会式から楽しませてもらっています。
島の文化です。
スポーツも文化です。
しかしながら、スポーツもプロになると「楽しむ」とばかりは言ってられない。
プロでなくても、競技スポーツとして勝負に固着すると
小学生から高校生までも「楽しむ」の意味あいがそれぞれ変わってくる。
「勝負が全て、結果が全て」という人もいるでしょう。
「遊び半分でも楽しくやれればいい」という人もいるでしょう。
「そんな甘い考え方じゃ勝てない」という人も、
「そんなに厳しくしなくてもいいのでは」という人もいるでしょう。
スポーツに対する、捉え方、感じ方、関わり方はそれぞれなので
正解はないものだと思います。
このコラムでも書かれていました。
『スポーツはやはり楽しむためにあると思うんです。
以前、柔道界の暴力行為が明るみに出た際に、
山口香さん(元柔道選手・全日本柔道連盟女子強化委員)は
相談に来たナショナルチームの選手に対して
「あなた達は何のために柔道をしているの?自立した人間になるためでしょう?」
とおっしゃったという報道を耳にし、いたく感銘しました。』
そして、続けて・・・
『スポーツは、できなかったことができるようになったとか、自分はここまで頑張れたとか、
もっと言えばいい結果が出せたとか、そういう事から自分に自信をもたらしてくれるものです。
そして今回頑張れたから次に困難な場面に出くわしても大丈夫、といったほかに応用がきくような
自分への誇り、自信、尊厳を正しい形で身につけるという目的が究極にはあると思います。
もちろん時と場合に応じて勝利や記録にこだわる必要はありますが、
それらを天秤にかけたときは
人間として尊厳を持てるようになることの方が重要だと思います。』
捉え方は、人それぞれですが、
今の私は、このコラムに感銘を受けました。
少なくとも、私は「トレーナー」としてこのような考え方を持っています。
決して、日の丸をつけるような有名なトレーナーではありませんが
今の私は、やはり小学校から続けてきたスポーツ活動で培われた精神で支えられ
自信の持ち方や礼儀などスポーツ活動から学び、身につけてきたものです。
時には勝負にこだわり、不条理だと感じる中でスポーツした時もあります。
当時、どういう状況であれ、今振り返ると「苦しい状況で乗り越えられた」という体験は
大きな自信となっているのも事実です。
そこに、もう一つ、付け加えるなら、
「自分で、選択した道だから」
という、決定的な裏付けがあるからです。
しかしながら、今思うのは・・・決して自分の決断だけではなく、
” そう思えるように仕向けてくれた ” 指導者や私の両親の教育だと、感謝しています。
私を指導して下さった先生方は、
どれだけ怒っても、私という人間の「尊厳」を傷つけるような言動はなかった。
私も、現在、学生から年配の方々まで幅広く指導する場があります。
これだけは、肝に銘じて
スポーツを通じてカラダを動かす楽しさ、素晴らしさ、大切さを伝えていこうと思います。
このようなタイトルでした。

精神科医・香山リカさんのコラムです。
香山さん自身は、全くスポーツをされないそうなのですが、
精神科医という立場から、スポーツと向き合うと、また違った魅力がある、そうです。
奄美に来て、島がこんなにスポーツが盛んだなんて知りませんでした。
マスゲームも、あんなに速いムカデ競争も、俵担ぎも見たことなかった。
先日行われた市民体育祭も、今年3度目の出場でした。
夜な夜な行われる練習にびっくりしながらも、
それゆえの真剣勝負に毎年、開会式から楽しませてもらっています。
島の文化です。
スポーツも文化です。
しかしながら、スポーツもプロになると「楽しむ」とばかりは言ってられない。
プロでなくても、競技スポーツとして勝負に固着すると
小学生から高校生までも「楽しむ」の意味あいがそれぞれ変わってくる。
「勝負が全て、結果が全て」という人もいるでしょう。
「遊び半分でも楽しくやれればいい」という人もいるでしょう。
「そんな甘い考え方じゃ勝てない」という人も、
「そんなに厳しくしなくてもいいのでは」という人もいるでしょう。
スポーツに対する、捉え方、感じ方、関わり方はそれぞれなので
正解はないものだと思います。
このコラムでも書かれていました。
『スポーツはやはり楽しむためにあると思うんです。
以前、柔道界の暴力行為が明るみに出た際に、
山口香さん(元柔道選手・全日本柔道連盟女子強化委員)は
相談に来たナショナルチームの選手に対して
「あなた達は何のために柔道をしているの?自立した人間になるためでしょう?」
とおっしゃったという報道を耳にし、いたく感銘しました。』
そして、続けて・・・
『スポーツは、できなかったことができるようになったとか、自分はここまで頑張れたとか、
もっと言えばいい結果が出せたとか、そういう事から自分に自信をもたらしてくれるものです。
そして今回頑張れたから次に困難な場面に出くわしても大丈夫、といったほかに応用がきくような
自分への誇り、自信、尊厳を正しい形で身につけるという目的が究極にはあると思います。
もちろん時と場合に応じて勝利や記録にこだわる必要はありますが、
それらを天秤にかけたときは
人間として尊厳を持てるようになることの方が重要だと思います。』
捉え方は、人それぞれですが、
今の私は、このコラムに感銘を受けました。
少なくとも、私は「トレーナー」としてこのような考え方を持っています。
決して、日の丸をつけるような有名なトレーナーではありませんが
今の私は、やはり小学校から続けてきたスポーツ活動で培われた精神で支えられ
自信の持ち方や礼儀などスポーツ活動から学び、身につけてきたものです。
時には勝負にこだわり、不条理だと感じる中でスポーツした時もあります。
当時、どういう状況であれ、今振り返ると「苦しい状況で乗り越えられた」という体験は
大きな自信となっているのも事実です。
そこに、もう一つ、付け加えるなら、
「自分で、選択した道だから」
という、決定的な裏付けがあるからです。
しかしながら、今思うのは・・・決して自分の決断だけではなく、
” そう思えるように仕向けてくれた ” 指導者や私の両親の教育だと、感謝しています。
私を指導して下さった先生方は、
どれだけ怒っても、私という人間の「尊厳」を傷つけるような言動はなかった。
私も、現在、学生から年配の方々まで幅広く指導する場があります。
これだけは、肝に銘じて
スポーツを通じてカラダを動かす楽しさ、素晴らしさ、大切さを伝えていこうと思います。
2014年11月18日
第3回ASAスポーツ講習会終了!
先週の土曜日に朝日小体育館で行った
「第3回ASAスポーツ講習会」
最終的には定員を超えて34名の受講者の方々を迎えて、
無事終了しました!

こんなに集まっていただけるとは、正直思わなかったのでびっくり・・・
ありがとうございました!
しかも、今日の奄美新聞に、講習の様子がなんと「カラー写真」で掲載!

ありがとうございます~!感謝です!
内容は「アスレティックリハビリテーション」。
主に腰痛が起きた場合、足関節捻挫が起きた場合に
復帰までどういうプロセスで選手を導くか・・・というテーマのもと
ストレッチングや腹筋・背筋の実技と
足関節捻挫、復帰への最終チェックともなるドリルを実技として行いました。
前回の反省を生かし・・・
子供達には「”えっと・・・”は使わない!」とメモ書きまで貼られ(笑)
なるべく実技に時間をとれるように作ったスライドを半分以上捨てて
準備していた・・・にもかかわらず・・・
必死すぎて、記憶がない・・・⇒⇒ 時間が思うように使えず、やはり反省。。。
どよよ~ん・・・
余裕もないので、せっかく来てくださった方々へ、挨拶もできず、さらに反省。
・・・・全力を使い果たして、いつもこのザマですが、
受講者の方々からの温かいお言葉を沢山いただき・・・
無事終われて、良かったなあと、思うところです。
内容を絞ればいい事は分かっているんですが
まだまだ軌道に乗らない講習会・・・来る人にとっては
どうせ行くなら、いろんな情報がもらえると嬉しいじゃないですか!
今まで、ケガしてもほったらかしだったり、何していいのかわからなかった方々が、
ちょっとでも、「へーっ!こんなことやるんだ!」って思ってもらったり、
「よくやるトレーニングだけど、こういうところ意識するんだ」とか、少しでも感じてもらえれば
私は嬉しく思います。
「ケガを予防」する事が一番ですが、
スポーツ現場では、必ず大なり小なり、ケガが起こるんです。
「ケガは起こるもの」
ケガなく、その日の活動を終われたら、ホント感謝です。
丈夫な身体をくれたお父さん、お母さん。安全な環境で活動させてくれた監督さんに
感謝です。
そういう風に思っておけば、選手1人1人が、本当に大切に思えてくるんです。
だからこそ、ケガが起きてしまった時・・・その大切な1人の子の為に何ができるか?
「素早く、的確な応急処置」
だったり、
「復帰までのサポート」
だったり。
トレーナーは、まず第一にそのために現場で活動します。
いわば、これが専門職なので、私達は 『出来て当たり前』ですが・・・
トレーナーがいる環境でスポーツ活動すること自体が、ごくごく稀なことです。
だからこそ、ある程度の「ケガに対する知識」は持っておいて損はないし、
ケガして、目の前真っ暗、不安な選手にとって、
差し伸べられた手は本当に温かなものとなるでしょう。
全ての内容を講習では伝えられませんでしたが
私はその「思い」だけは、今回精一杯、伝えられたと思っています。
本当は受講してくださった方、1人1人に感謝の気持ちを伝えたいところですが
この場をもって、感謝申し上げます。
そしていつも私のわがままに付き合い、快く準備してくださるASAスタッフ並びに
オフィシャルトレーナーの皆さんにも感謝いたします。
もっと、自分自身が工夫と経験を積み、よりよい情報提供ができるよう
これからも頑張ります。
「第3回ASAスポーツ講習会」
最終的には定員を超えて34名の受講者の方々を迎えて、
無事終了しました!

こんなに集まっていただけるとは、正直思わなかったのでびっくり・・・
ありがとうございました!
しかも、今日の奄美新聞に、講習の様子がなんと「カラー写真」で掲載!

ありがとうございます~!感謝です!
内容は「アスレティックリハビリテーション」。
主に腰痛が起きた場合、足関節捻挫が起きた場合に
復帰までどういうプロセスで選手を導くか・・・というテーマのもと
ストレッチングや腹筋・背筋の実技と
足関節捻挫、復帰への最終チェックともなるドリルを実技として行いました。
前回の反省を生かし・・・
子供達には「”えっと・・・”は使わない!」とメモ書きまで貼られ(笑)
なるべく実技に時間をとれるように作ったスライドを半分以上捨てて
準備していた・・・にもかかわらず・・・
必死すぎて、記憶がない・・・⇒⇒ 時間が思うように使えず、やはり反省。。。
どよよ~ん・・・
余裕もないので、せっかく来てくださった方々へ、挨拶もできず、さらに反省。
・・・・全力を使い果たして、いつもこのザマですが、
受講者の方々からの温かいお言葉を沢山いただき・・・
無事終われて、良かったなあと、思うところです。
内容を絞ればいい事は分かっているんですが
まだまだ軌道に乗らない講習会・・・来る人にとっては
どうせ行くなら、いろんな情報がもらえると嬉しいじゃないですか!
今まで、ケガしてもほったらかしだったり、何していいのかわからなかった方々が、
ちょっとでも、「へーっ!こんなことやるんだ!」って思ってもらったり、
「よくやるトレーニングだけど、こういうところ意識するんだ」とか、少しでも感じてもらえれば
私は嬉しく思います。
「ケガを予防」する事が一番ですが、
スポーツ現場では、必ず大なり小なり、ケガが起こるんです。
「ケガは起こるもの」
ケガなく、その日の活動を終われたら、ホント感謝です。
丈夫な身体をくれたお父さん、お母さん。安全な環境で活動させてくれた監督さんに
感謝です。
そういう風に思っておけば、選手1人1人が、本当に大切に思えてくるんです。
だからこそ、ケガが起きてしまった時・・・その大切な1人の子の為に何ができるか?
「素早く、的確な応急処置」
だったり、
「復帰までのサポート」
だったり。
トレーナーは、まず第一にそのために現場で活動します。
いわば、これが専門職なので、私達は 『出来て当たり前』ですが・・・
トレーナーがいる環境でスポーツ活動すること自体が、ごくごく稀なことです。
だからこそ、ある程度の「ケガに対する知識」は持っておいて損はないし、
ケガして、目の前真っ暗、不安な選手にとって、
差し伸べられた手は本当に温かなものとなるでしょう。
全ての内容を講習では伝えられませんでしたが
私はその「思い」だけは、今回精一杯、伝えられたと思っています。
本当は受講してくださった方、1人1人に感謝の気持ちを伝えたいところですが
この場をもって、感謝申し上げます。
そしていつも私のわがままに付き合い、快く準備してくださるASAスタッフ並びに
オフィシャルトレーナーの皆さんにも感謝いたします。
もっと、自分自身が工夫と経験を積み、よりよい情報提供ができるよう
これからも頑張ります。
2014年11月14日
第3回ASA講習会のお知らせ
急に寒くなりました・・・っても11月半ば、ですもんね。
風が強くて、あ~奄美の冬ってこんなんだったなあって思う今日この頃です。
9月のテーピング講習会から早2ヶ月・・・
なんとか今年度3回目のASA講習会、明日15日開催します!

新聞各社でも案内を掲載されています(^^)

今回は、聞きなれない言葉かと思います。
テーマは 『アスレティックリハビリテーション』 です。
これは、病院のリハビリ室で行う物理療法や理学療法士のもとで受ける施術・・・
いわゆる『メディカルリハビリテーション』から
医師の指示のもと、スポーツ現場で、スポーツ復帰にむけて
トレーナーが指導するトレーニングプログラムを施行するリハビリテーションのことです。
つまり・・・
ケガからの早期復帰を目的に、再発予防のみならず、ケガをする前よりももっといいカラダの状態で
復帰を目指す、スポーツ現場で行う準備のことを指します。
このアスレティックリハビリテーションは、アスレティックトレーナーの3つの大きな役割の一つです。
(その他・・・応急処置とコンディショニング)
ケガの種類でメニューの内容や危機管理は当然変わってきますが、
今回はスポーツ現場で最も多い外傷と障害である
「足関節内反捻挫」と「腰部疾患」
をとりあげてみます。
この二つのケガには関連性があります。
腰痛・・・つまり体幹部の安定性の欠如から発症する痛みは、
動きの不安定性を生み、やがて末端部(膝・足首や肩・肘・手首など)に負担が強いられます。
なので、捻挫の完治を待つ間に、どんどん体幹トレーニングはすべき!
足首痛くても・・・体幹部は元気でしょ?
腰痛も、スポーツが原因で起こるものも様々な症状があります。
その改善の大きな要因は、体幹部の強化やそれをとりまく各関節の可動範囲を広げることです。
・・・語り始めればキリがない!
ホント、私大好きなんです、この仕事が・・・(笑)
明日も2時間で、実技をメインにやりたいので、あまりしゃべらないようにします!
明日13時~あまみFMの「あまスポディ!ラックス」でも講習会について語ってます。

この番組、実は準レギュラーという名の、ゲスト穴埋め役を担ってます(笑)。
誰も投稿はしてきませんが、
「教えて、アヤさん!」というコーナーがひっそりと存在します(汗)。
ちょっとした疑問・・・ケガのことやトレーニングのこと、是非投稿してみてください!
・・・というわけで、ブログをわざわざ気にして下さった方で、
明日の夜、暇な方は是非どうぞ。
文字では表せない感覚や表現を、誠心誠意、お伝えします。
「百聞は一見にしかず」
大きな口は叩けませんが・・・頑張ってみます!
風が強くて、あ~奄美の冬ってこんなんだったなあって思う今日この頃です。
9月のテーピング講習会から早2ヶ月・・・
なんとか今年度3回目のASA講習会、明日15日開催します!

新聞各社でも案内を掲載されています(^^)

今回は、聞きなれない言葉かと思います。
テーマは 『アスレティックリハビリテーション』 です。
これは、病院のリハビリ室で行う物理療法や理学療法士のもとで受ける施術・・・
いわゆる『メディカルリハビリテーション』から
医師の指示のもと、スポーツ現場で、スポーツ復帰にむけて
トレーナーが指導するトレーニングプログラムを施行するリハビリテーションのことです。
つまり・・・
ケガからの早期復帰を目的に、再発予防のみならず、ケガをする前よりももっといいカラダの状態で
復帰を目指す、スポーツ現場で行う準備のことを指します。
このアスレティックリハビリテーションは、アスレティックトレーナーの3つの大きな役割の一つです。
(その他・・・応急処置とコンディショニング)
ケガの種類でメニューの内容や危機管理は当然変わってきますが、
今回はスポーツ現場で最も多い外傷と障害である
「足関節内反捻挫」と「腰部疾患」
をとりあげてみます。
この二つのケガには関連性があります。
腰痛・・・つまり体幹部の安定性の欠如から発症する痛みは、
動きの不安定性を生み、やがて末端部(膝・足首や肩・肘・手首など)に負担が強いられます。
なので、捻挫の完治を待つ間に、どんどん体幹トレーニングはすべき!
足首痛くても・・・体幹部は元気でしょ?
腰痛も、スポーツが原因で起こるものも様々な症状があります。
その改善の大きな要因は、体幹部の強化やそれをとりまく各関節の可動範囲を広げることです。
・・・語り始めればキリがない!
ホント、私大好きなんです、この仕事が・・・(笑)
明日も2時間で、実技をメインにやりたいので、あまりしゃべらないようにします!
明日13時~あまみFMの「あまスポディ!ラックス」でも講習会について語ってます。

この番組、実は準レギュラーという名の、ゲスト穴埋め役を担ってます(笑)。
誰も投稿はしてきませんが、
「教えて、アヤさん!」というコーナーがひっそりと存在します(汗)。
ちょっとした疑問・・・ケガのことやトレーニングのこと、是非投稿してみてください!
・・・というわけで、ブログをわざわざ気にして下さった方で、
明日の夜、暇な方は是非どうぞ。
文字では表せない感覚や表現を、誠心誠意、お伝えします。
「百聞は一見にしかず」
大きな口は叩けませんが・・・頑張ってみます!
2014年11月03日
越える
春高予選大会が行われています。
昨日の試合、国分中央に2-0で敗退、
今回もベスト16止まりの結果に終わったようです。
試合は観戦していませんが、チームの練習の雰囲気から・・・
きっと、力を尽くしての結果なのだと思います。
一つ評価できることは、
県大会に行っても、実力が出せるようになったということ。
昨年までは、力を発揮する以前に、自分たちで勝手にかけた
プレッシャーに押しつぶされていましたが
それを今年のチームは越えていることは
今までからすると大きな成長。
世の中から見れば、「結果が全て」です。
結果としては、今回も越えられなかった。
しかしながら最大の「課題」に向き合える準備は整ったようです。

トレーナーとして、再三この場で
チームとの関わりについて呟いてきていますが
私にとってこの半年間は模索の時でした。
それは今も変わりませんが、
チーム同様、花開くことを願いつつ
じっと根を張り、幹を太くして準備していく時期だと思っています。
そんな私の唯一の息抜きと楽しみは朝の連ドラ(笑)。
先週のエリーの言葉が、心に沁みました。
「人生はアドベンチャー」
これは、エリー役のシャーロット・ケイトさんが実際に呟いた言葉を
エリーのセリフとして使ったと知りました。
私も、自分がどうこれから人生を歩んでいくのかわからないけれど、
不安ではなく、分からないからこそワクワクします。
常識を超えるような、ワクワクする未来に挑んでいきたい。
この部旗の言葉のように、今の自分を越え続けていきたいと思います。
きっと・・・それが私がチームへ
本当のサポーターとなる近道のような気がします。
昨日の試合、国分中央に2-0で敗退、
今回もベスト16止まりの結果に終わったようです。
試合は観戦していませんが、チームの練習の雰囲気から・・・
きっと、力を尽くしての結果なのだと思います。
一つ評価できることは、
県大会に行っても、実力が出せるようになったということ。
昨年までは、力を発揮する以前に、自分たちで勝手にかけた
プレッシャーに押しつぶされていましたが
それを今年のチームは越えていることは
今までからすると大きな成長。
世の中から見れば、「結果が全て」です。
結果としては、今回も越えられなかった。
しかしながら最大の「課題」に向き合える準備は整ったようです。

トレーナーとして、再三この場で
チームとの関わりについて呟いてきていますが
私にとってこの半年間は模索の時でした。
それは今も変わりませんが、
チーム同様、花開くことを願いつつ
じっと根を張り、幹を太くして準備していく時期だと思っています。
そんな私の唯一の息抜きと楽しみは朝の連ドラ(笑)。
先週のエリーの言葉が、心に沁みました。
「人生はアドベンチャー」
これは、エリー役のシャーロット・ケイトさんが実際に呟いた言葉を
エリーのセリフとして使ったと知りました。
私も、自分がどうこれから人生を歩んでいくのかわからないけれど、
不安ではなく、分からないからこそワクワクします。
常識を超えるような、ワクワクする未来に挑んでいきたい。
この部旗の言葉のように、今の自分を越え続けていきたいと思います。
きっと・・・それが私がチームへ
本当のサポーターとなる近道のような気がします。
2014年09月07日
第2回ASAテーピング講習会
よく間違えられますが~
ASA奄美スポーツアカデミーの職員ではありませんよ。
ASAオフィシャルトレーナーとして
「スポーツ講習会」を担当しております!
第2回ASAスポーツ講習会を9月22日(月)19:00~21:00
奄美市民文化センター 第一会議室で・・・
開催します!

今回も、前回に引き続き「テーピング」で挑みます!
トレーナーの代名詞=「テーピング」ですからねっ(たぶん)。
そして、今回は・・・平日の夜にしてみました!
意外と・・・日曜日にわざわざ足を運ぶのは、面倒かな?と思って・・・。
今回は 『 足関節と膝関節 』
内容は・・・
1 テーピングの目的とその効果
2 足関節内反捻挫に対するテーピング
・” 内反捻挫 ” のメカニズム(受傷機転)
・足関節捻挫が起こった時の対処法(RICE処置)
・捻挫受傷後の対応と、スポーツ復帰までのプロセス(←おまけなのでごくごく簡単に・・)
3 足底部のテーピング
・Q-アングルとは?
・レッグヒールアングルとは?
・スクリューホームムーブメント
・足部回内位に対するアーチのテーピング
4 膝の障害に対するキネシオテープの活用
・” 外傷 ”と” 障害 ”の違い
・ジャンパー膝/オスグッドシュラッター病
・腸脛靭帯炎
・鵞足炎
・各障害に対する負担軽減を目的としたテーピングの方法
↑ 以上・・・今のところやりたい!と思って準備しているところです。
盛りだくさんすぎて(笑)
こんなに出来るかわからないのが正直なところですが・・・
ま、いいんじゃないですか~こんな講習会あっても!
来られる側の立場からすれば、いっぱい学べたらお得ですもんね(^-^)
こんな感じで、やってみようと思ってます。
また、ボチボチ宣伝しますね~。
なんで、こんなに膨らんでしまっているのか・・・
裏話的なものも、このブログで呟いてみようかと思ってます。
「面白そう」と思ったら、ご面倒ですが、
私でもASAでもいいのでご予約下さいね。
このブログのサイドバーの「メッセージ」
または、私に直接ご連絡いただくか・・・
ASAホームページhttp://amami-sa.com/の「お問い合わせ」のメールから申し込むか・・・
電話 0997-54-8687 へ。
よろしくお願いします!
ASA奄美スポーツアカデミーの職員ではありませんよ。
ASAオフィシャルトレーナーとして
「スポーツ講習会」を担当しております!
第2回ASAスポーツ講習会を9月22日(月)19:00~21:00
奄美市民文化センター 第一会議室で・・・
開催します!

今回も、前回に引き続き「テーピング」で挑みます!
トレーナーの代名詞=「テーピング」ですからねっ(たぶん)。
そして、今回は・・・平日の夜にしてみました!
意外と・・・日曜日にわざわざ足を運ぶのは、面倒かな?と思って・・・。
今回は 『 足関節と膝関節 』
内容は・・・
1 テーピングの目的とその効果
2 足関節内反捻挫に対するテーピング
・” 内反捻挫 ” のメカニズム(受傷機転)
・足関節捻挫が起こった時の対処法(RICE処置)
・捻挫受傷後の対応と、スポーツ復帰までのプロセス(←おまけなのでごくごく簡単に・・)
3 足底部のテーピング
・Q-アングルとは?
・レッグヒールアングルとは?
・スクリューホームムーブメント
・足部回内位に対するアーチのテーピング
4 膝の障害に対するキネシオテープの活用
・” 外傷 ”と” 障害 ”の違い
・ジャンパー膝/オスグッドシュラッター病
・腸脛靭帯炎
・鵞足炎
・各障害に対する負担軽減を目的としたテーピングの方法
↑ 以上・・・今のところやりたい!と思って準備しているところです。
盛りだくさんすぎて(笑)
こんなに出来るかわからないのが正直なところですが・・・
ま、いいんじゃないですか~こんな講習会あっても!
来られる側の立場からすれば、いっぱい学べたらお得ですもんね(^-^)
こんな感じで、やってみようと思ってます。
また、ボチボチ宣伝しますね~。
なんで、こんなに膨らんでしまっているのか・・・
裏話的なものも、このブログで呟いてみようかと思ってます。
「面白そう」と思ったら、ご面倒ですが、
私でもASAでもいいのでご予約下さいね。
このブログのサイドバーの「メッセージ」
または、私に直接ご連絡いただくか・・・
ASAホームページhttp://amami-sa.com/の「お問い合わせ」のメールから申し込むか・・・
電話 0997-54-8687 へ。
よろしくお願いします!
2014年06月11日
プレ講習会、実施。
6月15日のテーピング講習会の前に…
ASAのスタッフさん達に向けて
プレ講習会をさせて頂きました!
講習会は度々やらせて頂いてますが、
いつまで経っても慣れないし、
こちらが準備していても、
相手あっての事なので、やっぱり難しい。
もちろん、ASAのスタッフさんの勉強にもなるかもしれませんが、私の勉強にもなる場がこの「プレ講習会」です。
3人相手でも、一つの説明で違う捉え方をされる事もあるし、
「うまく伝わってないなぁ〜」と感じられるのも、やっぱり実技講習ならでは。
自分のイメージと、ちょっと違う部分もあって、今日は反省とヒラメキの時間となりました。

せっかく、時間とお金をかけて、来て下さる皆さんに、
いいモノ、確実な情報をお伝えしたい。
今回のテーピングの巻き方は
アスレティックトレーナーの実技試験でも採用されている
昔から変わらない、スタンダードな巻き方です。言わば、基本中の基本。
私も、初めてのテーピング講習で学び、それから何度も参考にしてきたモノです。
今は、自己流にかなりなっているんだなぁ〜と感じつつ、
「基本」の大切さを改めて実感します。
今回は、この「基本」を
より分かりやすく、お伝えする事に挑戦しようと思います!
空きはまだまだありますよ。
どうぞ、お時間ある方は、
今、皆さんの「スポーツ環境の整備の一環」として、
「テーピングの面白さ」を体験しに来て下さい!
ASAのスタッフさん達に向けて
プレ講習会をさせて頂きました!
講習会は度々やらせて頂いてますが、
いつまで経っても慣れないし、
こちらが準備していても、
相手あっての事なので、やっぱり難しい。
もちろん、ASAのスタッフさんの勉強にもなるかもしれませんが、私の勉強にもなる場がこの「プレ講習会」です。
3人相手でも、一つの説明で違う捉え方をされる事もあるし、
「うまく伝わってないなぁ〜」と感じられるのも、やっぱり実技講習ならでは。
自分のイメージと、ちょっと違う部分もあって、今日は反省とヒラメキの時間となりました。

せっかく、時間とお金をかけて、来て下さる皆さんに、
いいモノ、確実な情報をお伝えしたい。
今回のテーピングの巻き方は
アスレティックトレーナーの実技試験でも採用されている
昔から変わらない、スタンダードな巻き方です。言わば、基本中の基本。
私も、初めてのテーピング講習で学び、それから何度も参考にしてきたモノです。
今は、自己流にかなりなっているんだなぁ〜と感じつつ、
「基本」の大切さを改めて実感します。
今回は、この「基本」を
より分かりやすく、お伝えする事に挑戦しようと思います!
空きはまだまだありますよ。
どうぞ、お時間ある方は、
今、皆さんの「スポーツ環境の整備の一環」として、
「テーピングの面白さ」を体験しに来て下さい!
2014年05月27日
みんなでウォームアップ!Part Ⅱ
社会人バレーの練習、週2回あります。
昨日は大高で練習試合でした。
・・・なので、いつもより私も早めに体育館に行ったつもりなのですが、
隣のチームがそれよりも早く来てネット張っている?!
「どうしたんですか?エライ早くないですか?」と聞く方も失礼な話ですが(笑)。
「いや、どうしたら、みんな練習に早く来るかなあって考えて・・・
” 早く来たら、(私の)ストレッチの体操が出来るよ!” って言ったらみんな来てくれた」
って・・・笑ってしまいました。
昨日は練習ゲームの相手チームも含め、結構な人数での
ちょっとした「ウォームアップ講習会」・・・でした。(10分程度ですけど。)
うちのメンバー達は、私のせいで他のチームに周りを囲まれてしまい、ちょっと申し訳なかったな・・・(笑)。
まあ、でも!有難いことですよ!
皆さん、やっぱり感じてらっしゃるってことですよね、
「きちんとストレッチングを取り入れることは大事だ」ってことを・・・
ちょっとづつでも、みなさんが「ケガを予防する」意識を高めて下さったら、嬉しいですね。
昨日は大高で練習試合でした。
・・・なので、いつもより私も早めに体育館に行ったつもりなのですが、
隣のチームがそれよりも早く来てネット張っている?!
「どうしたんですか?エライ早くないですか?」と聞く方も失礼な話ですが(笑)。
「いや、どうしたら、みんな練習に早く来るかなあって考えて・・・
” 早く来たら、(私の)ストレッチの体操が出来るよ!” って言ったらみんな来てくれた」
って・・・笑ってしまいました。
昨日は練習ゲームの相手チームも含め、結構な人数での
ちょっとした「ウォームアップ講習会」・・・でした。(10分程度ですけど。)
うちのメンバー達は、私のせいで他のチームに周りを囲まれてしまい、ちょっと申し訳なかったな・・・(笑)。
まあ、でも!有難いことですよ!
皆さん、やっぱり感じてらっしゃるってことですよね、
「きちんとストレッチングを取り入れることは大事だ」ってことを・・・
ちょっとづつでも、みなさんが「ケガを予防する」意識を高めて下さったら、嬉しいですね。
2014年05月26日
気になるCM・・・
初めてみたとき・・・「うわっ、気持ちワルっ!」
って思わずつぶやいてしまった画。
あえて載せてみます・・・。

でも・・・見れば見るほど「こんだけ、股関節が動けば面白いな。」
と・・・思う私はオカシイか。
あの「奇妙な」姿勢を目指すわけではないけど、プロのダンサーはやはりあれくらいの身体レベルがあるから
しなやかな動きができるんでしょうね。
最近、「Core Conditioning」と称してストレッチングや自重負荷のトレーニングを
どちらかというと、今は一般の方をメインに指導しているのですが・・・
意外とみなさん、「柔らかい」んですね~。
カラダが硬いと思い込んでいる人の中には、カラダの使い方「それしか知らない」人もいるし、
実際本当に硬い人もいらっしゃるのですが、
どこが原因で「硬い」のか、少し気づくと、反応が面白い、というか・・・
日常から負荷をかけて過ごしてらっしゃる・・・いわゆる「アスリート」はごくごく稀な人種ですが、
そういう人は特に、股関節からしっかりと緩めて、
「しなやかさと強さを持つ、筋肉の質」を獲得できたらいいなあと思います。
本当にトレーニングを積んだ人、カラダをめいいっぱい使って動く人の筋肉は
非常にしなやか。
特に、ふくらはぎの筋肉を触ると、その選手の持つ能力がだいたい把握できるほどです。
「ブヨブヨしている」柔らかさとはちょっと異なるのであしからず・・・(苦)。
世の中的には、「筋肉がついているから硬い」と思われがち・・・いや実際そういう事で悩んでいる
人も多い。
また、「筋肉が脂肪に変わってしまって・・・・」とか。だから筋肉はつけたくない、とか・・・
意外と昔スポーツしてきた人が、そういう事を呟いてしまうようですね・・・。
女性の永遠のテーマだと思います。
でも、これは事実なんでしょうか?科学的な知見から証明されているのかなあ?
ちょっと調べてみよう!
こういうこと・・・社会人選手でも、高校生でも、一般女性でも、子育て中のお母さんでも、
みなさん同じような事で悩んでらっしゃいますよ。
(こういう事はあっちのブログ・・Core Conditioning*COCO・・で取り上げますね。)
話、もどして・・・
私のお師匠がつぶやく言葉・・・
「人間のカラダは、筋膜で繋がってるから」
最初は「???」わかるようなわからないような言葉だったんですが、
最近、意味がよく分かります。そうなんです。
だから簡単にいえば、「股割りしっかりしましょう」「股関節の柔軟性高めましょう」というのはそういうことなんです。
股関節周りの、大きな筋膜が緩めば、筋膜の内側の筋肉が十分使えるようになる。
私は、これが様々なトレーニングを行う準備のスタートだと思って、今は信じてやっています。
「まず、個々が持っている能力を引き出す」
そのお手伝いを最優先でアプローチをかける。
まだまだ技術は足りませんが、私の目指すトレーナーのスタイルです。
でも、人によっては、違う方面からのアプローチも出来るんですよ~
「あいたたた・・・」とストレッチを無理やりするより、もっと確実な方法も、ある。
だから、目指すは ↑↑ の画。
ということで・・・(笑)。
チームの方も、いよいよ今週末が大会です。
が・・・
全く練習に行けてない。。でも、
私に必要がないって事は、チームがうまく回っていて、いいことだなって思います。
温かく見守りたいと思います♪
って思わずつぶやいてしまった画。
あえて載せてみます・・・。

でも・・・見れば見るほど「こんだけ、股関節が動けば面白いな。」
と・・・思う私はオカシイか。
あの「奇妙な」姿勢を目指すわけではないけど、プロのダンサーはやはりあれくらいの身体レベルがあるから
しなやかな動きができるんでしょうね。
最近、「Core Conditioning」と称してストレッチングや自重負荷のトレーニングを
どちらかというと、今は一般の方をメインに指導しているのですが・・・
意外とみなさん、「柔らかい」んですね~。
カラダが硬いと思い込んでいる人の中には、カラダの使い方「それしか知らない」人もいるし、
実際本当に硬い人もいらっしゃるのですが、
どこが原因で「硬い」のか、少し気づくと、反応が面白い、というか・・・
日常から負荷をかけて過ごしてらっしゃる・・・いわゆる「アスリート」はごくごく稀な人種ですが、
そういう人は特に、股関節からしっかりと緩めて、
「しなやかさと強さを持つ、筋肉の質」を獲得できたらいいなあと思います。
本当にトレーニングを積んだ人、カラダをめいいっぱい使って動く人の筋肉は
非常にしなやか。
特に、ふくらはぎの筋肉を触ると、その選手の持つ能力がだいたい把握できるほどです。
「ブヨブヨしている」柔らかさとはちょっと異なるのであしからず・・・(苦)。
世の中的には、「筋肉がついているから硬い」と思われがち・・・いや実際そういう事で悩んでいる
人も多い。
また、「筋肉が脂肪に変わってしまって・・・・」とか。だから筋肉はつけたくない、とか・・・
意外と昔スポーツしてきた人が、そういう事を呟いてしまうようですね・・・。
女性の永遠のテーマだと思います。
でも、これは事実なんでしょうか?科学的な知見から証明されているのかなあ?
ちょっと調べてみよう!
こういうこと・・・社会人選手でも、高校生でも、一般女性でも、子育て中のお母さんでも、
みなさん同じような事で悩んでらっしゃいますよ。
(こういう事はあっちのブログ・・Core Conditioning*COCO・・で取り上げますね。)
話、もどして・・・
私のお師匠がつぶやく言葉・・・
「人間のカラダは、筋膜で繋がってるから」
最初は「???」わかるようなわからないような言葉だったんですが、
最近、意味がよく分かります。そうなんです。
だから簡単にいえば、「股割りしっかりしましょう」「股関節の柔軟性高めましょう」というのはそういうことなんです。
股関節周りの、大きな筋膜が緩めば、筋膜の内側の筋肉が十分使えるようになる。
私は、これが様々なトレーニングを行う準備のスタートだと思って、今は信じてやっています。
「まず、個々が持っている能力を引き出す」
そのお手伝いを最優先でアプローチをかける。
まだまだ技術は足りませんが、私の目指すトレーナーのスタイルです。
でも、人によっては、違う方面からのアプローチも出来るんですよ~
「あいたたた・・・」とストレッチを無理やりするより、もっと確実な方法も、ある。
だから、目指すは ↑↑ の画。
ということで・・・(笑)。
チームの方も、いよいよ今週末が大会です。
が・・・
全く練習に行けてない。。でも、
私に必要がないって事は、チームがうまく回っていて、いいことだなって思います。
温かく見守りたいと思います♪
2014年05月24日
子どもとスポーツ
今日は一日、娘たちのバレーボール少年団の試合でした。
ボール拾いと審判と子ども達のお世話係の名目でボーっと
試合を眺めています。
特に「子ども達は当たり前のことが出来るように」ということで
ボトルから荷物の管理は全て子供だけで出来るように
親はフォローする流れができています。
前回の試合で、ボトルのお水がフロアに落ちていたら拭くように、と指示を出すと、
今日もやる子はやってくれていました。
今日はレギュラーの子たちが自分の使ったタオルを下の学年の子や
ベンチに投げるように渡していたので・・・一喝。
せっかく、タイムアウトごとにたたんできれいに渡してくれるタオルを、
使った後で無造作に渡すなんて!「ありがとう、これ、お願いね」という気持ちは
急いでいても忘れてはいけないと思うんですよね。それくらいは子供達にもわかるはずです。
そして、絶対、バレーに出ますもん。
まだまだこんな教育は続きます(笑)。
「トレーナー」として声をかけてくださる方もいらっしゃいました。
それは、大歓迎です。
「痛みを抱えている選手がいる」という相談を受けました。
時間がなかったのでその場で少しストレッチをする程度しか出来ませんでしたが、
その後、動いていた姿に原因がはっきりと出ていましたので、監督さんと少しやり取りを。
実際には、痛みの原因はその場でポンと出来ることではありません。
いつも観ている選手は別ですが・・・
時間がかかることだし、単純なことでもないことがほとんどなので、
やはり子供相手だと、大人の方とのコミュニケーションが非常に大切になってきます。
そう思えば・・・治療院で何かしてもらえる方が、簡単なのかもしれません。
もう一つは「体幹強化が必要?」というニュアンスの質問でした。
話を聞くと、体幹を安定させることを考えるよりも、自分とボールとの「空間認知」の方が
優先順位は先なのでは?という視点からの発想をお伝えしてみました。
これは、昨日の講演のテーマ「発育発達」の準備のためにいろいろと整理した事がきっかけです。
主人ともよく話しますが、「バレーボール」って、難しいんです。
宙に浮いているボールを、たたいたり、コントロールしたりするわけですから、
観るよりも、難しい。そして技術が多いのもバレーボールの特徴なので、
非常に技術練習に時間がかかる。
ですが、小学生のうちは神経系の発達が成人の80~100%に到達する時期ですから、
きちんと指導の順を追って、感覚的なものを伝えてあげると抜群の吸収力を見せるわけです。
上手な子は、動きのイメージを頭の中でうまく自分に置き換えて出来る子だと思います。
でも、努力次第、教え方次第できちんと伝わる子もいるんだと思います。
逆に言えば、そういう子を沢山育てられると、素敵だなあと思います。
ただ、バレーボールはチームスポーツなので、個に応じた指導に限界があることも確かかな?と思います。
難しいですね。。
でも、そうやって声をかけてくださったことで、正解ではないかもしれないけれど、
こういう目線の考え方から、その人なりの考え方がプラスされると、本当に面白いと思うんですよね。
もっと、他の方の意見が重なれば、発想は無限大。
私もこうやって考えさせてもらって、ヒラメキに繋がる。
有難いですね。
今日は試合後にキャプテンの娘が
「ママ、みんなでストレッチしといたから!」
観ましたよ、シャキシャキし切れないキャプテンは監督に怒られながら皆を動かしていたところを(笑)。
可哀そうに、私と似て全然気が回らないんです。ホントは、母親の私がしっかりしなきゃいけないんですよね・・・
ここ最近は、練習後に教えた「クーリングダウン」を続けてやってくれています。
ホント、ごくごく簡単なものを、動きを覚えたら、少しずつ増やして。
これ、やったからって勝てるか、と言われれば、そうじゃないんですけど・・・
やっぱり、こういうことを当たり前に出来ることも、大切なことだと私は思うんですよね。


ボール拾いと審判と子ども達のお世話係の名目でボーっと
試合を眺めています。
特に「子ども達は当たり前のことが出来るように」ということで
ボトルから荷物の管理は全て子供だけで出来るように
親はフォローする流れができています。
前回の試合で、ボトルのお水がフロアに落ちていたら拭くように、と指示を出すと、
今日もやる子はやってくれていました。
今日はレギュラーの子たちが自分の使ったタオルを下の学年の子や
ベンチに投げるように渡していたので・・・一喝。
せっかく、タイムアウトごとにたたんできれいに渡してくれるタオルを、
使った後で無造作に渡すなんて!「ありがとう、これ、お願いね」という気持ちは
急いでいても忘れてはいけないと思うんですよね。それくらいは子供達にもわかるはずです。
そして、絶対、バレーに出ますもん。
まだまだこんな教育は続きます(笑)。
「トレーナー」として声をかけてくださる方もいらっしゃいました。
それは、大歓迎です。
「痛みを抱えている選手がいる」という相談を受けました。
時間がなかったのでその場で少しストレッチをする程度しか出来ませんでしたが、
その後、動いていた姿に原因がはっきりと出ていましたので、監督さんと少しやり取りを。
実際には、痛みの原因はその場でポンと出来ることではありません。
いつも観ている選手は別ですが・・・
時間がかかることだし、単純なことでもないことがほとんどなので、
やはり子供相手だと、大人の方とのコミュニケーションが非常に大切になってきます。
そう思えば・・・治療院で何かしてもらえる方が、簡単なのかもしれません。
もう一つは「体幹強化が必要?」というニュアンスの質問でした。
話を聞くと、体幹を安定させることを考えるよりも、自分とボールとの「空間認知」の方が
優先順位は先なのでは?という視点からの発想をお伝えしてみました。
これは、昨日の講演のテーマ「発育発達」の準備のためにいろいろと整理した事がきっかけです。
主人ともよく話しますが、「バレーボール」って、難しいんです。
宙に浮いているボールを、たたいたり、コントロールしたりするわけですから、
観るよりも、難しい。そして技術が多いのもバレーボールの特徴なので、
非常に技術練習に時間がかかる。
ですが、小学生のうちは神経系の発達が成人の80~100%に到達する時期ですから、
きちんと指導の順を追って、感覚的なものを伝えてあげると抜群の吸収力を見せるわけです。
上手な子は、動きのイメージを頭の中でうまく自分に置き換えて出来る子だと思います。
でも、努力次第、教え方次第できちんと伝わる子もいるんだと思います。
逆に言えば、そういう子を沢山育てられると、素敵だなあと思います。
ただ、バレーボールはチームスポーツなので、個に応じた指導に限界があることも確かかな?と思います。
難しいですね。。
でも、そうやって声をかけてくださったことで、正解ではないかもしれないけれど、
こういう目線の考え方から、その人なりの考え方がプラスされると、本当に面白いと思うんですよね。
もっと、他の方の意見が重なれば、発想は無限大。
私もこうやって考えさせてもらって、ヒラメキに繋がる。
有難いですね。
今日は試合後にキャプテンの娘が
「ママ、みんなでストレッチしといたから!」
観ましたよ、シャキシャキし切れないキャプテンは監督に怒られながら皆を動かしていたところを(笑)。
可哀そうに、私と似て全然気が回らないんです。ホントは、母親の私がしっかりしなきゃいけないんですよね・・・
ここ最近は、練習後に教えた「クーリングダウン」を続けてやってくれています。
ホント、ごくごく簡単なものを、動きを覚えたら、少しずつ増やして。
これ、やったからって勝てるか、と言われれば、そうじゃないんですけど・・・
やっぱり、こういうことを当たり前に出来ることも、大切なことだと私は思うんですよね。