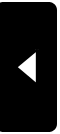2015年11月30日
国体強化練習会にて
週末は、小学生を対象に大島地区のバレーボーラーが集った合同練習会があり、そこで、ウォームアップとクールダウンを担当させていただきました。
7年後の鹿児島国体で中学一年生〜小学5年生が高校生になっているから、という程の…練習会は鹿児島県内、様々な競技が県からの依頼の元、強化のために行っているようです。。


主な企画、運営、技術指導担当は、中学生の先生方でした。
今回は、その企画をされた先生からの依頼で、させていただきました。
内容についても、特に指摘はなかったので
国体を前提・・・というよりもむしろ普段の選手のコンディショニングの一つとして
何か提供できたらいいな、という思い。
少しでしゃばって、
「ストレッチングはなぜ必要か?」というお話を、簡単にさせてもらいました。
子供たちを見守る、お父さん、お母さん達へも、少しご理解いただきたく。。
小学生高学年から中学生の成長期にかけてのカラダの変化や
カラダの硬さが、技術(プレー)獲得に及ぼす弊害、
自分自身で、まず自分のカラダに興味を持つことの必要性
・・・など、「自分のコンディションを整えるための方法の1つ」として
ゆくゆくは、こういう意識が、「自己管理」につながっていくといいな・・・という思いでした。
練習会が終わり、先生方のミーティングにも参加させてもらいました。
最後に、「次回も、ストレッチングとかウォームアップの指導を入れる時間は設けたほうがいい」と
お世辞でも、そう言ってくださったのは、うれしかったです。
今回、こうした中学生の先生方とお話しする機会の中で、
先生方の思いは、競技問わず同じです。
「ケガは、させたくない。でも練習時間短いので、(確保する)時間がない。」
難しい問題です。でも、ストレッチングの必要性は、理解してくださっていること、
また、これを機に再認識していただければ、ありがたい。
子供たちも含めて、繰り返しこういう提供ができれば
やらない(提供しない)よりは、何か救われる子供も出てくると信じて
またの機会を、待ちたいと思います。
さて、最後に・・・一言申し上げておきたい。
『 国体強化練習会 』と名前ばかりは良いのですが、果たして本当に必要なのか?
「地区の強化」ではなく、「鹿児島県全体での国体に向けての強化」なはずなのに、
県としての一貫性はなく、地区に丸投げのこの事業はいかがなものかな・・・
と個人的には思います。
というのも、「国体」そのもの自体が昨今、必要性や意義について疑問を投げかけられている。
他県でも国体の「強化費」を各競技団体に渡し、
あとは ”お任せ” というところも少なくないようです。
おそらく、ほとんどの国体開催県は「優勝」を掲げて強化に励む、
しかし、開催後のフォローは? 選手の育成は?
指導者はさらに資質・技術レベルを上げる努力ができるのか?
「国体優勝」を掲げた、その後の目標設定が、本当に明確で
県も資質の維持・向上につとめているのか・・・
鹿児島国体は、奇しくもオリンピックイヤー。
世界と戦うことを視野にいれた、選手・指導者の資質向上のために
国全体の強化システム(ジュニア育成からの具体的な方針など)が早急に見直され、
この大島地区にも、情報が通い、本当の意味での「強化」になることを
願うばかりです。
7年後の鹿児島国体で中学一年生〜小学5年生が高校生になっているから、という程の…練習会は鹿児島県内、様々な競技が県からの依頼の元、強化のために行っているようです。。


主な企画、運営、技術指導担当は、中学生の先生方でした。
今回は、その企画をされた先生からの依頼で、させていただきました。
内容についても、特に指摘はなかったので
国体を前提・・・というよりもむしろ普段の選手のコンディショニングの一つとして
何か提供できたらいいな、という思い。
少しでしゃばって、
「ストレッチングはなぜ必要か?」というお話を、簡単にさせてもらいました。
子供たちを見守る、お父さん、お母さん達へも、少しご理解いただきたく。。
小学生高学年から中学生の成長期にかけてのカラダの変化や
カラダの硬さが、技術(プレー)獲得に及ぼす弊害、
自分自身で、まず自分のカラダに興味を持つことの必要性
・・・など、「自分のコンディションを整えるための方法の1つ」として
ゆくゆくは、こういう意識が、「自己管理」につながっていくといいな・・・という思いでした。
練習会が終わり、先生方のミーティングにも参加させてもらいました。
最後に、「次回も、ストレッチングとかウォームアップの指導を入れる時間は設けたほうがいい」と
お世辞でも、そう言ってくださったのは、うれしかったです。
今回、こうした中学生の先生方とお話しする機会の中で、
先生方の思いは、競技問わず同じです。
「ケガは、させたくない。でも練習時間短いので、(確保する)時間がない。」
難しい問題です。でも、ストレッチングの必要性は、理解してくださっていること、
また、これを機に再認識していただければ、ありがたい。
子供たちも含めて、繰り返しこういう提供ができれば
やらない(提供しない)よりは、何か救われる子供も出てくると信じて
またの機会を、待ちたいと思います。
さて、最後に・・・一言申し上げておきたい。
『 国体強化練習会 』と名前ばかりは良いのですが、果たして本当に必要なのか?
「地区の強化」ではなく、「鹿児島県全体での国体に向けての強化」なはずなのに、
県としての一貫性はなく、地区に丸投げのこの事業はいかがなものかな・・・
と個人的には思います。
というのも、「国体」そのもの自体が昨今、必要性や意義について疑問を投げかけられている。
他県でも国体の「強化費」を各競技団体に渡し、
あとは ”お任せ” というところも少なくないようです。
おそらく、ほとんどの国体開催県は「優勝」を掲げて強化に励む、
しかし、開催後のフォローは? 選手の育成は?
指導者はさらに資質・技術レベルを上げる努力ができるのか?
「国体優勝」を掲げた、その後の目標設定が、本当に明確で
県も資質の維持・向上につとめているのか・・・
鹿児島国体は、奇しくもオリンピックイヤー。
世界と戦うことを視野にいれた、選手・指導者の資質向上のために
国全体の強化システム(ジュニア育成からの具体的な方針など)が早急に見直され、
この大島地区にも、情報が通い、本当の意味での「強化」になることを
願うばかりです。
2015年11月24日
第2回ASAテーピング講習会 終了!
21日土曜日に行いました「ASAスポーツ講習会」
テーピングの実技講習、多くの方にご参加いただき無事終了いたしました。



中学生、高校生の参加もあり、
みなさん、積極的に質問で手を挙げていただいたり
観るほど、うまく巻けない難しさや
「特定の関節の動きに制限をかける」ことのできる
テーピングの効果を体感していただきました。
救急箱に眠ったままのテープを、少し見直して、活用していただけると幸いです。
来年1月16日は「体幹トレーニング」のテーマで
第3回の講習会をすでに計画しています。
そんな予告をした直後に、
「腹筋はむちゃくちゃ鍛えていたのに、腰痛になってしまい、治るのに結構時間がかかった」
と話をしてくれた方が。
サブタイトルは決定!
「 圧をかける、圧に耐える 」 かな・・・
現在、高校生へ「体幹の強化」は、大きなテーマの一つとして指導に当たっています。
少しづつ、自分のカラダと向き合えるようになってきた彼女達の指導を通して、
より伝わりやすい、シンプルな言語で
「体幹を安定させる大切さ」を講習会の場でお伝えできるよう
引き続き、自分の技術を極めていきたいと思います。
今回を皮切りに…今年はあと4つ、講義・講習が待ってます。
こんな時期もあるんだな、と(笑)。有難い事です。
私自身に出来る事は限りがありますが、何か皆さんの+αの発想に繋がれば…と
自分の役割を全うしたいと思うところです。
テーピングの実技講習、多くの方にご参加いただき無事終了いたしました。



中学生、高校生の参加もあり、
みなさん、積極的に質問で手を挙げていただいたり
観るほど、うまく巻けない難しさや
「特定の関節の動きに制限をかける」ことのできる
テーピングの効果を体感していただきました。
救急箱に眠ったままのテープを、少し見直して、活用していただけると幸いです。
来年1月16日は「体幹トレーニング」のテーマで
第3回の講習会をすでに計画しています。
そんな予告をした直後に、
「腹筋はむちゃくちゃ鍛えていたのに、腰痛になってしまい、治るのに結構時間がかかった」
と話をしてくれた方が。
サブタイトルは決定!
「 圧をかける、圧に耐える 」 かな・・・
現在、高校生へ「体幹の強化」は、大きなテーマの一つとして指導に当たっています。
少しづつ、自分のカラダと向き合えるようになってきた彼女達の指導を通して、
より伝わりやすい、シンプルな言語で
「体幹を安定させる大切さ」を講習会の場でお伝えできるよう
引き続き、自分の技術を極めていきたいと思います。
今回を皮切りに…今年はあと4つ、講義・講習が待ってます。
こんな時期もあるんだな、と(笑)。有難い事です。
私自身に出来る事は限りがありますが、何か皆さんの+αの発想に繋がれば…と
自分の役割を全うしたいと思うところです。
2015年11月20日
食べることの大切さ
「食べることの大切さ」
というテーマで、
女子バレー部副顧問で、家庭科教諭の
吉永智子先生にお話していただきました。

今年度3回目の「スポーツ栄養学」の勉強会です。
今月行ったフィールドテストや、ウエイトの1RM測定(筋力測定)を受けて、
今後、彼女達のパフォーマンス向上や、コンディショニングを考える上で
必要不可欠であるのが、「食事=栄養補給」 です。
トレーニングは、いわば 「カラダを壊す」 作業と 「修復する」 作業の繰り返しです。
学生なので、それぞれの家庭での食生活まで関与できるものではありませんが
最低限「食べる側」が知識をもち、意識をすることは、大事かなと思って
家庭科の授業の延長・・・「実践編」といいますか(笑)。
前回までは 「食事のバランスガイド」を利用して、それぞれの食生活を振り返ってもらい、
基本的な「食」に関する知識を、教えていただきましたが、
今回はさらに、食事の大切さを再認識した上で、「日々の生活の中で、どう工夫していくか」という内容。

お弁当の大きさの目安、体調やコンディションと自分の食生活の振り返りなどの中で、
選手自身が考える 「改善していきたいこと」 「そのための解決策」 書き込み、
与えた知識をさらに自分の中で解釈し、取り込んでいくか・・・
自分と向き合う時間にもなった、と思います。
答えは、あってないようなものだけど
「何か、考えて行動を変える」 ということは
大事なことじゃないかな・・・
これを変えたから、といって勝てる、とか、
パフォーマンスが変わる、とかは「絶対」ではないけれど
私は「勝負の楽しみ方」って、
こういう面から始まっている、と思います。
ジュニア期のスポーツには多少指導者からの強制も入るけど
それは、子供達がまだ持っていない情報を、
意図がそこにあれば、指導であり、躾でもある。
結構、そういう事を蔑ろにして、
「 技術練習だけ頑張っていれば上手くなるんじゃないか 」とか、
「 練習頑張っておけば勝てるんじゃないか 」とか
思っているのが「子供」なのだと思います。
でも、本当は「勝つため」にはテクニックだけじゃなく、
フィジカル(身体)も、メンタル(心理)も、そしてニュートリション(栄養)もあって
自分に何が足りてない、ということを知り
その情報や知識は、求めれば揃えることができる、
揃えることで救われることもある、ということを
知ってほしいと思います。
「勝たなきゃ意味がない」「勝つから楽しい(負けたら楽しくない)」 のではなく
上手くいかないことや、その悔しさを経験しながら
「勝負を競う合うことの楽しさ」 ・・・スポーツの本質を楽しんでほしいなあ・・・。
『これを知る者は、これを好む者に如かず これを好む者は、これを楽しむ者に如かず (孔子) 』
というテーマで、
女子バレー部副顧問で、家庭科教諭の
吉永智子先生にお話していただきました。

今年度3回目の「スポーツ栄養学」の勉強会です。
今月行ったフィールドテストや、ウエイトの1RM測定(筋力測定)を受けて、
今後、彼女達のパフォーマンス向上や、コンディショニングを考える上で
必要不可欠であるのが、「食事=栄養補給」 です。
トレーニングは、いわば 「カラダを壊す」 作業と 「修復する」 作業の繰り返しです。
学生なので、それぞれの家庭での食生活まで関与できるものではありませんが
最低限「食べる側」が知識をもち、意識をすることは、大事かなと思って
家庭科の授業の延長・・・「実践編」といいますか(笑)。
前回までは 「食事のバランスガイド」を利用して、それぞれの食生活を振り返ってもらい、
基本的な「食」に関する知識を、教えていただきましたが、
今回はさらに、食事の大切さを再認識した上で、「日々の生活の中で、どう工夫していくか」という内容。

お弁当の大きさの目安、体調やコンディションと自分の食生活の振り返りなどの中で、
選手自身が考える 「改善していきたいこと」 「そのための解決策」 書き込み、
与えた知識をさらに自分の中で解釈し、取り込んでいくか・・・
自分と向き合う時間にもなった、と思います。
答えは、あってないようなものだけど
「何か、考えて行動を変える」 ということは
大事なことじゃないかな・・・
これを変えたから、といって勝てる、とか、
パフォーマンスが変わる、とかは「絶対」ではないけれど
私は「勝負の楽しみ方」って、
こういう面から始まっている、と思います。
ジュニア期のスポーツには多少指導者からの強制も入るけど
それは、子供達がまだ持っていない情報を、
意図がそこにあれば、指導であり、躾でもある。
結構、そういう事を蔑ろにして、
「 技術練習だけ頑張っていれば上手くなるんじゃないか 」とか、
「 練習頑張っておけば勝てるんじゃないか 」とか
思っているのが「子供」なのだと思います。
でも、本当は「勝つため」にはテクニックだけじゃなく、
フィジカル(身体)も、メンタル(心理)も、そしてニュートリション(栄養)もあって
自分に何が足りてない、ということを知り
その情報や知識は、求めれば揃えることができる、
揃えることで救われることもある、ということを
知ってほしいと思います。
「勝たなきゃ意味がない」「勝つから楽しい(負けたら楽しくない)」 のではなく
上手くいかないことや、その悔しさを経験しながら
「勝負を競う合うことの楽しさ」 ・・・スポーツの本質を楽しんでほしいなあ・・・。
『これを知る者は、これを好む者に如かず これを好む者は、これを楽しむ者に如かず (孔子) 』
2015年10月23日
足の捻挫受傷後の経過例(重症度Ⅰ度)
足関節の捻挫をした選手の経過例を載せてみます。
ご参考までに。。
<背景>
競技・・・バレーボール(中学1年生・女子)
発生機転・・・ジャンプ着地時にネット越しにプレーヤーの足を踏み足首をひねる。
処置・・・痛みはあったが、自身で歩いて帰宅し、帰宅後にRICE処置を行った。
夜間のため、整形外科の受診は見送る。
その他・・・
試験期間明け。角膜炎のため、視力矯正なしの状態で練習参加。
試合1週間前。
以上から、
ケガの原因は「コンディショニング(準備)不足」。
選手に自己管理能力があれば、未然に防ぐことができたと推測します。
<所見>
重症度・・・Ⅰ度
*Ⅰ度とは?・・腫れもなく、歩行が可能、2~3日安静後、1週間程度でスポーツ復帰可能
発生機転と、足関節の外側の痛みより、足関節内反捻挫(内返し)と推測。
<受傷2日目>
起床後の様子・・・腫れはなし。荷重で痛みあり。
その他・・・本人の希望で、練習(練習ゲーム)に参加したい、とのこと。
再発予防・・・テープ固定(キネシオ)と足関節のバンド固定。
トレーナー所見・・・動くことによって、腫れが出てくる事を予想して、キネシオテープで
関節の固定を行った。テープ事前にRICE処置。
本人がまき直しができるバンドでさらに固定した。
帰宅後の様子・・・「痛かった。昨日よりもズキズキする。」
前日よりも若干の腫れと熱感。アイシングで処置。
通常の対応・・・「2~3日のアイシングと患部の安静」が適当です。
軽度の捻挫でも、”無理” をすると、腫れと痛み(炎症反応)が出てきます。
RICE処置で、寝る前までアイシング。
<受傷3日目>
起床後の様子・・・「夜中に急に足が熱くなって、とても痛かった。」「昨日の朝と変わらない痛み」
その他・・・本人の希望で、練習に参加したい、とのこと。
再発予防・・・テープ固定(前日よりも、もうすこししっかりと固定:スパイラルテープ・
キネシオテープ・フレックステープ)とバンド固定(前日と巻き方を変えてみる)。
トレーナー所見・・・痛みはあるが、腫れはほとんどなかったが、動くことでの腫れの出現を考慮して、
キネシオテープなどで関節の固定を図る。
*テープで圧迫しているため、練習途中のアイシングは冷たさが通らないだろう、と
患部の拳上を促した。
<受傷4日目>
起床後の様子・・・痛みあり。
再発予防・・・アイシングをして、学校生活での動作範囲を考慮してきっちりテーピング固定(ホワイトテープ)。
部活時には、テープ固定も緩みが出るため、必要に応じてバンド固定を促した。
トレーナー所見・・・受傷4日目で、腫れも痛みもピークは越えたので学校生活では関節の安静を図った。
朝練習のランニングはやらずに、ストレッチングなどを別メニューで行うことを促す。
帰宅後の様子・・・いつもよりテープ固定がきっちりされたので、スポーツ動作に制限があったことを訴える。
痛みはほとんどなかった。
<受傷5日目>
起床後の様子・・・痛みなし。軽いテープ固定と、バンドの固定でいい、と本人の希望。
帰宅後の様子・・・「大丈夫だった」
<受傷6日目>
再発予防・・・バンド固定のみ
これが重症度Ⅰの、軽度の捻挫の今回の経過です。
ちなみに選手とは、うちの娘です。
娘には申し訳ないですが、完全に私の実験台です(笑)。
トレーナーと選手といえど、寝食をともにする機会はあまりないので
私の今までの「経験」と、「教科書」がどれくらいマッチするのか
非常にいい体験データとなりました。
セオリーは、「無理はしないほうがいい」です。
その方が、回復が速い。3日、練習を我慢して安静にしていれば
4日目にはなんでもないケガの程度だったと思います。
これが出来る(試せる)前提には
経験と知識と技術があるからに過ぎません。
きちんと受傷後のフォローが出来ない事がほとんどなので
・整形外科での受診、画像診断による医師の診断
・受傷3日間程度の患部の安静
やはり、このようにおススメするのが、現実的かな、と思います。
結果的に今回は、試合までに間に合う程度のケガでした。
私はケガを治すことはできませんが
何か、ご相談があれば、このような人間を、気軽にご活用ください。
ご参考までに。。
<背景>
競技・・・バレーボール(中学1年生・女子)
発生機転・・・ジャンプ着地時にネット越しにプレーヤーの足を踏み足首をひねる。
処置・・・痛みはあったが、自身で歩いて帰宅し、帰宅後にRICE処置を行った。
夜間のため、整形外科の受診は見送る。
その他・・・
試験期間明け。角膜炎のため、視力矯正なしの状態で練習参加。
試合1週間前。
以上から、
ケガの原因は「コンディショニング(準備)不足」。
選手に自己管理能力があれば、未然に防ぐことができたと推測します。
<所見>
重症度・・・Ⅰ度
*Ⅰ度とは?・・腫れもなく、歩行が可能、2~3日安静後、1週間程度でスポーツ復帰可能
発生機転と、足関節の外側の痛みより、足関節内反捻挫(内返し)と推測。
<受傷2日目>
起床後の様子・・・腫れはなし。荷重で痛みあり。
その他・・・本人の希望で、練習(練習ゲーム)に参加したい、とのこと。
再発予防・・・テープ固定(キネシオ)と足関節のバンド固定。
トレーナー所見・・・動くことによって、腫れが出てくる事を予想して、キネシオテープで
関節の固定を行った。テープ事前にRICE処置。
本人がまき直しができるバンドでさらに固定した。
帰宅後の様子・・・「痛かった。昨日よりもズキズキする。」
前日よりも若干の腫れと熱感。アイシングで処置。
通常の対応・・・「2~3日のアイシングと患部の安静」が適当です。
軽度の捻挫でも、”無理” をすると、腫れと痛み(炎症反応)が出てきます。
RICE処置で、寝る前までアイシング。
<受傷3日目>
起床後の様子・・・「夜中に急に足が熱くなって、とても痛かった。」「昨日の朝と変わらない痛み」
その他・・・本人の希望で、練習に参加したい、とのこと。
再発予防・・・テープ固定(前日よりも、もうすこししっかりと固定:スパイラルテープ・
キネシオテープ・フレックステープ)とバンド固定(前日と巻き方を変えてみる)。
トレーナー所見・・・痛みはあるが、腫れはほとんどなかったが、動くことでの腫れの出現を考慮して、
キネシオテープなどで関節の固定を図る。
*テープで圧迫しているため、練習途中のアイシングは冷たさが通らないだろう、と
患部の拳上を促した。
<受傷4日目>
起床後の様子・・・痛みあり。
再発予防・・・アイシングをして、学校生活での動作範囲を考慮してきっちりテーピング固定(ホワイトテープ)。
部活時には、テープ固定も緩みが出るため、必要に応じてバンド固定を促した。
トレーナー所見・・・受傷4日目で、腫れも痛みもピークは越えたので学校生活では関節の安静を図った。
朝練習のランニングはやらずに、ストレッチングなどを別メニューで行うことを促す。
帰宅後の様子・・・いつもよりテープ固定がきっちりされたので、スポーツ動作に制限があったことを訴える。
痛みはほとんどなかった。
<受傷5日目>
起床後の様子・・・痛みなし。軽いテープ固定と、バンドの固定でいい、と本人の希望。
帰宅後の様子・・・「大丈夫だった」
<受傷6日目>
再発予防・・・バンド固定のみ
これが重症度Ⅰの、軽度の捻挫の今回の経過です。
ちなみに選手とは、うちの娘です。
娘には申し訳ないですが、完全に私の実験台です(笑)。
トレーナーと選手といえど、寝食をともにする機会はあまりないので
私の今までの「経験」と、「教科書」がどれくらいマッチするのか
非常にいい体験データとなりました。
セオリーは、「無理はしないほうがいい」です。
その方が、回復が速い。3日、練習を我慢して安静にしていれば
4日目にはなんでもないケガの程度だったと思います。
これが出来る(試せる)前提には
経験と知識と技術があるからに過ぎません。
きちんと受傷後のフォローが出来ない事がほとんどなので
・整形外科での受診、画像診断による医師の診断
・受傷3日間程度の患部の安静
やはり、このようにおススメするのが、現実的かな、と思います。
結果的に今回は、試合までに間に合う程度のケガでした。
私はケガを治すことはできませんが
何か、ご相談があれば、このような人間を、気軽にご活用ください。
2015年10月09日
「ロコモ」って言葉、ご存じですか?
「ロコモ予防の推進を」
新聞を開くと、大きく掲載されていました。

健康寿命を延ばすための「ロコモ予防推進」を県の政策として取り組んでいく、
という内容。
「ロコモ」
一見美味しそう、楽しそう・・・と3年前初めて聞いた時に思ったなあ(笑)。
「ロコモティブシンドローム(運動器症候群)」
簡単に言うと、
「年を取ると、カラダの筋肉量が減って、筋力は低下するよ。
そのまま、ほおっておくと立ったり、歩いたりできなくなっちゃうよ。」
・・・というもの。
2022年度までに、県民の「ロコモ」認知度を80%にあげるのが、まず目標、とのこと。
(現在、県では35.6%、全国では44.4%)
似たような言葉、ありますね。
「メタボ」
こちらは、数年前から認知度は定着しましたね。
「メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)」
こちらは・・・
「内臓脂肪がたまると、血管がつまったりして大変なことになっちゃうよ。」
食生活の改善や、運動のススメなど
「生活習慣の改善」を、この言葉をキーワードに少なからず、
意識をされた方もいらっしゃると思います。
ロコモとメタボ。
これは、健康を阻害する要因だけでなく、「認知症を合併する」方も多いそうです。

人間は、誰しも歳をとり、老いていくことは避けられない道です。
薄々、そう感じながらも
できるだけ人様の支援を受けなくても、自立した生活を送りたいと思っている方も多いと思う。
「ロコモ」という言葉の提唱には、
『 運動器に支えられて生きている人間が、健康であるためには
生活を送るだけの運動機能を落とさないための対策が必要なことを、日々意識してくださいね 』
というメッセージが込められているようです。
なるほど・・・
わかっちゃいたけど、ガックリきたのが、この現実 ↓↓
運動機能の低下が徐々にあらわれ始めるのが40代から・・・(苦)。
新聞を開くと、大きく掲載されていました。

健康寿命を延ばすための「ロコモ予防推進」を県の政策として取り組んでいく、
という内容。
「ロコモ」
一見美味しそう、楽しそう・・・と3年前初めて聞いた時に思ったなあ(笑)。
「ロコモティブシンドローム(運動器症候群)」
簡単に言うと、
「年を取ると、カラダの筋肉量が減って、筋力は低下するよ。
そのまま、ほおっておくと立ったり、歩いたりできなくなっちゃうよ。」
・・・というもの。
2022年度までに、県民の「ロコモ」認知度を80%にあげるのが、まず目標、とのこと。
(現在、県では35.6%、全国では44.4%)
似たような言葉、ありますね。
「メタボ」
こちらは、数年前から認知度は定着しましたね。
「メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)」
こちらは・・・
「内臓脂肪がたまると、血管がつまったりして大変なことになっちゃうよ。」
食生活の改善や、運動のススメなど
「生活習慣の改善」を、この言葉をキーワードに少なからず、
意識をされた方もいらっしゃると思います。
ロコモとメタボ。
これは、健康を阻害する要因だけでなく、「認知症を合併する」方も多いそうです。

人間は、誰しも歳をとり、老いていくことは避けられない道です。
薄々、そう感じながらも
できるだけ人様の支援を受けなくても、自立した生活を送りたいと思っている方も多いと思う。
「ロコモ」という言葉の提唱には、
『 運動器に支えられて生きている人間が、健康であるためには
生活を送るだけの運動機能を落とさないための対策が必要なことを、日々意識してくださいね 』
というメッセージが込められているようです。
なるほど・・・
わかっちゃいたけど、ガックリきたのが、この現実 ↓↓
運動機能の低下が徐々にあらわれ始めるのが40代から・・・(苦)。
2015年10月06日
ココロも、トレーニング。
数年前から、心理学についての書籍を手にすることが多くなりました。
「コンディショニング」の中に心理的サポートという役割も含まれるのがこの仕事です。
まさしく、「 ココロとカラダは繋がっている 」のだなあ、と実感します。
先日、奄美パークに 「 メンタリスト Daigo 」の講演会を聞きに行きました。
読書が趣味、というだけあって、話し方がスマートな方でした。
Daigo さん、自分の過去の実話をベースに
「 自分を変える 」というテーマでお話されたのが非常に興味深かった。
内容までは書けませんが、「 自己分析 」 と 「 目標設定 」から自分を変えていくことが出来る。
メンタル面のスキル(技術)を学ぶことで、実際、自らを変えた当人だということが
この 「 メンタリスト 」として成功をつかむきっかけとなったようです。
私が一番面白かったのは、ココですが、
テレビでよくする 「人の心を読む」かのように、ペン8色から
観客が引き当てた色を当てる 「パフォーマンス」 は本当に驚きでしたね。
私と出会うスポーツ選手は、「ケガをして練習ができない」状況が大半です。
そして、「こいつは、治療も出来ないくせに、何をする人だろう?」と
疑心暗鬼の目で、来ます(笑)。
そんな疑心暗鬼+マイナスオーラ全開でやってきますから、
「原因」が見えていても、聞く耳をもってもらうまでに、「パフォーマンス」が大事です。
ペンの色をあてることは絶対できませんが(笑)
ホンの数センチのテープで、動きを変えることはできます。
そういう 「パフォーマンス」 が結構大事だと、講演の中でも触れられていまして
これも私なりの 「 心理作戦 」だったんだな、と納得しました。
その作戦が成功したら、次は 「 自己分析 」です。
動きながら、自分のカラダと向き合うことを追求します。
頭で考えた動きを、身体で表現し、五感を研ぎ澄まして、身体の変化を感じてもらいます。
そこで、自分のカラダに気づいてもらう。
「ココが硬い」とか「これが出来ない」とか「ココが弱い」とか。
マイナスの子に、出来ない事ばかりに目を向けさせて、余計凹ましては本末転倒なので
「 やれば、できるんだよ 」
・・・身体の使い方を知り、出来ることが増える。徐々に笑顔が見えてきます。
そこで、やっと、本人が原因を知る。いや、知ろうとする。そしてどうにかしたい、と欲する。
選手にとって、「痛みを取る事」は、最終目標ではなく、優先順位の問題であって、
最終目標はあくまで
「パフォーマンスを高める」 ことなのです。
目標が明確に定まれば、あとはやるべきことがおのずと見えてきます。
今は、練習には同じように参加できないかもしれないけど、
その練習時間で、自分はどう時間を使うべきか
そこまで判断してくれる選手は、賢い。
「 考え方が変われば、行動が変わる 」
ココロも、適切なアプローチで地道にトレーニングを積めば、
「弱い心」もきっと、強くなれる。
トレーナー活動を通じて、私が一番学んだことの一つかもしれません。
「コンディショニング」の中に心理的サポートという役割も含まれるのがこの仕事です。
まさしく、「 ココロとカラダは繋がっている 」のだなあ、と実感します。
先日、奄美パークに 「 メンタリスト Daigo 」の講演会を聞きに行きました。
読書が趣味、というだけあって、話し方がスマートな方でした。
Daigo さん、自分の過去の実話をベースに
「 自分を変える 」というテーマでお話されたのが非常に興味深かった。
内容までは書けませんが、「 自己分析 」 と 「 目標設定 」から自分を変えていくことが出来る。
メンタル面のスキル(技術)を学ぶことで、実際、自らを変えた当人だということが
この 「 メンタリスト 」として成功をつかむきっかけとなったようです。
私が一番面白かったのは、ココですが、
テレビでよくする 「人の心を読む」かのように、ペン8色から
観客が引き当てた色を当てる 「パフォーマンス」 は本当に驚きでしたね。
私と出会うスポーツ選手は、「ケガをして練習ができない」状況が大半です。
そして、「こいつは、治療も出来ないくせに、何をする人だろう?」と
疑心暗鬼の目で、来ます(笑)。
そんな疑心暗鬼+マイナスオーラ全開でやってきますから、
「原因」が見えていても、聞く耳をもってもらうまでに、「パフォーマンス」が大事です。
ペンの色をあてることは絶対できませんが(笑)
ホンの数センチのテープで、動きを変えることはできます。
そういう 「パフォーマンス」 が結構大事だと、講演の中でも触れられていまして
これも私なりの 「 心理作戦 」だったんだな、と納得しました。
その作戦が成功したら、次は 「 自己分析 」です。
動きながら、自分のカラダと向き合うことを追求します。
頭で考えた動きを、身体で表現し、五感を研ぎ澄まして、身体の変化を感じてもらいます。
そこで、自分のカラダに気づいてもらう。
「ココが硬い」とか「これが出来ない」とか「ココが弱い」とか。
マイナスの子に、出来ない事ばかりに目を向けさせて、余計凹ましては本末転倒なので
「 やれば、できるんだよ 」
・・・身体の使い方を知り、出来ることが増える。徐々に笑顔が見えてきます。
そこで、やっと、本人が原因を知る。いや、知ろうとする。そしてどうにかしたい、と欲する。
選手にとって、「痛みを取る事」は、最終目標ではなく、優先順位の問題であって、
最終目標はあくまで
「パフォーマンスを高める」 ことなのです。
目標が明確に定まれば、あとはやるべきことがおのずと見えてきます。
今は、練習には同じように参加できないかもしれないけど、
その練習時間で、自分はどう時間を使うべきか
そこまで判断してくれる選手は、賢い。
「 考え方が変われば、行動が変わる 」
ココロも、適切なアプローチで地道にトレーニングを積めば、
「弱い心」もきっと、強くなれる。
トレーナー活動を通じて、私が一番学んだことの一つかもしれません。
2015年09月10日
コンディショニング
「コンディショニング」って何でしょう?
まさしく「コンディション(状態・状況)を整える」事なのだと思います。
日本体育協会アスレチックトレーナーでは
「勝つための全ての準備」
と定義付けられ、その要因は以下の3つ。
①環境を整える
②身体を整える
③心を整える
フィジカル(身体的)トレーニングの「コンディショニング」はスポーツ生理学という、運動時に必要とされるエネルギーシステム(代謝)を強調したプログラム、といえます。
ここには競技特性が大きく関与し、
多くのプログラムには運動/休息比が用いられます。
例えば、バレーボール(国際大会)の場合、
・1プレー3~10秒
・1ラリー5~30秒
・1セット20~30秒
・1試合60~120分
・プレー間20~30秒(休息)
・セット間3分(休息)
で、行われます。
「コンディショニング」を考える上では、この競技の特徴の中で、「いかに最高のパフォーマンスを出せるか」ということを考慮したうえで
「準備」を整えなければなりません。
これこそ、まさに”ゲームのための身体づくり”と言えます。
「体力をつける」ためにスピードの強弱、セットの時間や休息時間を無視した「走り続ける」トレーニングだけでは
例え選手が一生懸命トレーニングを積んだとしても、ケガが絶えなかったり、体力の改善が見えなかったりすることはよく現場でみられます。
「コンディショニングプログラム」はおそらく選手が一番嫌がるプログラムかもしれません。。
だから一番テンションが下がます・・・
今日は「頑張れ!自分に負けるな!」と叱咤激励。。キツいのも、よく分かるから…観ていてこちらも、力が入ります。
だから、写真も撮り忘れてしまいました(笑)
また時間があるときに、詳しく紹介したいと思います。
まさしく「コンディション(状態・状況)を整える」事なのだと思います。
日本体育協会アスレチックトレーナーでは
「勝つための全ての準備」
と定義付けられ、その要因は以下の3つ。
①環境を整える
②身体を整える
③心を整える
フィジカル(身体的)トレーニングの「コンディショニング」はスポーツ生理学という、運動時に必要とされるエネルギーシステム(代謝)を強調したプログラム、といえます。
ここには競技特性が大きく関与し、
多くのプログラムには運動/休息比が用いられます。
例えば、バレーボール(国際大会)の場合、
・1プレー3~10秒
・1ラリー5~30秒
・1セット20~30秒
・1試合60~120分
・プレー間20~30秒(休息)
・セット間3分(休息)
で、行われます。
「コンディショニング」を考える上では、この競技の特徴の中で、「いかに最高のパフォーマンスを出せるか」ということを考慮したうえで
「準備」を整えなければなりません。
これこそ、まさに”ゲームのための身体づくり”と言えます。
「体力をつける」ためにスピードの強弱、セットの時間や休息時間を無視した「走り続ける」トレーニングだけでは
例え選手が一生懸命トレーニングを積んだとしても、ケガが絶えなかったり、体力の改善が見えなかったりすることはよく現場でみられます。
「コンディショニングプログラム」はおそらく選手が一番嫌がるプログラムかもしれません。。
だから一番テンションが下がます・・・
今日は「頑張れ!自分に負けるな!」と叱咤激励。。キツいのも、よく分かるから…観ていてこちらも、力が入ります。
だから、写真も撮り忘れてしまいました(笑)
また時間があるときに、詳しく紹介したいと思います。
2015年09月06日
負荷をかける
体育祭シーズンですね。
大高の体育祭を今年も観に行きました。
ムカデのスピードと応援団の気迫は圧巻ですね。高校生達の自主性によるエネルギーは素晴らしい。
今月は「フィジカルトレーニング」について
取り入れた情報と、自分の実践状況と経験と考えを踏まえて
書き込んでいきます。半分は自分の活動と考え方の整理です。
(興味ある方が「へー」と思ってもらえればいいかな。)
まず、根本的な私のフィジカルトレーニングに対する考え方。
フィジカル(身体)トレーニングは「負荷」をかけないと意味がありません。
自分のカラダを追い込んで、追い込んで、追い込んでこそ・・・成長できると思っています。
かといって、急にハードトレーニングをさせても、これこそ無意味です。
だから、まずは「自分の体重をコントロールできるか」が負荷をどれくらいかけるかの最初のチェックになります。
体力測定も然りです。これは個々の現状を他者と比較しつつ、成長を数値で表し、トレーニング効果を可視化するためのものです。
指導者が毎日きちんと選手を観察できていれば、粗方その数字は納得できるものになるはずです。
負荷は自体重のみでも、動作コントロールが「きちんと」できれば、十分変化がみられます(注:大半は間違った動きに気づく事なく、サボっています)。
チームのトレーニングを担当していますが、私の中ではまだまだ半分くらいしか、させきれていません。
大事なことですが、本当に自分が成長するには、個々のモチベーションの高さが必要だと思っています。
これは、こちらからいくら要求しても、ほぼ伝わりません。
やらせることもできますが、「強制」はサボりにすぐ繋がります。
まだまだ、フィジカルトレーニングの必要性を選手に伝えきれていないのだと思います。私の責任もあります。
あとは、目指すべき目標やイメージが明確でないのでしょう。ここを伝えるには実際、試合をこなして、自分達の実力を目の当たりにしないと難しいかも。もう少し時間が必要です。
そういう状況の中でも、「負荷をかける」ことは可能な範囲で行うべきだと思います。
選手は素直です。言われた事はやります。だから、知らない間に身体は負荷に耐え得る能力を身につける。パフォーマンスも時間かければ上手くなります。
ただ、「やらされているトレーニングは面白くないだろうな」と思います…
「人間は自分に出来ないと思う事、上手くやれないと思う事はやらない」
…習性があるようなので、やはり待つしかないな、と思うのです。
応援団のように…自主性ある部活動に。
自分で上手くなるための工夫し、「負荷」をかけられるような選手が現れるのを楽しみにしながら…
「フィジカルトレーニング」の必要性を伝えて、実際に形として残していきたいと思います。
これも一つ私の「負荷」として、チャレンジしたいと思います。
大高の体育祭を今年も観に行きました。
ムカデのスピードと応援団の気迫は圧巻ですね。高校生達の自主性によるエネルギーは素晴らしい。
今月は「フィジカルトレーニング」について
取り入れた情報と、自分の実践状況と経験と考えを踏まえて
書き込んでいきます。半分は自分の活動と考え方の整理です。
(興味ある方が「へー」と思ってもらえればいいかな。)
まず、根本的な私のフィジカルトレーニングに対する考え方。
フィジカル(身体)トレーニングは「負荷」をかけないと意味がありません。
自分のカラダを追い込んで、追い込んで、追い込んでこそ・・・成長できると思っています。
かといって、急にハードトレーニングをさせても、これこそ無意味です。
だから、まずは「自分の体重をコントロールできるか」が負荷をどれくらいかけるかの最初のチェックになります。
体力測定も然りです。これは個々の現状を他者と比較しつつ、成長を数値で表し、トレーニング効果を可視化するためのものです。
指導者が毎日きちんと選手を観察できていれば、粗方その数字は納得できるものになるはずです。
負荷は自体重のみでも、動作コントロールが「きちんと」できれば、十分変化がみられます(注:大半は間違った動きに気づく事なく、サボっています)。
チームのトレーニングを担当していますが、私の中ではまだまだ半分くらいしか、させきれていません。
大事なことですが、本当に自分が成長するには、個々のモチベーションの高さが必要だと思っています。
これは、こちらからいくら要求しても、ほぼ伝わりません。
やらせることもできますが、「強制」はサボりにすぐ繋がります。
まだまだ、フィジカルトレーニングの必要性を選手に伝えきれていないのだと思います。私の責任もあります。
あとは、目指すべき目標やイメージが明確でないのでしょう。ここを伝えるには実際、試合をこなして、自分達の実力を目の当たりにしないと難しいかも。もう少し時間が必要です。
そういう状況の中でも、「負荷をかける」ことは可能な範囲で行うべきだと思います。
選手は素直です。言われた事はやります。だから、知らない間に身体は負荷に耐え得る能力を身につける。パフォーマンスも時間かければ上手くなります。
ただ、「やらされているトレーニングは面白くないだろうな」と思います…
「人間は自分に出来ないと思う事、上手くやれないと思う事はやらない」
…習性があるようなので、やはり待つしかないな、と思うのです。
応援団のように…自主性ある部活動に。
自分で上手くなるための工夫し、「負荷」をかけられるような選手が現れるのを楽しみにしながら…
「フィジカルトレーニング」の必要性を伝えて、実際に形として残していきたいと思います。
これも一つ私の「負荷」として、チャレンジしたいと思います。
2015年09月03日
「体力」をつけるには?
今日も、書きます。今日は久々「トレーニング」についてです。
「体力」といえば、何が思い浮かびますか?
「体力をつける」と聞いて、どんな手段が思い浮かびますか?
恐らく、半数以上の人は
「走る」
「長い距離を走れる体力」
「長い時間走れると体力がつく」
私も、そう信じてきた人間です。
そして、「体力をつけろ!」と言われるたびに、走らされてきた1人です。
専門用語言えば『最大酸素摂取量(Vo2max)』が高まれば、長時間プレーすることや疲労からより早く回復することが可能になる、という考え方です。
(*最大酸素摂取量・・・全身の細胞レベルで利用することが出来る酸素量の最大値)
最近、トレーニングプログラムを立てる中で私の迷いは、この
「走る」
ということでした。
現在プログラムを立てている種目は「バレーボール」のみですが、
バレーボールという競技は、ジャンプや方向転換の能力(パワー)、スピードの要素が求められる競技です。
プログラムを立てる上で、考えなければならないポイントは
「スポーツの特異性」
です。
どういう意味かといいますと、
バレーボールの試合中、ずっと同じペースで走り続けるような場面はない、ということです。
いわゆる「体力=走る」というセオリーは当てはまらない競技、ということになります。
しかもチームスポーツのほとんどすべては「スピード」と「パワー」が要求されます。
以下は文献でよく目にする文言です。
-パワー系選手の有酸素トレーニングを実施すると、結果的に『最大酸素摂取量』は高まったが、パフォーマンスには変化がみられなかった。
-「サッカー選手は1試合で約10km走る」「テニスの試合は2時間以上続く」のだから、より早い回復には有酸素系システム(長く運動を続ける機能)が重要だ。
続けて、こう述べてあります。
-しかし、このようなことは問題ではない。問題なのは、どのくらいのスピードで、どのくらいの時間で、である。テニスの試合では約2時間プレーしているが、そのうちスプリント(ダッシュ)と休息の比率はどのくらいだろうか。
もう一つ、よく目にする文言ですが・・・
-持久性トレーニングに集中しすぎると、スピードの発達に悪影響を及ぼす可能性があることも考慮しなければならない。逆をとれば、スプリンターを長距離選手にするのは簡単だともいえる。
そうなんですよ・・・
身体、というのは適応するからトレーニングの効果が反映されるわけで、
いくら「体力をつける」ために長い距離を走れるようになったとしても、
競技特異性からみれば、
昔から言われていた「長い距離を走れる体力」は
バレーボールやサッカー、テニスやバドミントンなどの技術改善にはならない、わけです。
当然といえば、当然です。
では、それでもやっぱり「走る」トレーニングをチーム取り入れるべきと思っている・・・
しかも、「長距離走」です。
そこには、「トレーニングの目的」が関係します。
長くなりそうなので、また続きは明日書く事にします。。
「体力」といえば、何が思い浮かびますか?
「体力をつける」と聞いて、どんな手段が思い浮かびますか?
恐らく、半数以上の人は
「走る」
「長い距離を走れる体力」
「長い時間走れると体力がつく」
私も、そう信じてきた人間です。
そして、「体力をつけろ!」と言われるたびに、走らされてきた1人です。
専門用語言えば『最大酸素摂取量(Vo2max)』が高まれば、長時間プレーすることや疲労からより早く回復することが可能になる、という考え方です。
(*最大酸素摂取量・・・全身の細胞レベルで利用することが出来る酸素量の最大値)
最近、トレーニングプログラムを立てる中で私の迷いは、この
「走る」
ということでした。
現在プログラムを立てている種目は「バレーボール」のみですが、
バレーボールという競技は、ジャンプや方向転換の能力(パワー)、スピードの要素が求められる競技です。
プログラムを立てる上で、考えなければならないポイントは
「スポーツの特異性」
です。
どういう意味かといいますと、
バレーボールの試合中、ずっと同じペースで走り続けるような場面はない、ということです。
いわゆる「体力=走る」というセオリーは当てはまらない競技、ということになります。
しかもチームスポーツのほとんどすべては「スピード」と「パワー」が要求されます。
以下は文献でよく目にする文言です。
-パワー系選手の有酸素トレーニングを実施すると、結果的に『最大酸素摂取量』は高まったが、パフォーマンスには変化がみられなかった。
-「サッカー選手は1試合で約10km走る」「テニスの試合は2時間以上続く」のだから、より早い回復には有酸素系システム(長く運動を続ける機能)が重要だ。
続けて、こう述べてあります。
-しかし、このようなことは問題ではない。問題なのは、どのくらいのスピードで、どのくらいの時間で、である。テニスの試合では約2時間プレーしているが、そのうちスプリント(ダッシュ)と休息の比率はどのくらいだろうか。
もう一つ、よく目にする文言ですが・・・
-持久性トレーニングに集中しすぎると、スピードの発達に悪影響を及ぼす可能性があることも考慮しなければならない。逆をとれば、スプリンターを長距離選手にするのは簡単だともいえる。
そうなんですよ・・・
身体、というのは適応するからトレーニングの効果が反映されるわけで、
いくら「体力をつける」ために長い距離を走れるようになったとしても、
競技特異性からみれば、
昔から言われていた「長い距離を走れる体力」は
バレーボールやサッカー、テニスやバドミントンなどの技術改善にはならない、わけです。
当然といえば、当然です。
では、それでもやっぱり「走る」トレーニングをチーム取り入れるべきと思っている・・・
しかも、「長距離走」です。
そこには、「トレーニングの目的」が関係します。
長くなりそうなので、また続きは明日書く事にします。。
2015年06月07日
中学生の部活動でのストレッチング指導
昨日は朝日中にて、
男女バスケットボール部へストレッチングの指導をしました(^^)



学校の部活動で、直接、練習現場で指導するのは(ウチのチーム以外では)稀な活動です。そしてバスケット部の指導は初めて!
普段、バレーの現場で活動している事が多いのですが、競技が違えばウォームアップの取り入れ方や内容の違い、雰囲気も違います。
でも、アップの内容や構成が本当にしっかりしていて、かなり先生ご自身が勉強されているんだなぁ…という実感。
お話聞いていると…思い出しました!バスケットボールは指導者育成のシステムが確立されているので、アップやストレッチングに関してもトップから降りてくるモノを導入されているんですよね。。
観ているこちらも勉強になりました!
メニューは豊富ですが、個々それぞれ同じメニューのはずなのに、動きが違う。
これが何故なのか、どう改善していくのかを分析して、アドバイスしていくのが、私の仕事、という事になります。
今回は、「講習会」では絶対出来ない面白い時間でした。普段の練習の流れに順次ながら、いつもやっているストレッチングのフォーム指導や、ポイントを伝えたり…
先生が以前から気になってらっしゃった、時間の使い方の部分で、「この隙間の時間がもったいないので、何かストレッチングをさせたいんです」と目的をしっかり伝えて下さったので、実際のその時間に合わせて、その中で子供達にいろいろさせてみました。
私は入れ替わり立ち代り目の前にいる子供達に…目が回りましたが(笑)
最初は身体の使い方が分からなくて、悲鳴を上げていた子供達も…
さすが、中学生!習得が早い!
あちこちで、「出来た!」との声。嬉しいよね、出来なかった事が出来るようになるって。私もその笑顔は、嬉しい(^^)
身体が硬い、と思っていた子も、
身体の使い方一つで、どんどん身体が思うように動いていきます。
それが、バスケとどう繋がるか…までを観察する余裕は、今回なかったなぁ。
やはり個々で少しづつ伝えたいポイントや言葉の選択が違う…けどタイムオーバー!
最後は保護者や先生方も一緒に、クールダウンの指導とケアを兼ねたストレッチングの提供をさせていただきました。
先生方や、保護者の方々が日頃、少し疑問に思ってらっしゃった事などにも、お話しながらお答え出来たのかな?と。。
やはり、人間ですから…時間を共に過ごして、少しづつお互いを理解する所から、私の仕事は始まります。
いい出会いに感謝して、またチャンスがあればさらにイイものをお伝え出来たらなぁ、と思いました。
男女バスケットボール部へストレッチングの指導をしました(^^)



学校の部活動で、直接、練習現場で指導するのは(ウチのチーム以外では)稀な活動です。そしてバスケット部の指導は初めて!
普段、バレーの現場で活動している事が多いのですが、競技が違えばウォームアップの取り入れ方や内容の違い、雰囲気も違います。
でも、アップの内容や構成が本当にしっかりしていて、かなり先生ご自身が勉強されているんだなぁ…という実感。
お話聞いていると…思い出しました!バスケットボールは指導者育成のシステムが確立されているので、アップやストレッチングに関してもトップから降りてくるモノを導入されているんですよね。。
観ているこちらも勉強になりました!
メニューは豊富ですが、個々それぞれ同じメニューのはずなのに、動きが違う。
これが何故なのか、どう改善していくのかを分析して、アドバイスしていくのが、私の仕事、という事になります。
今回は、「講習会」では絶対出来ない面白い時間でした。普段の練習の流れに順次ながら、いつもやっているストレッチングのフォーム指導や、ポイントを伝えたり…
先生が以前から気になってらっしゃった、時間の使い方の部分で、「この隙間の時間がもったいないので、何かストレッチングをさせたいんです」と目的をしっかり伝えて下さったので、実際のその時間に合わせて、その中で子供達にいろいろさせてみました。
私は入れ替わり立ち代り目の前にいる子供達に…目が回りましたが(笑)
最初は身体の使い方が分からなくて、悲鳴を上げていた子供達も…
さすが、中学生!習得が早い!
あちこちで、「出来た!」との声。嬉しいよね、出来なかった事が出来るようになるって。私もその笑顔は、嬉しい(^^)
身体が硬い、と思っていた子も、
身体の使い方一つで、どんどん身体が思うように動いていきます。
それが、バスケとどう繋がるか…までを観察する余裕は、今回なかったなぁ。
やはり個々で少しづつ伝えたいポイントや言葉の選択が違う…けどタイムオーバー!
最後は保護者や先生方も一緒に、クールダウンの指導とケアを兼ねたストレッチングの提供をさせていただきました。
先生方や、保護者の方々が日頃、少し疑問に思ってらっしゃった事などにも、お話しながらお答え出来たのかな?と。。
やはり、人間ですから…時間を共に過ごして、少しづつお互いを理解する所から、私の仕事は始まります。
いい出会いに感謝して、またチャンスがあればさらにイイものをお伝え出来たらなぁ、と思いました。
2015年05月25日
自分の身は、自分で守る
昨日、資格の継続研修を鹿児島で受けてきました。
日本赤十字社の救急法救急員の資格です。
この資格を初めて取得したのは、おそらく2000年。
日赤の資格は3年間有効。奇しくも更新は5回目、ということになります。
確か、この年のNSCA-CPT(NSCA公認パーソナルトレーナー)の受験をするのにCPR(心肺蘇生法)の資格保持が必須で、
受講したのがきっかけだと思います。
ここ数年で、継続研修が資格有効期間内ならば1日で終わるシステムになったため、
今回も、1日でめでたく資格を更新することができました。
トレーナーだから、という理由でこの資格を保持してきましたが、
最近の大災害や、先日の地震のことを思うと、
スポーツ現場だけでなく、もしかしたら自然災害などでも必要とされる知識なのでは?と
今回受講しながら思いました。
鹿児島県は、今年度から防災強化県として今後、学校関係で防災についての勉強会が行われる、と
指導員の方が言われていました。
火山や地震が多いからです。
そこで
「自助」「共助」「公助」
という言葉を掲げられていました。
東北の災害で、亡くなられた方の90%は即死だったといいます。
うち、生き残られた方の95%は「自助」と「共助」で生き延びられたとそうです。
自力でどうにか乗り切るか、周りの協力を得られて生き延びることができた。
「公助」、つまり消防や自衛隊など国の助けで生きられた方はたった5%。
県や国の助けを待っていたのでは、遅い、というデータが最近ようやく上がってきた、とのこと。
どういうことを意味するのか?
要するに、災害発生時は、「自分の身は、自分で守る」という事、だそうです。
それは、こういう知識を身につけておくことかもしれないし、
過信せず、早めに避難することかもしれないし、
日頃から体力をつけておくことかもしれないし、
その時が起こらないとわからないことなのかもしれないのですが、
「災害に対する意識を、もっと各自がもっておく」ということは今すぐできることなのかもしれません。
スポーツの現場についても、同様のことを思います。
ケガが起きない方がいい、予防が完璧にできれば問題ないのですが、
まず、絶対起こらないということは、ありえません。
スポーツ現場は、「ケガも起こりうる」ということを前提として、
大人は最低限の知識と技術を持っておくべきだと、
私は講習会の場で訴えます。
ケガや痛みに関しても、
必ず、痛みがひどくなる前には「サイン」が出ます。
疲れて、身体が疲労している状態でも「サイン」が出ます。
日頃から、その「サイン」に気づけるかどうかもやはり大事。
でも、その「サイン」に気づいても、訴えることができない環境、
頼る場所がわからないという現状は
日本のスポーツ界の、まだまだ大きな問題です。
でも、ケガの予防に対する意識を日頃から持っておけるかどうかで、
やはり選択肢は準備できるのではないでしょうか?
「自分の身は、自分で守る」
「生きる力」じゃないですけど、
やはり、スポーツ選手もスポーツが出来るだけでなく、
きちんと自己管理できる選手に育ててあげたいと思います。
日本赤十字社の救急法救急員の資格です。
この資格を初めて取得したのは、おそらく2000年。
日赤の資格は3年間有効。奇しくも更新は5回目、ということになります。
確か、この年のNSCA-CPT(NSCA公認パーソナルトレーナー)の受験をするのにCPR(心肺蘇生法)の資格保持が必須で、
受講したのがきっかけだと思います。
ここ数年で、継続研修が資格有効期間内ならば1日で終わるシステムになったため、
今回も、1日でめでたく資格を更新することができました。
トレーナーだから、という理由でこの資格を保持してきましたが、
最近の大災害や、先日の地震のことを思うと、
スポーツ現場だけでなく、もしかしたら自然災害などでも必要とされる知識なのでは?と
今回受講しながら思いました。
鹿児島県は、今年度から防災強化県として今後、学校関係で防災についての勉強会が行われる、と
指導員の方が言われていました。
火山や地震が多いからです。
そこで
「自助」「共助」「公助」
という言葉を掲げられていました。
東北の災害で、亡くなられた方の90%は即死だったといいます。
うち、生き残られた方の95%は「自助」と「共助」で生き延びられたとそうです。
自力でどうにか乗り切るか、周りの協力を得られて生き延びることができた。
「公助」、つまり消防や自衛隊など国の助けで生きられた方はたった5%。
県や国の助けを待っていたのでは、遅い、というデータが最近ようやく上がってきた、とのこと。
どういうことを意味するのか?
要するに、災害発生時は、「自分の身は、自分で守る」という事、だそうです。
それは、こういう知識を身につけておくことかもしれないし、
過信せず、早めに避難することかもしれないし、
日頃から体力をつけておくことかもしれないし、
その時が起こらないとわからないことなのかもしれないのですが、
「災害に対する意識を、もっと各自がもっておく」ということは今すぐできることなのかもしれません。
スポーツの現場についても、同様のことを思います。
ケガが起きない方がいい、予防が完璧にできれば問題ないのですが、
まず、絶対起こらないということは、ありえません。
スポーツ現場は、「ケガも起こりうる」ということを前提として、
大人は最低限の知識と技術を持っておくべきだと、
私は講習会の場で訴えます。
ケガや痛みに関しても、
必ず、痛みがひどくなる前には「サイン」が出ます。
疲れて、身体が疲労している状態でも「サイン」が出ます。
日頃から、その「サイン」に気づけるかどうかもやはり大事。
でも、その「サイン」に気づいても、訴えることができない環境、
頼る場所がわからないという現状は
日本のスポーツ界の、まだまだ大きな問題です。
でも、ケガの予防に対する意識を日頃から持っておけるかどうかで、
やはり選択肢は準備できるのではないでしょうか?
「自分の身は、自分で守る」
「生きる力」じゃないですけど、
やはり、スポーツ選手もスポーツが出来るだけでなく、
きちんと自己管理できる選手に育ててあげたいと思います。
2015年05月21日
競技力向上とケガ
ジュニア選手の痛みに関して、時々ご相談受けることがあります。
「捻った記憶はないけれど、練習後に足首が痛む」
「捻挫してアイシングをしたけれど、それからどうしてあげたらいいのか?」
「腰痛があるのだが、成長期の子供は整骨院などに連れて行ってもいいのか?」
「病院に連れて行った方がいいのか?整骨院などがいいのか?」
我が子が、痛みを訴える。
ささいな疑問でも、いざとなると、不安に感じたり、どう対応してあげたらいいのか、
何を選択したらいいのかわからない。
親としては、悩むところですよね。
私も、小学生の頃から、痛みを訴えて親を悩ませていた一人です。
中学生に至っては、腰痛で悩まされ、
高校でとうとう、ヘルニアの診断で入院。
なぜ、痛みが出たのかわからないけど、痛いと訴える。
「いい」と聞けば、母は私を治療に連れて行ってくれました。
今考えると・・・本当に親に迷惑かけてきたなあ・・・という思いです。
昨日は、以前からご相談を受けていたジュニア選手のもとを尋ねました。
診断は、「腰椎分離症」。いわゆる腰の骨に骨折の形跡がみられる
成長期特有のスポーツ障害の一つです。
ご連絡いただいたのは、その選手を指導されている先生から。
先生自身も、ネットで調べたり、整形外科での診断と指示に従われながら・・・
でも、「どうしたらいいのか、自分では対応できない」という判断でご相談いただいていました。
安静期間を経て、痛みもほぼ解消されていたようなので、
動作の確認をしながら、原因をみつけて、選手本人が出来る事を一緒にやってみました。
観ていて、怖かったかもしれませんね・・・今まで安静にしていた子がストレッチングでかなり身体を動かしていたので。。
でも、そのレベルで身体を動かせないと、競技でかかる負担はもっとですから・・・
痛みなく、自分のカラダをコントロールできることが大前提です。
ですが、本人も先生も「どこまで動かしていいのかわからない怖さ」があります。
ここが、競技復帰のむずかしさです。
私も、昨日の指導だけで、本人に伝わっているとは思わないし、
これから長い目で動作の確認をしていかないと、再発の可能性もあります。
どこまでそのことをお伝えできたかわかりませんが・・・
せっかくのご縁なので、遠慮なく呼んでもらえたらいいなと思います。
先生が呟かれた一言が心に響きました。
「いい能力を持った選手だと思うんですよ、でも私が焦っていたのでしょうね、こんな事になってしまって本当に申し訳なくて。」
素直な思いを、伝えて頂いて
競技力向上と健康のバランスの難しさを改めて感じます。
その為に、私達トレーナーという役割がいるのですが、まだまだそのように認識して頂くには活動や実績が足りないのでしょうね。。。黒子の立場なので決して目立ちはしないのですが、担う役割は大きいです。
どう、認識を広めようかなぁ…
地道にコツコツ、やるしかないですね!
「捻った記憶はないけれど、練習後に足首が痛む」
「捻挫してアイシングをしたけれど、それからどうしてあげたらいいのか?」
「腰痛があるのだが、成長期の子供は整骨院などに連れて行ってもいいのか?」
「病院に連れて行った方がいいのか?整骨院などがいいのか?」
我が子が、痛みを訴える。
ささいな疑問でも、いざとなると、不安に感じたり、どう対応してあげたらいいのか、
何を選択したらいいのかわからない。
親としては、悩むところですよね。
私も、小学生の頃から、痛みを訴えて親を悩ませていた一人です。
中学生に至っては、腰痛で悩まされ、
高校でとうとう、ヘルニアの診断で入院。
なぜ、痛みが出たのかわからないけど、痛いと訴える。
「いい」と聞けば、母は私を治療に連れて行ってくれました。
今考えると・・・本当に親に迷惑かけてきたなあ・・・という思いです。
昨日は、以前からご相談を受けていたジュニア選手のもとを尋ねました。
診断は、「腰椎分離症」。いわゆる腰の骨に骨折の形跡がみられる
成長期特有のスポーツ障害の一つです。
ご連絡いただいたのは、その選手を指導されている先生から。
先生自身も、ネットで調べたり、整形外科での診断と指示に従われながら・・・
でも、「どうしたらいいのか、自分では対応できない」という判断でご相談いただいていました。
安静期間を経て、痛みもほぼ解消されていたようなので、
動作の確認をしながら、原因をみつけて、選手本人が出来る事を一緒にやってみました。
観ていて、怖かったかもしれませんね・・・今まで安静にしていた子がストレッチングでかなり身体を動かしていたので。。
でも、そのレベルで身体を動かせないと、競技でかかる負担はもっとですから・・・
痛みなく、自分のカラダをコントロールできることが大前提です。
ですが、本人も先生も「どこまで動かしていいのかわからない怖さ」があります。
ここが、競技復帰のむずかしさです。
私も、昨日の指導だけで、本人に伝わっているとは思わないし、
これから長い目で動作の確認をしていかないと、再発の可能性もあります。
どこまでそのことをお伝えできたかわかりませんが・・・
せっかくのご縁なので、遠慮なく呼んでもらえたらいいなと思います。
先生が呟かれた一言が心に響きました。
「いい能力を持った選手だと思うんですよ、でも私が焦っていたのでしょうね、こんな事になってしまって本当に申し訳なくて。」
素直な思いを、伝えて頂いて
競技力向上と健康のバランスの難しさを改めて感じます。
その為に、私達トレーナーという役割がいるのですが、まだまだそのように認識して頂くには活動や実績が足りないのでしょうね。。。黒子の立場なので決して目立ちはしないのですが、担う役割は大きいです。
どう、認識を広めようかなぁ…
地道にコツコツ、やるしかないですね!
2015年05月11日
柔軟性と筋力のバランス
深く選手のカラダと付き合っていくと、最終的にはこの問題は非常に重要です。
「身体が硬いとケガをしやすい」
何をもって「硬い」とするか・・・ですが、
股関節の可動域が狭い、もしくは上手な股関節の動かし方を身体が知らない人は確かに痛みが出てきやすいです。
硬くても、適度な運動量ならば、問題はありませんが
無理がたたって、あちこちに痛みを抱える選手は少なくありません。
ですが、関節の硬さは筋力不足を補う「安定性」の確保の役割も果たします。
逆に関節の柔らかい人は、「安定性」が欠けるので、筋力がないと身体の負担も大きくなります。
つまり、身体が硬いから・・・といってストレッチングばかりやって柔軟性を高めすぎても
もともと備わっている筋力がなければ、「力が入らない」状態が起きる可能性があります。
とはいえ、一般的なストレッチングでは急激に柔軟性が高くなることはまずありません。
日々の積み重ねで可動域を高めながら、技術練習の幅を広げて、めいいっぱい身体を使う。
その刺激が、筋力強化にも繋がり、最終的にバランスよく柔軟性と筋力が高められるのかもしれません。
GW4日間、チーム帯同して選手のカラダの変化をみてきました。
ホント、人は「生もの」です。負荷のかかり方でどんどん変化していきます。
ですが、日々の積み重ね、トレーニングの効果は、少々のことでは崩れません。
周りの評価と、選手の評価と、自分の観る目がきちんと一致するような仕事は当たり前で
さらに、その先選手を、どのように成長させられるか布石を置けるような仕事が出来るように
精進していきたいと思うところです。
「身体が硬いとケガをしやすい」
何をもって「硬い」とするか・・・ですが、
股関節の可動域が狭い、もしくは上手な股関節の動かし方を身体が知らない人は確かに痛みが出てきやすいです。
硬くても、適度な運動量ならば、問題はありませんが
無理がたたって、あちこちに痛みを抱える選手は少なくありません。
ですが、関節の硬さは筋力不足を補う「安定性」の確保の役割も果たします。
逆に関節の柔らかい人は、「安定性」が欠けるので、筋力がないと身体の負担も大きくなります。
つまり、身体が硬いから・・・といってストレッチングばかりやって柔軟性を高めすぎても
もともと備わっている筋力がなければ、「力が入らない」状態が起きる可能性があります。
とはいえ、一般的なストレッチングでは急激に柔軟性が高くなることはまずありません。
日々の積み重ねで可動域を高めながら、技術練習の幅を広げて、めいいっぱい身体を使う。
その刺激が、筋力強化にも繋がり、最終的にバランスよく柔軟性と筋力が高められるのかもしれません。
GW4日間、チーム帯同して選手のカラダの変化をみてきました。
ホント、人は「生もの」です。負荷のかかり方でどんどん変化していきます。
ですが、日々の積み重ね、トレーニングの効果は、少々のことでは崩れません。
周りの評価と、選手の評価と、自分の観る目がきちんと一致するような仕事は当たり前で
さらに、その先選手を、どのように成長させられるか布石を置けるような仕事が出来るように
精進していきたいと思うところです。
2015年01月13日
動作の視点
いつも久々の投稿です。
それでも、いつも誰かがブログを覗いてくれているんだ。。。ということに気づいて、
ちょっとたまには自分史がてら、書いてみようと思います。
年始に恒例の母校の合宿へ。チームに帯同しました。
この合宿は、鹿屋OB、OGが関わるチームのみ参加できる合宿です。
要するに、この時期にこんなところにいるってことは、
春高には出場できなかった、ということですが・・・
それでも九州県内でもベスト4に入るチームも。
みんな、それぞれ頑張っているんだなあ、と嬉しく思います。
私にとって、毎年年始は「リセット」です。
自分の1年間を、いやこれまでを 『師匠』 に再会することで
確認したり、修正したり、時には180°考え方を変えることになったり、
今まで積み重ねたものを捨てたり・・・
決して、「答え」を頂けるわけではありません。
ただ、みて学ぶ。言葉を聞いて、キーワードを拾う。
話を聞く中で、自分の視野の狭さに気づかされる。
そして、自分はまだまだだ、と思い知らされる。
でも、不思議なもんで・・・こうした経験は確実に考え方が変わり、
選手の動き一つ、見えてくるものが変わってくるのです。
「スパイク打つ時、肩が痛いんです」
「どういう動作で痛いの?」
「ええっと、こういう時・・・」
と、選手が痛みを探す、この一瞬の行動の中に原因が隠されています。
師匠だったら、どうみるのかな・・・?
こういう気持ちになりつつも、この思考は逆に、自分の迷いになります。
洋服のしわのより方や、肘の捻り方や、体幹の動き・・・いや、肩の軟部組織自体の問題か?
ありとあらゆる、自分の今までの引き出しを引っ張ってみるのですが、
いや、やっぱ、違うんじゃね?他に見方はないのかな?とか。
試しに、師匠に何か観るポイントがあるのか?と聞いてみたら・・・
「そんなのは、その時で違うから、なんともいえない。自分なりにいろいろみてみたら。」
・・・・だよね(笑)。
そんな、モヤモヤが本当はとっても大事なことだと思うことにしています。
卒業以来初めて、図書館に行きました。
「トレーナーになりたい」
そう思って、大学時代に自ら本で学んだ場所が、大学の図書館です。
ここには、膨大な数の体育に関する本があります。
私にとっては、宝の山です。

改めて、沢山の本を眺めながら、自分はどうしたいのだろう?とふと思いました。
答えは、これまた何も見つからなかったけど、
今、自分がやるべきことは、ここで書物をあさることではなく、
選手をしっかりと向き合うことだ、ということは分かりました。
師匠には、ほど遠いけれど、
来年、もしまたお会いできるならば、もう少し成長している姿を見せたいな。
今年も、また1年が始まりました。
頑張ろう。

それでも、いつも誰かがブログを覗いてくれているんだ。。。ということに気づいて、
ちょっとたまには自分史がてら、書いてみようと思います。
年始に恒例の母校の合宿へ。チームに帯同しました。
この合宿は、鹿屋OB、OGが関わるチームのみ参加できる合宿です。
要するに、この時期にこんなところにいるってことは、
春高には出場できなかった、ということですが・・・
それでも九州県内でもベスト4に入るチームも。
みんな、それぞれ頑張っているんだなあ、と嬉しく思います。
私にとって、毎年年始は「リセット」です。
自分の1年間を、いやこれまでを 『師匠』 に再会することで
確認したり、修正したり、時には180°考え方を変えることになったり、
今まで積み重ねたものを捨てたり・・・
決して、「答え」を頂けるわけではありません。
ただ、みて学ぶ。言葉を聞いて、キーワードを拾う。
話を聞く中で、自分の視野の狭さに気づかされる。
そして、自分はまだまだだ、と思い知らされる。
でも、不思議なもんで・・・こうした経験は確実に考え方が変わり、
選手の動き一つ、見えてくるものが変わってくるのです。
「スパイク打つ時、肩が痛いんです」
「どういう動作で痛いの?」
「ええっと、こういう時・・・」
と、選手が痛みを探す、この一瞬の行動の中に原因が隠されています。
師匠だったら、どうみるのかな・・・?
こういう気持ちになりつつも、この思考は逆に、自分の迷いになります。
洋服のしわのより方や、肘の捻り方や、体幹の動き・・・いや、肩の軟部組織自体の問題か?
ありとあらゆる、自分の今までの引き出しを引っ張ってみるのですが、
いや、やっぱ、違うんじゃね?他に見方はないのかな?とか。
試しに、師匠に何か観るポイントがあるのか?と聞いてみたら・・・
「そんなのは、その時で違うから、なんともいえない。自分なりにいろいろみてみたら。」
・・・・だよね(笑)。
そんな、モヤモヤが本当はとっても大事なことだと思うことにしています。
卒業以来初めて、図書館に行きました。
「トレーナーになりたい」
そう思って、大学時代に自ら本で学んだ場所が、大学の図書館です。
ここには、膨大な数の体育に関する本があります。
私にとっては、宝の山です。

改めて、沢山の本を眺めながら、自分はどうしたいのだろう?とふと思いました。
答えは、これまた何も見つからなかったけど、
今、自分がやるべきことは、ここで書物をあさることではなく、
選手をしっかりと向き合うことだ、ということは分かりました。
師匠には、ほど遠いけれど、
来年、もしまたお会いできるならば、もう少し成長している姿を見せたいな。
今年も、また1年が始まりました。
頑張ろう。

2014年09月24日
第2回ASAテーピング講習会 終了!
第2回 ASAスポーツ講習会「足関節・膝のテーピング」
9月22日(月)19時~文化センター第一会議室にて行いました!


定員が40名でしたが、珍しく定員越えの46名のご参加いただきました。
会場の関係と、準備していたテープ個数の関係とで、
お断りさせていただいた方には大変申し訳ありません。
皆さん、テープにはある程度慣れてらっしゃる方が多かったように見受けました。皆さん、とてもお上手でした!
積極的にご質問下さり・・・特に「ヒールロック」と呼ばれる、踵部の固定テープの巻き方を
私は短時間に何回巻いたか・・・たぶん私が一番技術習得出来たと思っているところです。
うちのチーム(大高バレー部)のマネージャーのみくちゃんをサポートにつれていきました。
彼女は、この1年で本当に上手にテープを巻けるようになったので・・・
「私より絶対上手に巻かないように!」
と強く念を押して(笑)、デモンストレーションとお手伝いをしてくれました。
学生さんでも、チームのマネージャーにきちんと教育して、
にこうしてテープを扱える子がいると、本当に助かります。
もちろん、他のマネージャーもケガした選手にもちゃんとRICE処置してくれています。
前回の記事「水分補給」でも、彼女たちなりの、チームのスタイルに合ったフォローをしてくれます。
マネージャーも、監督、トレーナー同様、
「チームスタッフ」として選手が安全に、安心して練習が出来るようにサポートする役割を
スポーツ現場では担うのが大きな仕事の一つです。
「スポーツ」はどうしても、現場では選手の活躍が目に行きがちですが、
こういう「サポーター」も、なくてはならない役割だと思います。
きっと、スポーツのみならず、様々な部活やサークル活動も同様でしょうね。
・・・と話は講習会に戻りますが、
後半は膝のテーピングを「キネシオテープ」を使って行いました。
時間が十分あるつもりだったのですが、少し膝に関してはデモが中心になってしまい
わかり辛いところがあったと思い・・・反省です。
しかしながら、講義の中でも強調したのですが・・・膝のケガ(障害)は本当に原因が多面的で、
テープでは完全にフォロー出来ないなあ、と現場で対応する中での率直な感想です。
(ケガの種類も多様なので、限定的にテープを巻く方法をお伝えできない苦しさはありましたが・・・)
基本的な解剖と筋肉の走行を簡単に把握してもらって、
そこにサポートするような形で、資料をまとめさせてもらいました。
膝に関しては、そういう事情もあり・・・「下肢アライメント」の評価を踏まえて
少しお話させていただきました。
痛みの原因となる、簡単な「状態把握」です。
X脚とかO脚とか、扁平足とか・・・
日頃、目に見える形の骨格構造とケガとの関連性を簡単に紹介させてもらいました。
ご参加いただいた方の中で、このブログをご覧になっている方がいらっしゃいましたら・・・
この場を借りて、お礼申し上げます。
次回11月15日(土)三儀山サンドームにて19時~の予定です。
「アスレティックリハビリテーション」という
ケガした直後からスポーツ復帰までの『繋ぎ目』の期間に
選手は何を行うことができるか?というテーマで実技講習していきます。
「安静にしておいてくださいね」の期間にも、出来ることは山積みです。
興味ある方は、是非このブログもご覧くださいね。
ボチボチ、内容をアップしていきます。
9月22日(月)19時~文化センター第一会議室にて行いました!


定員が40名でしたが、珍しく定員越えの46名のご参加いただきました。
会場の関係と、準備していたテープ個数の関係とで、
お断りさせていただいた方には大変申し訳ありません。
皆さん、テープにはある程度慣れてらっしゃる方が多かったように見受けました。皆さん、とてもお上手でした!
積極的にご質問下さり・・・特に「ヒールロック」と呼ばれる、踵部の固定テープの巻き方を
私は短時間に何回巻いたか・・・たぶん私が一番技術習得出来たと思っているところです。
うちのチーム(大高バレー部)のマネージャーのみくちゃんをサポートにつれていきました。
彼女は、この1年で本当に上手にテープを巻けるようになったので・・・
「私より絶対上手に巻かないように!」
と強く念を押して(笑)、デモンストレーションとお手伝いをしてくれました。
学生さんでも、チームのマネージャーにきちんと教育して、
にこうしてテープを扱える子がいると、本当に助かります。
もちろん、他のマネージャーもケガした選手にもちゃんとRICE処置してくれています。
前回の記事「水分補給」でも、彼女たちなりの、チームのスタイルに合ったフォローをしてくれます。
マネージャーも、監督、トレーナー同様、
「チームスタッフ」として選手が安全に、安心して練習が出来るようにサポートする役割を
スポーツ現場では担うのが大きな仕事の一つです。
「スポーツ」はどうしても、現場では選手の活躍が目に行きがちですが、
こういう「サポーター」も、なくてはならない役割だと思います。
きっと、スポーツのみならず、様々な部活やサークル活動も同様でしょうね。
・・・と話は講習会に戻りますが、
後半は膝のテーピングを「キネシオテープ」を使って行いました。
時間が十分あるつもりだったのですが、少し膝に関してはデモが中心になってしまい
わかり辛いところがあったと思い・・・反省です。
しかしながら、講義の中でも強調したのですが・・・膝のケガ(障害)は本当に原因が多面的で、
テープでは完全にフォロー出来ないなあ、と現場で対応する中での率直な感想です。
(ケガの種類も多様なので、限定的にテープを巻く方法をお伝えできない苦しさはありましたが・・・)
基本的な解剖と筋肉の走行を簡単に把握してもらって、
そこにサポートするような形で、資料をまとめさせてもらいました。
膝に関しては、そういう事情もあり・・・「下肢アライメント」の評価を踏まえて
少しお話させていただきました。
痛みの原因となる、簡単な「状態把握」です。
X脚とかO脚とか、扁平足とか・・・
日頃、目に見える形の骨格構造とケガとの関連性を簡単に紹介させてもらいました。
ご参加いただいた方の中で、このブログをご覧になっている方がいらっしゃいましたら・・・
この場を借りて、お礼申し上げます。
次回11月15日(土)三儀山サンドームにて19時~の予定です。
「アスレティックリハビリテーション」という
ケガした直後からスポーツ復帰までの『繋ぎ目』の期間に
選手は何を行うことができるか?というテーマで実技講習していきます。
「安静にしておいてくださいね」の期間にも、出来ることは山積みです。
興味ある方は、是非このブログもご覧くださいね。
ボチボチ、内容をアップしていきます。
2014年09月14日
腰痛
腰に対する痛みや、不安感を持つ方は多いですね。
小学生からご年配の方まで、容体は様々。
私も、高校生の時に椎間板ヘルニアで1か月間入院生活を送りました。
小学校の時から腰に違和感を感じたり、痛みがあったりしました。
母が整骨院へちょこちょこ連れて行ってくれて、
飛び上がるほど痛いマッサージを受けていた記憶が・・・
中学校の時は、ゴムチューブを腰に巻いて、スポーツをしていましたし、
常に、腰のコルセットは高校時でも手放せなかったような気がします。
決して安価ではないMRI検査も何度もしました。
あの頃に自分に会えるなら・・・
ストレッチングとトレーニングを適切にアドバイスできることでしょうね・・・(笑)。
昨日はソフトボールのピッチャーをしている高校生の子が尋ねてきてくれました。
面白いなあと思って・・・趣向を変えて実際ボールを投げる姿から
原因を究明していきました。
腰というより背中のあたりの痛みだったのですが
「背中の丸さ」が一番の問題点でした。
いつもテープをあちこち貼ってみて、効率よい動きを導き出したり、
ストレッチングの具体的な指導の中で、自分のカラダと向き合ってもらうなかで
気づいたり、感じたりしながら・・・痛みのない感覚をつかんでもらいます。
(もちろん医学的に問題ない場合のみです)
さらに『痛みなくボールが投げられるようになる』 そして 『もっといいボールが投げられるようになる』
というところまで波及して、面白い反応が出ました。
パートナーで球を受けてくれた子がカラダの違いに気づいてくれました。
下半身が安定すると、上半身はスムーズに動きます。
本人の感覚と、球を受けてくれた子の感覚と、私の観た感覚がマッチしたことが
「自分でも治す事が、出来るのかな?」
と、
こういう機会に、自分の身体の事を考え、向き合って
さらに目標高く、練習に取り組む気持ちになって欲しいなぁと思います。
小学生からご年配の方まで、容体は様々。
私も、高校生の時に椎間板ヘルニアで1か月間入院生活を送りました。
小学校の時から腰に違和感を感じたり、痛みがあったりしました。
母が整骨院へちょこちょこ連れて行ってくれて、
飛び上がるほど痛いマッサージを受けていた記憶が・・・
中学校の時は、ゴムチューブを腰に巻いて、スポーツをしていましたし、
常に、腰のコルセットは高校時でも手放せなかったような気がします。
決して安価ではないMRI検査も何度もしました。
あの頃に自分に会えるなら・・・
ストレッチングとトレーニングを適切にアドバイスできることでしょうね・・・(笑)。
昨日はソフトボールのピッチャーをしている高校生の子が尋ねてきてくれました。
面白いなあと思って・・・趣向を変えて実際ボールを投げる姿から
原因を究明していきました。
腰というより背中のあたりの痛みだったのですが
「背中の丸さ」が一番の問題点でした。
いつもテープをあちこち貼ってみて、効率よい動きを導き出したり、
ストレッチングの具体的な指導の中で、自分のカラダと向き合ってもらうなかで
気づいたり、感じたりしながら・・・痛みのない感覚をつかんでもらいます。
(もちろん医学的に問題ない場合のみです)
さらに『痛みなくボールが投げられるようになる』 そして 『もっといいボールが投げられるようになる』
というところまで波及して、面白い反応が出ました。
パートナーで球を受けてくれた子がカラダの違いに気づいてくれました。
下半身が安定すると、上半身はスムーズに動きます。
本人の感覚と、球を受けてくれた子の感覚と、私の観た感覚がマッチしたことが
「自分でも治す事が、出来るのかな?」
と、
こういう機会に、自分の身体の事を考え、向き合って
さらに目標高く、練習に取り組む気持ちになって欲しいなぁと思います。
2014年08月01日
水分補給と熱中症予防
台風・・・長引きそうですね。
風と雨の中、朝から高校の練習に行ってきました。
最近、忙しくて久々にチームをみると、変化がよく見えて、発見が多く・・・
高校生でなくても、テープやちょっとしたストレッチングやトレーニングで変化をみることは出来るのですが、
トレーニングしている選手達の、潜在能力の出現はやっぱ本当に面白い!
カラダに負荷を与えて、それに耐えているからこそ!
やっぱり、スポーツの現場は、面白い。
私も、1人1人のカラダといつも「勝負」です。
ふと入口に目をやると、キーパーが3つ。

マネージャーに聞くと、麦茶、緑茶、それとスポーツドリンク用の水。
「今日の練習は3時間なので、後半スポーツドリンクを作る為です」
とのこと。
コートサイドにはいつものように個人用のボトルと、塩分と糖分補給の配慮でしょうね、
塩昆布、干し梅、黒糖が準備されていました。


熱中症、予防するための配慮です。毎年のことながら、感心です。
先日、「あまスポディ!ラックス」 明日8月2日放送分を収録してきました。
テーマは「熱中症予防・水分補給」についてです。

まだまだ、暑い夏はこれから!
涼しい場所でゆったりできれば別ですが、スポーツする人は
暑い環境で汗をしっかりかくのは避けられないわけですから・・・
カラダを元気に!高いパフォーマンスでプレーする為の
水分補給は、タイミングが大切です!
そんな情報をお伝えしている?つもりですが・・(さて、うまく喋れているかな?)
放送は土曜13:00~、再放送19:00~です。
風と雨の中、朝から高校の練習に行ってきました。
最近、忙しくて久々にチームをみると、変化がよく見えて、発見が多く・・・
高校生でなくても、テープやちょっとしたストレッチングやトレーニングで変化をみることは出来るのですが、
トレーニングしている選手達の、潜在能力の出現はやっぱ本当に面白い!
カラダに負荷を与えて、それに耐えているからこそ!
やっぱり、スポーツの現場は、面白い。
私も、1人1人のカラダといつも「勝負」です。
ふと入口に目をやると、キーパーが3つ。

マネージャーに聞くと、麦茶、緑茶、それとスポーツドリンク用の水。
「今日の練習は3時間なので、後半スポーツドリンクを作る為です」
とのこと。
コートサイドにはいつものように個人用のボトルと、塩分と糖分補給の配慮でしょうね、
塩昆布、干し梅、黒糖が準備されていました。


熱中症、予防するための配慮です。毎年のことながら、感心です。
先日、「あまスポディ!ラックス」 明日8月2日放送分を収録してきました。
テーマは「熱中症予防・水分補給」についてです。

まだまだ、暑い夏はこれから!
涼しい場所でゆったりできれば別ですが、スポーツする人は
暑い環境で汗をしっかりかくのは避けられないわけですから・・・
カラダを元気に!高いパフォーマンスでプレーする為の
水分補給は、タイミングが大切です!
そんな情報をお伝えしている?つもりですが・・(さて、うまく喋れているかな?)
放送は土曜13:00~、再放送19:00~です。
2014年06月16日
テーピング講習会!
昨日の午前中は、再三この場でも投稿してきた
ASA「スポーツ講習会」でした。



定員の約半数、20名の参加でしたが、
いや、こんなに来てくださると思ってなかったので、ビックリでしたよ、ホント!
内容は、今回は「手指・手首」に絞りました。
それでも、時間いっぱい・・・
本当は、「手指と足首」なんて夢の共演にすれば良かったのかもしれませんが、
中身が薄くなってしまうので、こだわりを貫きました。。
「プレ講習」が良かったんです。
ASAのスタッフさん、思ったよりもテープをうまく扱えなくて(笑)、
唯一専門学校時代にテーピングを習ったという上赤さんは、さすがでした!
そこで思ったのは
「普段、テープに触れない方でも巻けるようになるような講義にしよう」
もう一度、何度も自分でテープを巻いたりしながら順番確認し、
ポイントを押さえた内容を目指すきっかけになりました。
本当にスタンダードなテーピングの方法をベースに、
今回は、キネシオテープ、デニバン(デニム素材の伸縮テープ)を使って、
ホワイトテープとの固定感の違いを体験していただきました。
自分で巻くにしろ、人に巻いてあげるにしろ、
まず、自分で試してみる、自分の巻いたテープの固定感と、イメージが見合っているか、
というのは、
とても大切な事だと思います。
1㎝いや、5㎜テープを貼る場所が違っただけでも、
また強く引っ張るところ、軽くテープを乗せるところ・・・そういう工夫をすることで
格段に固定感が変わってくる。
そういう細かい・・・本当に「感覚」の世界を体験していただけたら、面白いと思っていました。
今回、最初に来られた受講者の方に・・・年配の女性の方でしたが、
受講された目的を、それとなく聞いてみました。
スポーツとか、そういう事はまったくされず、昔、流行った「テーピング」
今はそれほどでもない気がする。
自分はいいが、、孫たちに、何か役立つ日がくるのかな?と
「勉強しに来た」
とおっしゃられました。
私、ふと、自分のおばあちゃんの事を思い出して、心が温かくなりました。
いつまでも、「学ぶ」という姿勢を持たれている方、素晴らしいなあと最初から感動。
皆さん、それぞれのバックグラウンドは違いますが、
熱心に、実技を受けて帰られました。
有難いなあ。。
私は、ちゃんと何か伝えられたかな?
この講習を受講された方の繋がりで、
個人的にテーピングの巻き方を訪ねて来られた方もいらっしゃいました。
また、新聞での宣伝記事をみて、
研修をしたいとの依頼のお話も頂きました。
新しい出会いも、ありました。
新しい繋がりも、出来ました。
ここから、また皆さんが、勇気をもってテープを活用していただくことを願っています。
それが、誰かの心の支えとなり、喜びとなればいいな。
ASA「スポーツ講習会」でした。



定員の約半数、20名の参加でしたが、
いや、こんなに来てくださると思ってなかったので、ビックリでしたよ、ホント!
内容は、今回は「手指・手首」に絞りました。
それでも、時間いっぱい・・・
本当は、「手指と足首」なんて夢の共演にすれば良かったのかもしれませんが、
中身が薄くなってしまうので、こだわりを貫きました。。
「プレ講習」が良かったんです。
ASAのスタッフさん、思ったよりもテープをうまく扱えなくて(笑)、
唯一専門学校時代にテーピングを習ったという上赤さんは、さすがでした!
そこで思ったのは
「普段、テープに触れない方でも巻けるようになるような講義にしよう」
もう一度、何度も自分でテープを巻いたりしながら順番確認し、
ポイントを押さえた内容を目指すきっかけになりました。
本当にスタンダードなテーピングの方法をベースに、
今回は、キネシオテープ、デニバン(デニム素材の伸縮テープ)を使って、
ホワイトテープとの固定感の違いを体験していただきました。
自分で巻くにしろ、人に巻いてあげるにしろ、
まず、自分で試してみる、自分の巻いたテープの固定感と、イメージが見合っているか、
というのは、
とても大切な事だと思います。
1㎝いや、5㎜テープを貼る場所が違っただけでも、
また強く引っ張るところ、軽くテープを乗せるところ・・・そういう工夫をすることで
格段に固定感が変わってくる。
そういう細かい・・・本当に「感覚」の世界を体験していただけたら、面白いと思っていました。
今回、最初に来られた受講者の方に・・・年配の女性の方でしたが、
受講された目的を、それとなく聞いてみました。
スポーツとか、そういう事はまったくされず、昔、流行った「テーピング」
今はそれほどでもない気がする。
自分はいいが、、孫たちに、何か役立つ日がくるのかな?と
「勉強しに来た」
とおっしゃられました。
私、ふと、自分のおばあちゃんの事を思い出して、心が温かくなりました。
いつまでも、「学ぶ」という姿勢を持たれている方、素晴らしいなあと最初から感動。
皆さん、それぞれのバックグラウンドは違いますが、
熱心に、実技を受けて帰られました。
有難いなあ。。
私は、ちゃんと何か伝えられたかな?
この講習を受講された方の繋がりで、
個人的にテーピングの巻き方を訪ねて来られた方もいらっしゃいました。
また、新聞での宣伝記事をみて、
研修をしたいとの依頼のお話も頂きました。
新しい出会いも、ありました。
新しい繋がりも、出来ました。
ここから、また皆さんが、勇気をもってテープを活用していただくことを願っています。
それが、誰かの心の支えとなり、喜びとなればいいな。
2014年06月07日
手指と手首のテーピング固定
6月15日(日)に三儀山体育館武道場にて午前中
テーピングの講習会をやります!
ASA奄美スポーツアカデミー主催の第1回スポーツ講習会です。

今回は、主に「手指と手首」のテーピング実技講習です。
「指のテーピング、グルグル巻きしかしたことないわ」
という方は結構多いのではないでしょうか・・・
決して、グルグル巻いても、関節が固定されていれば間違いではありません。
「親指を突き指してしまって、なかなか治らない・・・」
という方はいませんか?
ほおっておくより、きちんとした巻き方をすれば、ある程度の痛みは軽減できます。
「テープの種類がいろいろあるけど、どういうときに、どのテープを選べばいいの?」
そういう疑問がちょっと心の奥にある方はいませんか?
テープにも使い方や目的があり、使い分けることで効果的に固定することができます。
スポーツを頑張っているお子さんや、選手の活動を日々支えるマネージャーさん、
スポーツ活動の指導に励まれている監督さん、自分で自分のケガもフォローしなければならない選手の皆さん、
治療院の患者さんに、少しアドバイスしてあげたいとおもう医療従事者の方々・・・
スポーツ現場では、どんなに注意をしていても、「ケガ」は起こりうることです。
大切な選手が「ケガ」してしまった時・・・
その選手にどんな声掛けや、どんなサポートや、どんなフォローが出来るか・・
考えてみたことは、ありませんか?
何か、私でも出来ることはあるんじゃないか?と思ったことはありませんか?
ケガや事故を予防する環境を整える事は、最も大切なことですが、
「ケガ」に関する基本的な知識を知っておくことも、私はとても大事な環境づくりだと信じて、
こういう「講習会」をさせていただいています。
これからPTAバレーや郡大会、子供さんのスポーツ少年団の大会など・・・
スポーツイベント満載の季節がやってきます。
「安全な環境」あってこそ楽しめるスポーツ。
万が一に備えて、どうぞ「脳に知識」を、そして「知識を実践」してみてください!
島で唯一行われている「スポーツ講習会」です。
申込み連絡先:ASA奄美スポーツアカデミー 0997-54-8687
ホームページ ASA奄美スポーツアカデミー 「お問い合わせ」より申込も可
テーピングの講習会をやります!
ASA奄美スポーツアカデミー主催の第1回スポーツ講習会です。

今回は、主に「手指と手首」のテーピング実技講習です。
「指のテーピング、グルグル巻きしかしたことないわ」
という方は結構多いのではないでしょうか・・・
決して、グルグル巻いても、関節が固定されていれば間違いではありません。
「親指を突き指してしまって、なかなか治らない・・・」
という方はいませんか?
ほおっておくより、きちんとした巻き方をすれば、ある程度の痛みは軽減できます。
「テープの種類がいろいろあるけど、どういうときに、どのテープを選べばいいの?」
そういう疑問がちょっと心の奥にある方はいませんか?
テープにも使い方や目的があり、使い分けることで効果的に固定することができます。
スポーツを頑張っているお子さんや、選手の活動を日々支えるマネージャーさん、
スポーツ活動の指導に励まれている監督さん、自分で自分のケガもフォローしなければならない選手の皆さん、
治療院の患者さんに、少しアドバイスしてあげたいとおもう医療従事者の方々・・・
スポーツ現場では、どんなに注意をしていても、「ケガ」は起こりうることです。
大切な選手が「ケガ」してしまった時・・・
その選手にどんな声掛けや、どんなサポートや、どんなフォローが出来るか・・
考えてみたことは、ありませんか?
何か、私でも出来ることはあるんじゃないか?と思ったことはありませんか?
ケガや事故を予防する環境を整える事は、最も大切なことですが、
「ケガ」に関する基本的な知識を知っておくことも、私はとても大事な環境づくりだと信じて、
こういう「講習会」をさせていただいています。
これからPTAバレーや郡大会、子供さんのスポーツ少年団の大会など・・・
スポーツイベント満載の季節がやってきます。
「安全な環境」あってこそ楽しめるスポーツ。
万が一に備えて、どうぞ「脳に知識」を、そして「知識を実践」してみてください!
島で唯一行われている「スポーツ講習会」です。
申込み連絡先:ASA奄美スポーツアカデミー 0997-54-8687
ホームページ ASA奄美スポーツアカデミー 「お問い合わせ」より申込も可
2014年05月20日
ASAスポーツ講習会
今年度も担当させていただくことになりました
「ASA スポーツ講習会」
平成26年度 第1回は
「テーピングの実技講習会(指・手首)」です♪

「足関節捻挫のテーピング」はあちこちでやっているのですが~
意外と普段使うことが多いのは、指とか、手首、とかなのかな?と現場にいて思います。
それに、” 自分で出来る ・自分で巻ける ”というお手軽さが、テープになじみ深い?というか・・・
それゆえに、「巻けばいい」と思ってしまい、結構巻き方のポイントを知らない・・・というのもこの部位の特徴です。
なので・・・あえて第一回に 「指・手首のテーピングの実技」を持ってきました!
ちなみに、次回は「足・膝のテーピング」を予定しております!
実は私も今テーピングが手放せない・・・(涙)
先月フットサルの大会に初めて出たら、みごとに左薬指の2度も突き指してしまい・・・
幸か不幸か、現在も結婚指輪が外せないほど関節が腫れています。
病院には行かなかったんですけど、たぶん酷いことやってしまっていたのでしょうね。
やはり、バレーとかすると怖いので固定をしています。
自分のは面倒なので単に 「ぐるぐる」と巻いてみたのですが、
ややや・・・これではまだ痛いぞ。
面倒だけど、きちんと固定したら、やっぱ違う!!!痛くなーい(笑)。
わざとらしい文ですが、ホントの話です!
ってな感じで「再発予防のテーピング」。これが本来正しいテープの使い方です。
6月15日開催日までも、ちょこちょこ・・・宣伝がてらテーピングにまつわる話を載せていきたいと思います!
今回も予約制ですが、電話予約だけでなく
ASAホームページ
からも「お問い合わせ」でメール予約できるようになりました!
お気軽に、ご連絡くださいね♪
「ASA スポーツ講習会」
平成26年度 第1回は
「テーピングの実技講習会(指・手首)」です♪

「足関節捻挫のテーピング」はあちこちでやっているのですが~
意外と普段使うことが多いのは、指とか、手首、とかなのかな?と現場にいて思います。
それに、” 自分で出来る ・自分で巻ける ”というお手軽さが、テープになじみ深い?というか・・・
それゆえに、「巻けばいい」と思ってしまい、結構巻き方のポイントを知らない・・・というのもこの部位の特徴です。
なので・・・あえて第一回に 「指・手首のテーピングの実技」を持ってきました!
ちなみに、次回は「足・膝のテーピング」を予定しております!
実は私も今テーピングが手放せない・・・(涙)
先月フットサルの大会に初めて出たら、みごとに左薬指の2度も突き指してしまい・・・
幸か不幸か、現在も結婚指輪が外せないほど関節が腫れています。
病院には行かなかったんですけど、たぶん酷いことやってしまっていたのでしょうね。
やはり、バレーとかすると怖いので固定をしています。
自分のは面倒なので単に 「ぐるぐる」と巻いてみたのですが、
ややや・・・これではまだ痛いぞ。
面倒だけど、きちんと固定したら、やっぱ違う!!!痛くなーい(笑)。
わざとらしい文ですが、ホントの話です!
ってな感じで「再発予防のテーピング」。これが本来正しいテープの使い方です。
6月15日開催日までも、ちょこちょこ・・・宣伝がてらテーピングにまつわる話を載せていきたいと思います!
今回も予約制ですが、電話予約だけでなく
ASAホームページ
からも「お問い合わせ」でメール予約できるようになりました!
お気軽に、ご連絡くださいね♪